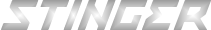『スクーデリア一方通行』の筆者である加瀬竜哉/本名加瀬龍哉さんが急逝されました。長い闘病生活を送りながら外には一切知らせず、“いつかガンを克服したことを自慢するんだ”と家族や関係者に語っていたとのことですが、2012年1月24日、音楽プロデュサーとして作業中に倒れ、帰らぬ人となりました。
[STINGER-VILLAGE]では、加瀬さんのなみなみならぬレースへの思いを継承し、より多くの方に加瀬さんの愛したF1を中心とするモーターレーシングを深く知っていただくために、“スクイチ”を永久保存とさせていただきました。
[STINGER-VILLAGE]村長 山口正己
Wildest Dream~見果てぬ夢~ 第二章
スクーデリア・一方通行/加瀬竜哉書き下ろしweb小説・特別集中連載
「Wildest Dream〜見果てぬ夢〜」
 第二章・反逆
第二章・反逆
火曜夜。
F1モナコGPの週末に向け、モンテカルロ市街地サーキットはグランプリ開催準備に余念がない。先週までただの街角だった交差点はF1マシンの走行のために特別なガード・レールによってコース割が施され、グランプリを彩る様々な企業看板が並び、足場を組立てた簡易観戦スタンドが建てられる。その様はあまりにも特殊で、街全体、いや国全体が巨大な祭りの準備をしている、と言っても過言ではない。
「アグーロ!。セナが勝ったレースで、ここでスピンしてたのを覚えてるよ!」
明らかに酒に酔った2人組の男が、反対車線側から赤いフェラーリの帽子を振りながら上機嫌で声をかけて来る。
「ハハハ。サンキュ!。」
前夜のテレビ報道により、今やモナコでも「時の人」となってしまった感のあるTSJの面々。特にスポーティング・ディレクターと言う位置付けの鈴石亜久郎は1990年代にモナコに住み、そしてレースで自らの暮らす街を走っていたと言う特殊な経歴を持つ。
「毎朝、カーテンを開けて眺める景色の中を600馬力のエンジン背負って突っ走るんだ。そりゃまともじゃないよねえ」
海岸に浮かぶ多くのクルーザーのシルエットを眺めながら、鈴石は懐かしそうに呟いた。パパラッチが気になる大椋だったが、ヨーロッパのレース・ファンのフランクさに、やや安心の表情を浮かべた。
「それにしても、いったい誰が考えたんですかね」
「ん?、何を?」
「モナコGPを、ですよ。だいたい一般道でレース、ってだけでもまともじゃないのに、よりによってF1を、よりによってこの狭いモナコで、ですよ。普通に競争前提で考えたら、こんなに無茶なレースはない筈なのに」
「普通も何も、実際無茶だよ。だって、ロウズ・ホテルのヘアピンなんてステアリング目一杯切んなきゃ曲がんないし、トンネルなんか何も見えやしないし。だいたいここじゃ、ぶつけなきゃ絶対抜けない。そりゃ50年前も俺ん時も今も一緒」
「なのに、何でずっとやってんですかね」
「ま、モナコって言う豪華な国がある。そこに金持ちが集まる。クルマを見せびらかす。人が集まって来た。ちょっと走らそうか。ついでに順位つけちゃえば立派なイベントになるな、てのが基本理念。まず競争じゃなく、まずイベント。それが高貴なヨーロッパの連中の考え方。こりゃ敗戦国ニッポンには存在しなかった価値観だ」
「まあ、確かにそうですけど…」
「でさ、そこに抜ける筈のないようなこんな面倒なコースで、神懸かり的なドライビングを見せる奴が、たまに現れる。ヒルとかセナとかシューマッハー、みたいな、ね。だからいつまでもレースとして成り立ってんだ。で、俺はそう言う伝説にゃなれなかった、と」
「92年の11位が最高でしたっけ。フットワークでしたよね」
「良く覚えてんな、そんなの」
「あの時も日の丸っぽい赤白のカラーリングで…何と言うか、ナショナリズムでしたねえ」
「あのね、こっちにはそう言う概念がないの。ブラジル人のセナがイギリスのマクラーレンと日本のホンダでフランス人のプロストに勝てば良いの。なんか、日本は『世界を相手に』とか『ヨーロッパを股にかけて』とか、相手を勝手に大きくしてるんだよな。実際にはもっと身近なさ、眼の前のガキ大将をどうやってやっつけるか、そのためにどんな道具を使ってやろうか、みたいなさ。フェラーリだって、イタリアがヨーロッパでナンバー1だ、近所のイギリスとかフランスのクルマにゃ負けない、って言う感覚。もう根本から違うわけ。それを、なんか『大和魂』みたいので立ち向かっちゃうと、ちょっと空回りしちゃうんだよ」
実際モナコと言うヨーロッパ都市に暮らし、世界最高のF1グランプリのドライバーとして闘い、自らチームを率いた経験のある鈴石ならではの見方だった。
「日本は、特に企業が絡むとそうは行かなくなってしまってましたもんね」
「そりゃあそうだよ。参戦する側の自動車産業は当然のこと、スポンサーも皆そこに利益を求めて集まって来る。だがソイツはドライバーの、さっき言った『個人的な喧嘩』みたいな部分とは無関係。だから難しい。昨日まで赤白のマルボロ・カラーだったセナが今日から青いロスマンズ、みたいな感覚が当時の我々には理解出来なかった。ナショナリズムでやっちゃうからなんだよね。セナは、隣にいるプロストからチャンピオン・フラッグを奪いたいだけだった。だから何でも出来たんだよ」
「…どうしました?」
鈴石はふと立ち止まり、沖の夕闇を見つめて大きく息を吐いた。
「…でもさ、俺達の世代にゃ、結局それしか出来ないんだ。日本を背負っちゃった、って言うのかな。中嶋さんもそうだったけど、現場とブームの温度差は大きかった。バブル景気だったし、それこそ日本は『F1ブーム』だったから、この巨大なスポーツ・イベントに誰もが押し掛けて、それが全て、みたいになっちゃった。…ただひとりを除いて、ね」
「ただひとり…あの人ですよね」
「そ。あの人」
…星田一俊。TSJのチーム監督であり、かつて「日本一速い男」の名を欲しいままにした不世出の名レーサーは、1976年、日本に初めてF1レースがやって来た時、ヨーロッパのドライバーを迎え撃つべく地元・日本からエントリーした、言わば日本のF1ドライバーの草分けである。しかも初レースとなった富士では予選21番手から雨の中奇跡の追い上げを見せて3位まで上昇、しかし雨が上がった際、ドライ・タイヤが足りずに無念のリタイアとなり、幻の表彰台となった伝説を持つ。
以後国内レースでは無敵を誇った星田だったが、1987年以降の所謂「F1ブーム」とは縁がなかった。もちろん年齢/実力的には申し分なかった筈だが、ホンダやトヨタがF1に挑戦するのを尻目に、契約していたメーカーがF1進出を行わなかったのが大きくキャリアに響き、以後F1に乗ることはなく、2002年に現役を引退していた。
環境、タイミング、想い。全てのバランスが星田をF1には導かなかったのである。
「でもあの人にもそう言うチャンスはあった」
「もちろん」
「でも…乗らなかった」
「そう。乗らなかった。乗れなかったんじゃなく、乗らなかったんだ」
「1990年の鈴鹿で、トップ・チームのベネトンからヘリコプターの事故で出れなくなったナニーニの代わりを打診されて、その時にベネトンは当然のように持込資金を要求したけど、俺はプロのレーサーだから、例え2万円でも貰わなきゃ乗らない、って言ったと言う話がありますね」
「それが本当かどうか知らないけどさ、そんな噂が出るところが如何にも星田さんらしいじゃない」
「ところで、そのレースで…」
「そう、俺がF1で唯一の表彰台に乗ったレース」
「ちなみにナニーニの代役にロベルト・モレノが乗ったベネトンは…」
「俺の前。つまりベネトンの1-2フィニッシュだった。優勝は3度の世界王者、ネルソン・ピケ」
「つまり、もし星田さんが乗ってたら…」
「ハハハ。好きだねえ、そんな話」
「だって、悔しいじゃないですか」
「悔しい、か。…それはちょっと違うかも知れないね。エディ・アーバインとかフレンツェンとかがF1の記者会見で『日本には俺達が適わないとんでもないレーサーがいる』って星田さんのことを自慢してたんだけどさ、あの人は自分のキャリアを誇りにしてると思うよ。F1どうのこうの、ってのはあくまでも周りが言うだけで、あの人自身はそんなこと気にしてないさ」
「うーん…もしも星田さんがF1に乗ってたら、って、やっぱり考えちゃいますよね」
「F1だけが全てじゃないさ」
鈴石は自身が日本人初のF1表彰台経験者だが、キャリア2年目にそのピークを迎えていた。当然3年目以降はそれ以上の成績を目指し、チーム体制なども含めてステップ・アップする筈だった。しかし上手く行かず、不本意な現役引退を迎える。その後ホンダのバック・アップで自己の名を冠したF1チームを結成、だが肝心のホンダが経済不況を理由にF1から手を退き、鈴石のチームもまた経営不振で撤退を余儀なくされた経緯を持つ。
「そう考えると、ウチは本当にドリーム・チームじゃないですか」
「少なくとも日本のレース界を支えて来た人達が集まってるのは確かだよ。ただ、タイミングは本当に最悪だった。経験もノウハウも申し分ないのに、それを回すための環境がない。FIAもなんとか予算を下げようと努力してくれたけど、それに報いることは…出来なかった」
話が弾んでいた鈴石と大椋だったが、ふと前夜にF1からの撤退が決まったばかりだった現実に帰った。
「ま、結局のところはF1はあまりにも特殊なところ。でも、フェラーリとかマクラーレンとかの連中は、それが当たり前の生活をしてるの。この非・日常のF1が日常…羨ましいねえ」
大椋の携帯が鳴った。
「おっと、このタイミングでの広報からの電話はロクな話じゃないんだ。はい、もしもし…何だって!?」
「はあ…ま、もう大抵のことじゃ驚かないけどね…」
鈴石は以前暮らしたサン・デ・ボーテのマンションを見上げて苦笑いした。
「…風間がホテルに戻って来たそうです」
「ハッハッハ。アイツ、日本に帰ったんじゃなかったのか」
「星田さんと話したい、と言って待ってるらしいです」
「よし、俺も行こう。あの我侭ボーイの面倒は星田さんひとりじゃ無理だ」
「はい」
鈴石と大椋は今来た道を足早に戻る羽目になった。
TSJのドライバー、風間裕人は大股開きでホテルの部屋のソファに座り、髪の毛を掻きむしりながら足を激しく揺すっていた。この若きレーサー、いやレーサー兼二枚目タレントは明らかに「我慢」が苦手なタイプだった。それもその筈、裕福な家庭に育ち、学生時代からチヤホヤされて来た典型的なお坊っちゃまである風間は、例え相手が誰であろうとも怯まないその強さだけは高い評価を得ていた。
「よう、何の用だ?」
ノックもなく部屋に入って来た星田は風間の対面には座らず、ソファの後を素通りして窓へと向い、やや乱暴気味にカーテンを開けた。その空気の流れに、風間のイライラは一層増したようだった。
「何で帰って来たのか、聞かないんですか」
「ん?、聞いて欲しいのか?」
星田は笑いながら上着を脱ぎ捨て、聞いた。自分のペースで物事が進まなくなった時、風間の髪を掻きむしる仕草はより激しさを増す。
「昨夜は飛行機の出発が2時間も遅れましてね。とてもじゃないけど待ってらんないから、そのままマネージャーとカジノに行って…」
「何の用かを聞いてるんだが」
話を制された風間はわざと星田に聞こえるようにチッと舌打ちし、勢いあまってソファから立ち上がった。
「いくらこれが最後だからって、ドライバーがいないんじゃチームだって困るでしょう。こんな形は不本意だけど、契約だってあるし、だいたい僕がいなきゃ初めから話になんないんだから」
「いや、そんなことはないさ。既に昨夜、複数のドライバーから我々のシートに関する問い合わせがあった」
「誰からです?、何って答えたんですか?」
「君には関係ない。それこそ秘密保持は契約上の義務だ。そんなこと解ってるだろう?」
風間は憤慨し、星田に対してこれ見よがしに、わざと倒れ込むような姿勢でソファに座り直した。
「忘れないで欲しいな。TSJは僕のためのチームだ。僕を中心にプロジェクトが立ち上げられ、僕のためにスポンサーが動き、僕を走らせるために存在するんだ」
ここまで風間と眼を合わせなかった星田が、突如鬼のような形相で風間を睨みつけた。
「ふざけるな!。だったら何故ひとりで帰ろうとした?、チーム全員が問題に直面し、闘っている時に、どうしてオマエだけが逃げ出せるんだ。それで良くチームだなんて言えるな?」
「あんな話を聞かされたら、誰だってその場から逃げ出したくなるでしょう」
「いや、オマエ以外、誰ひとり逃げ出さなかった。全員で問題を受け止め、今後どうするべきかを話し合った。スタッフだけじゃない、ジョナサンもだ」
「だいたいこれは僕の責任じゃない。どうして僕がそこにいなくちゃいけないんだ。僕達ドライバーのために問題を解決するのがチームの仕事でしょう?」
「ピンチに一目散に逃げ出すような奴のために、誰が必死に取り組むと言うんだ!?」
予想に反し、あまりにもエキサイトした星田の声に驚きながら鈴石と大椋が急ぎ部屋に入って来た。
「いい加減にしてくれ。僕はスターだ。スターを輝かせるために、スタッフは一丸となってチームを強くする。それが当たり前のことでしょう」
「確かにオマエはスターさ。ドライバーはレーシング・チームの花形だ。そのことに異論はない。ただ、そのスターもチームの一員なんだ。皆が同じように働き、上を目指し、闘う。そこに優劣などないんだ。オマエはそれを解っていない。自分は悪くない、周りが悪い、と繰り返すばかりだった。それではチームにならない。まして勝負にはならないんだよ」
珍しくエキサイトする星田の姿に、鈴石も大椋も唖然となっていた。が、その状況が今後の、まして眼の前に迫ったF1モナコGPに良い影響を及ぼさないことだけは明らかだった。
「星田さん、もう…」
「裕人、いい加減にしろ。何処まで勝手なことをすれば気が済むんだ」
「ああもう、いい加減にしてよ。僕のF1レーサー計画は、この愚かな集団のせいで台無しだ」
「…何だと!」
星田が風間に殴りかかるよりも前に、小さな瞳から大粒の涙をこぼしながら、大椋が風間の胸ぐらを掴んでいた。
「お前なんか、お前なんかに…星田さんの気持ちが解ってたまるか!」
「大椋、やめろ」
今度は星田が大椋を制した。しかし更にふたりに割って入るように、今度は鈴石が静かに話し始めた。
「星田さんがかつて『日本一速い男』と呼ばれたことは、流石にまだ生まれていなかったお前でも知ってるだろう。俺達全員が束になって向って行っても、この人には適わなかった。が、俺達日本人がF1と言うモーター・スポーツの最高峰にようやく行きついた時、運命は星田さんに残酷だった」
「よさないか、鈴石」
星田は冷静になり、ようやくソファに座った。風間は乱れた髪を直す仕草を見せたが、そこにいる誰とも眼を合わさなかった。
「いや、言わせて貰います…中嶋さんや俺や右京を初め、色んな人がこの最高峰カテゴリーに挑戦して行った。そして、確かにホンダやブリヂストンのような企業は成功したかも知れないが、これまでドライバーの成功者は出なかったのは知っての通りだ。しかしそれは、もしかしたら星田さんだったら出来たかも知れないことだった。もちろん時代が、文化が、性能がモノを言う世界だ。しかしこの人はまだF1が日本に定着する以前、決して勝てるとは言えない体制で彼等に挑み、素晴らしいレースを魅せてくれた人なんだ」
大椋の息づかいが落ち着くと、その場にいた全員がやや平静さを取り戻し、一瞬の静けさが部屋を包んだ。
「…ほんの小さなことなんだ。そのほんの小さな歯車の狂いが、歴史に大きく影響した。1976年の富士で、本当にこの人は世界を相手に闘い、そして勝てたかも知れなかったんだ」
「もういい、鈴石。今更な話だ」
「いや、俺はこの若僧に、多くの人が築き上げて来た歴史の重みを解らせたいんだ。誰でもポンと行って出来ることではない、その中には多くの紆余曲折があり、多大なる年月をかけ、多くの人々が挑戦して、今がある。そして笑った人もいれば、泣いた人もいるんだ。と言うことを」
「へっ、冗談じゃない」
鈴石が話終らない内に、風間は再び激しく髪を掻きむしり始めた。
「だから何なんですか。そんな話は僕には関係ない。今は21世紀なんだ。自動車メーカーがどうの、負けた人がどうの、なんて話に興味はないね」
「何だと」
鈴石が声を荒げる。
「もういい。勝てなかったのは事実だ」
「浪花節なら勝手にやって下さいよ。僕には関係ないことだ」
鈴石が眼を合わさぬまま風間に問いかける。
「裕人、最後にもう1度だけ聞く。何しに帰って来た?」
「帰って来た?。違いますよ。TSJは僕のためのチームだ。僕がいなきゃ意味がないからここにいるんだ」
「解った」
ふっと笑みにも似た一呼吸を置き、鈴石の拳が風間の頬を捉え…いや、正確にはヒットする直前に星田の右手が鈴石の拳を受け止め、風間は両手で頭を抱えて震えていた。
「今すぐ出て行け、裕人。たった今、俺の一存で貴様は解雇だ」
「鈴石さん!そんなことしたらモナコGPが…」
「かまわん。我々にはジョナサンがいる。もうこんな馬鹿野郎は必要ない。とっとと日本に帰ればいい」
「フッ、ハッハッハ。鈴石さん、今日のことは良く覚えておいて下さいよ。どんなことになっても僕は知らな…」
「さっさと出て行け!」
一瞬の間を置き、風間裕人は思い切りドアを閉めながら部屋を出て行った。部屋に残された3人は誰もその場から動かなかった。
「いいんですか、鈴石さん」
大椋が袖で頬を拭きながら聞いた。
「良くなんかないさ。ないけど、アイツはもうチームの一員じゃない。ついでに、スポンサーが離れる以上、もう裕人に拘る必要はない」
「でも、このレースまでは電脳の資金でやってるんです。これじゃ明日から一切の資金調達が出来なくなるかも知れない」
「そんなことはどうでもいい。…星田さん、俺は間違ってますか」
星田は一点を見つめたままだった。
「解らん。が、少なくともこれでまた失うものがひとつ増えたことは事実だ」
「…。」
再び部屋を静寂が包んだ。そこへ、TSJのエグゼクティヴ・ディレクターである桜田繁敏が大股で入って来た。
「騒々しいと思ったら、やっぱりこんなことか。坊っちゃん、あの剣幕じゃ今度こそ帰って来ねえぞ」
「もういいんです。奴はたった今、解雇しましたから」
鈴石が深呼吸をしながら呟く。
「ま、あのくらい虚勢を張る方が、世界を相手に闘うには意外にいいのかも知れん。いつの日かF1チャンピオンになってるかも知れないぞ」
「俺達は…古いんですかね」
鈴石の口元が緩んだ。
「もちろん古いさ。だから集まるんじゃねえかな。浪花節もお得意、お涙頂戴大歓迎だ」
「桜田さんにはかなわんな」
ようやく星田が落ち着きを取り戻し、笑みがこぼれた。
「大椋、ミーティング続きで悪いが、また林田さん達を呼んでくれ。事の顛末をボスに知らせなきゃならん。それともちろん、ジョナサンもだ」
「解りました」
現場人間の桜田が部屋の空気を変える。
「セナが来たっけな」
「…1987年ですか」
またも大椋が食いつく。
「ああ。ルノーで走ってんのに、『どうしてもホンダ・エンジンで走りたい』って、監督の泊まってるホテルまで押し掛けて来たんだ。あのストイックさにゃ誰も適わないね…ハハ、どうしてこう、想い出話になっちゃうかな。さ、レースの準備だ。天下のモナコGPだぜ!」
ムード・メーカーの大きな声は部屋中に響いた。しかし、そこにいる誰もがその言葉にひとことも返せずにいた。
次回に続く。
※この物語はフィクションです。