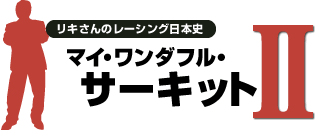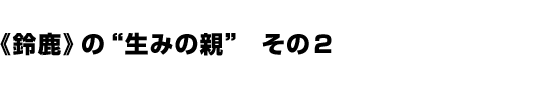1956年、欧州視察旅行の時点で、ホンダ副社長・藤沢武夫には、原付自転車に代わるべき新商品をつくらなければダメだ、という方向からだったとはいえ、かなり具体的なイメージはあったようだ。
その背景にあったのは、50年代の後半、自転車も二輪車(バイク)も、荷物運びの運搬具から脱して、「乗用志向」が生まれていたこと。大久保さんは言う。
「自転車も、若者を中心に『サイクリング』が広まって、軽快なスポーツ車がウケはじめていた。サイクリングをテーマにした歌謡曲のヒットもあったけどね」
このように自転車に乗用志向が強まれば、これにエンジンを付けようという人はいなくなる。それに伴って、“後付け”のカブ・エンジンは商品性を失う。これが藤沢武夫の危機感だった。
「藤沢さんは、これも伝説になりつつあるんだけど、本田さんに、『蕎麦屋の出前が、オカモチを持って、片手で運転できるもの』というコンセプトを与えた」
「自転車ではなくて、ちゃんとしたオートバイとしてのボディがあって、でも50ccで、二輪需要の底辺を広げるもの、ですね」(大久保)
……うーん、このへんは若干、時代背景の説明が要るかもしれない。
まず、いまの「宅配ピザ」をイメージしてほしいが、当時、日本蕎麦の店は「出前」(宅配)をするのが普通だった。そして、蕎麦がノビる前にということで、注文先まで、蕎麦屋の若手店員が自転車で“急行”した。
「オカモチ」(岡持)というのは、そのときに蕎麦などを入れて運ぶためのハコで、それを左手で下げ、自転車を片手で運転して、蕎麦をデリバリーしていたのだ。
たとえば、全国の蕎麦屋のすべてが、自転車に代えて、ホンダがこれからつくる“新しい乗りもの”に買い換えてくれたら? これが、藤沢武夫にとっての「底辺の広がり」の、具体的なイメージのひとつだった。
「この頃の欧州で、たとえばドイツは、すでに多彩な50cc車があって、各社が競っていた。まあ敗戦で、大排気量のエンジン製作が占領軍によって禁止されていたこともあったんだけど」
こう言いながらリキさん(大久保力)は、当時のドイツのメーカー名を列挙した。DKW、ハインケル、クライドラー、マイコ、ハーキュレス、TWN、ビクトリア……。そして、なかでも、「『NSUクイックリー』は、月産2万台以上の生産を誇る、ドイツ・モペットの代表機種だった」
◆スーパーカブの爆発的なヒットが、新工場を求めた
「一方でイタリアは、映画『ローマの休日』でもわかるように、スクーター王国でした」
この映画で“主役”を演じたのはベスパだったが、これ以外にも、ランブレッタ、ジレーラ、モトグッツィといったスクーターのブランドがあって、覇を競っていた。
またイタリアでは、ペダル付きシクロ(自転車)やモペットなどの50cc車が盛んであり、この分野には、ビアンキ、モンディアル、イソ、MVアグスタ、パリラといったメーカーが参入していた。
さらには、イタリアには1950年代のこの時点で、すでに「アルピーノ・ツーリング」や「ジレーラ50」などのように、50cc車を「スポーツとしての乗りもの」(リキさん)に仕上げて楽しんでいるという状況もあった。
さらに、リキさんはつづけた。
「フランスもね、ちょっと意外かもしれないけど(笑)、この時代って、世界一のオートバイ王国だったんです」
この時期のフランスの二輪、その50%強は「モペット」であり、自転車+エンジンというものが多かったが、それが完全に日常の足として、「社会生活の用具になっていた」と、リキさんは言う。
ブランドでいうと、モトベカーヌ、プジョー、アルション、フォリ、モネーゴワイヨン、テローなどで、これらが実用に徹した二輪(モペット)をつくって、カスタマーに提供していた。
また、これらの国以外でも、ベルギー、オランダ、デンマーク、スウェーデン、オーストリア、旧・東ドイツでも、それぞれのニーズに合わせて、さまざまな「二輪車」がつくられていたと、リキさんは語る。
藤沢武夫と本田宗一郎の二人は、このような“欧州事情”を肌で感じながら、長い旅をつづけていた。
だが藤沢は、ヨーロッパでいうシクロやモペットを、そのまま日本で展開すればそれでいいとは、まったく思っていなかった。

1947年、自転車にエンジンをつけただけの“Model A”。
たとえば、日本の(当時の)道路事情では、絶対にサスペンションは必要! しかし、運転の操作は(自転車のように)簡単であるべきだ。さらには、小径ホイールのスクーターよりもずっと安定した走行性能を持ち、そして、既存の自転車や、あるいはオートバイとは、まったく異なるもの、つまり、新種の《ビークル》……。
こういうものを、藤沢は、本田宗一郎に「つくらせよう」としていたのだ。
そして、ついに、その時が来る。1957年、欧州視察からおよそ1年後、本田宗一郎が藤沢武夫に電話するのだ。
「ちょっと、白子の研究所に来てくれ」
研究所で、宗一郎の「きみのいう『50cc』ってのは、こんなもんでいいのか?」という言葉とともに藤沢を待っていたのは、スーパーカブのプロトタイプ、そのクレイモデルだった。
それを一目見た藤沢は、「これは売れる!」と即断した。ヨーロッパにも、そしてもちろん日本にも、こんな格好の二輪車はなかった。自転車でもなかったし、また、既存のオートバイとも違っていた。

1958年、自転車にエンジンを着けたレベルを一気に進化させるスーパーカブC100が登場。爆発的な人気を博し、これが鈴鹿サーキットの原動力になった。
そして、そのモックアップとほとんど変わらないスタイルで、1958年に発売された『スーパーカブ』は、当事者の予想をも超えた大ヒット作になっていく。
「初期のスーパーカブは、埼玉製作所の大和工場でつくっていたんだけど、あまりに売れたので、すぐにカブのための新しい『工場』が必要になった」
「それで土地探しが始まり、日本全国を探し回ったあげくに、《鈴鹿》という場所に出会う。そして、生産工場である鈴鹿製作所が設立される」
「鈴鹿とホンダの接点というのは、まずは『工場」だったんです。ここに工場ができたことが、のちのサーキット建設につながっていくんですね」
こう語りながら、リキさんは、さらにつづけた。
「本田(宗一郎)さんが、なぜ《鈴鹿》を選んだのか。このへんにも、おもしろい話がいっぱいあってね!(笑)」
……あ、リキさん、ちょっと長くなったので、それはまた、次回にお願いします!
第二回・了 (取材・文:家村浩明)