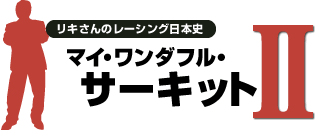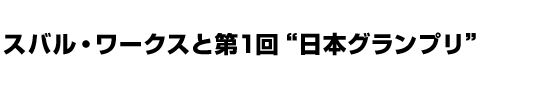(1)初めてのグランプリ・レースは、コース走行講習会から始まった!
――1963年のレースに参戦するスバル・ワークスでのリキさんについて、伺っていきます。クルマを試すためのテストロードなんかなかったという前回のお話しでしたが、でも、鈴鹿サーキットへ行けば走れましたよね?
「初めての顔合わせ以後、太田工場では何回か同じような、チョコッとだけ走ってみるような小規模のテストが繰り返されました」
「そして、鈴鹿サーキットにも行ったことは行ったんですが、これは車両のテストのためではなく、5月のこのレースにプレエントリーした者は、全員、鈴鹿の走り方の講習を受けなくてはならないという規定のためでした。これの第1回の講習会は、 たしか3月中旬。でも、笑っちゃいますよね。レースに出る人がサーキットの走り方を教わらなきゃダメっていうんですから(笑)」
――なるほど、そういうレギュレーションですね。一種の“鈴鹿ライセンス”みたいなものに思えますが、それを体験&取得してくれと?
「そういうことです。まあ、何度もお話ししてますけど、名神高速道路さえなかった時代ですから、自動車で高速走行をするという機会が、そもそも当時の日本人にはなかった。だから、こういう講習会が存在した理由は理解はできます」
――そういう状況だからこそ、エントリーしたメーカーは、レースや《鈴鹿》の経験者がほしかった?
「ええ、それが四輪レースは未経験の二輪ライダーであってもね。レースというかたちでの競い合いと、そのやり方を知って、さらにそれの体験もしていた者を探すなら、二輪レースの関係者が一番手っ取り早かった。これは客観的な事実だったでしょう」
――リキさんが所属したレーシング・チームというのは、どのような構成で?

出番を待つパドック。スバル・サンバーの“サービスカー”や参加車の向こうに、逆バンク周辺のコースが見えている。
「うーん、“チーム”ですか……。これは、なかなか微妙ですね(笑)。第2回のグランプリに向けてなら、スバルは正式にGPチームを結成して、その監督には、太平洋戦争では騎馬隊隊長だった佐藤重雄さん(技術部・実験課課長)が就任されました。でも、1963年の第1回のときは……」
――“チーム”というよりも?
「要するに“人の集まり”だったというか(笑)。人材はたしかにいましたが、この時点では“チーム”というには程遠い体制だったと言うしかないですね」
「当時、エンジンを製作していたのは三鷹製作所で、車体を製作するのは、群馬製作所の呑龍工場(太田工場)。この二部門から、技術者と整備要員が派遣されていて、レース参戦に向けて動いていたのはそうした人々でした。そして事務方といいますか総務面は、本社の宣伝部が担当でした」
「車両面だけを見れば、総合的には、『スバル360』というこの世界的名車の開発主任者である百瀬晋六さん、エンジン設計主任の小山仁さんも関わっておられたと記憶しています」
「そして、その市販車をどのようにサーキットに“合わせる”のか。実際の車両の改造では、エンジン開発担当の海野保さん(三鷹製作所)と、車体関係は太田工場の家弓正矢さんがメインであったことを覚えています」
――すぐれた技術者は多く参集していたが、それが“闘うチーム”として機能していたかどうかというと、やや“?”であった?
「まあね!(笑)ぼくの場合は、ひとりのライダーとして、またジャーナリストとして、たとえばヤマハの“渡瀬軍団”とか、そういうのを見てきていますからね。レーシング・チームというのがどういうものか、それを曲がりなりにも知っている立場からすれば、どんなもんかなーといった感じで……」
――ただ、レース参戦は、スバルにとってはこのときが“初体験”ですね?
「そうです、だから、無用な批判をここでする気はありません。それと、そもそもターゲットをどう定めるかのという根本的なところが揺れていた。これは、メーカー側のせいではなく、たとえば車両規定にしても、結局は、レースの当日まで明確にならない、また、明確にできないということの連続でしたから」
――それはたとえば、クルマのこの部分をこう直すと、それがレギュレーションでアリかナシか。それがよくわからないということですか?
「その通りです!(笑)困ったものですが、ただ“初体験”といえば主催者も同じでね。四輪の、それも市販車をベースとする車両によるレースなんて、やったことがなかったわけです。だから、規定も明確ではなくて、実際に改造された状態や改装したモノを見て、これはおかしいとか、これはダメとか、そんな朝令暮改を繰り返していました」
「そのような状態ですから、5月のレースが近づくにつれ、メーカー(チーム)の技術者とレース運営機関との会議が何度も行われ、その度に改造や改装の解釈が変わるほどでした。要するに、車両規定の“迷走”と併行してのクルマ作りでしたね」
(2)「四輪車って、鈴鹿では、こんなにも遅いものなのか!」
――そうしたチューンされた部品は、そのテストをする場もなく?
「そうですね、レースのために作ったものは、サーキットを走ってみて、そこで初めて(良し悪しが)わかるという状況。そこでいろんな事態に遭遇するというか、そういうことばかり。そして、実際に鈴鹿のコースを四輪で走ってみて、しみじみ実感したことがあって……」
――はい、何でしょう?
「自動車とは、こんなにも遅いものなのか!(笑)」
――おお!
「そして、自動車は、こんなにも“曲がれない”“止まれない”ものなのか! さらに、こんなにも壊れるのか!(笑)」
――ハハハ(笑)って、笑っちゃいけないかな。でも、それって高度なレベルになっていた二輪のレースを知る人だけが語れることだったかもしれません。きっと鈴鹿の最終コーナーなんかも、四輪で走りながら、リキさんはかなりイライラされてたんでしょうね?(笑)
「うーん、イライラというか、手持ちぶさたでね(笑)。直線では、床が凹むくらいアクセル踏んでいるんだけど、50ccの二輪(レーサー)の方が速い(笑)。そのくせ、ブレーキは効かない、ステアリングも反応しない。63年の初めてのレースは、そんなものでした。これが次回の第2回GPになると、一転して、阿修羅の如く変貌するんですけどね。でも、もちろん、そういう“道具”の範囲内でタイムを出さなきゃならないのですが」
――でも、その“道具”がけっこうアヤフヤ、手探り状態というか?
「そうです、いわば“未知の改造車”に、ぼくらは乗ってた」
「それから、実際に鈴鹿のコースをレース仕様のクルマで走り始めたのは、ようやくレースの一ヵ月くらい前からでした。そしてそれも、何日も走れたわけではありません。スバル・チームの場合で、日数にして7日間ほどかな。それも、1日に1~2時間程度の走行ではなかったでしょうか」

第1回日本グランプリ前、鈴鹿のテストで力走する“ワークス・スバル450”の二台。
――なるほど、ワークス・チームといえども、そんな状況だったのですね。
「ですから、ぼくのように、二輪で走っていた者には有利でしたけど」
――それにしても慌ただしいというか、そういうタイム・スケジュールで第1回の日本グランプリへと向かって行った?
「クルマ(レーシングカー)を“作る”ということで言うと、一応はメーカー・チームですから、ドライバーが気づいて要望したようなこと、そしてそれに必要な部品は、可能である限り、ほとんど工場で作ってしまうことができました。たとえば、アクセルやブレーキペダル、シートの取り付け位置の変更、あるいは、シフトレバーの形状変更など。少しでもドライブしやすくしようとする改造は多くやりました」
「そして、エンジンの馬力を高めたり、サスペンションを多少固めたりといった技術的な変更、これもしていたのでしょうが……。でもぼくには、それが“目に見える”ようなレベルのものであったようには感じられませんでした。でも、このチームは、チューニングなどしなくても負けるわけがない!という雰囲気だったからなあ(笑)」
――第1回グランプリでのスバル・ワークスは、360ccクラスでスズキと対決し、そして700ccクラスではトヨタ・パブリカと競うという、一種の二面作戦を採ることになります。戦争において最悪の戦略/作戦は“二面作戦”だという説もありますが(笑)、ドライバーという立場からは、この戦略をどのように考えておられましたか?
「ぼくは、すでに二輪の世界GPの50ccと125ccクラスで勝利していたスズキの2サイクル技術力の高さを知っていましたから、スバルのこんな程度のチューンでは完全に負けると思っていました」
――この時点での「スバル360」に搭載されていたのは、後年の4サイクルではなく、2サイクルのエンジンですね。
「だからこそ、口幅ったいですが、練習タイムでも一番速いぼくを360ccクラスに出すべきだと思っていました。でも監督は、“何も大久保や小関典幸(社員ドライバーのリーダー)を投入する必要なんかない”と──。つまり360ccクラスでは、スバルの3番手や4番手のドライバーで、楽にスズキには勝てると考えたのでしょう。そして『スバル450』で、700ccのクラスに出て、トヨタのパブリカと闘う!」
――あ、スバルに、そういうモデルありましたね。
「この『450』というのは、少量ながら輸出用として、また、普通車と軽自動車とは制限速度が違ったので、そこから国内の小型車クラスとして設定されていたモデルです。エンジンは423ccにスケールアップされてました」
「この『450』に“速い二人”を乗せる。そして、排気量がほぼ倍のパブリカに食らいつき、上位入賞すれば万々歳! ……というのが、このときのチームの空気というか、身の程知らずの(笑)目論見だったのです。もちろん監督の指示ですから、ぼくは不満ながらも、それには従いましたけどね」
第二十四回・了 (取材・文:家村浩明)