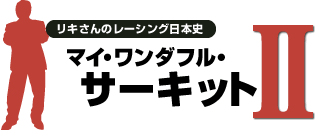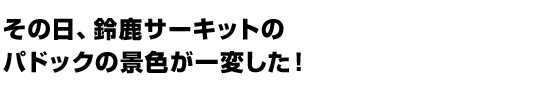(1)いったい、どんなクルマが走るレースなんだ?
――二回ほど、1963年、第一回の日本グランプリに参戦するドライバーという立場からのお話しををいただいていますが、今回は少しそこから離れて、より大局的なといいますか、ジャーナリストとして、当時どうご覧になっていたかをお伺いしたいのですが?
「それは、なかなかむずかしいなあ。ぼくは、そのレースではエントラントだったからね。それと、名前だけは“ワークス契約ドライバー”だったけど、出版社のライター&ライダー、さらにはMFJ事務局では夜間のアルバイトもやっていたから、けっこう忙しかったのよ!(笑) (その頃)いったい、何が自分のメインだったのか……。ぼくもバタバタ、そしてGPもバタバタ(笑)。そんな状態でしたからね」
――たとえば、開幕一ヵ月前くらいのときで、グランプリ・レースに向けての“盛り上がり”というようなことはあったのでしょうか?
「前回に、レース参加希望者は“サーキットの走り方”を教わる講習を受けなければダメという話をしましたね。これで、出場者の顔ぶれが大方揃ったということになります。レースを構成する要素のうちの“ドライバー”という部分については、これでほぼ明らかになったわけですが──」
――はい?
「……という風にわざわざ分けてみたのは、このとき、世間様が(笑)興味を示したのは主に“クルマ”であって、ドライバーではなかったから」
――あ、その“グランプリ”っていうレースは、“誰が”じゃなくて、“何が”走るんだという論議になってしまった?
「そういうことです。5月のレースには、どんなクルマが出るのか。ほとんど、こっちの関心一本だった。運転手がいなければ、クルマは走らないのにね!(笑) それと、もうひとつの“状況”としてあったのは、二輪(レース)の関係者がシラーッとしていたことです。なぜかクール、冷たかった」
――せっかく日本初の、四輪車の大きなレースが開催されようとしているのに?
「そう。おそらく、どうせ大したもんじゃねーよ、くらいに思ってたんでしょうけど(笑)。でも、そんな状況が変化の兆しを見せたのは4月に入ってからです。4月の5日頃にエントリーが締め切られて、正式な発表会もありました。そして、グランプリ・レースは10のクラス分けがあり、それに対して約120台のクルマが参加している。この事実が明らかになったときに、あ、レースをやるってのはホントのことなんだ、そして、そのレースはかなりの規模なんだということで、ムードが変わってきたように思います」
――メディアの様子にも変化があった?
「そうですね。自動車レースに関するスポーツ新聞や週刊誌の報道も多くなって、一般ユーザーもグランプリ・レースがあること、そして、それがどんなものであるかを知るようになってきました」
「それと、4月に入りますと、プライべート参加者──二輪用語だと“クラブマン”になるかな、そうした人たちの“鈴鹿通い”も激しくなりました。だから、サーキットのスポーツ走行の時間も足りないくらいでしたね」
「この半年前に行なわれた二輪レースでも同じでしたが、メーカーなどのコース占有がないときは、一般ライダー/ドライバーがコースを走れるスポーツ走行という営業があります。これは、いまも同じですね。四輪レースのための講習を受講した者は、30分で1200円、超過10分ごとに400円というのが当時の走行フィーでした。今日に換算すれば、1時間が1万8000円くらいでしょうか」
――リキさんは“ワークス・ドライバー”だったから、メーカーが占有しているときに走れた?
「走れました。その意味では、恵まれていました。ただ“ワークス”といったって、走り方を教えてくれる人がいるわけでなく、また、それを教わる手段もなく、闇雲な自己流で走り方を探っていくというのが実状でした。“ワークス”を名乗ってそんな状態でしたから、プライベートなら尚更ですね。……というか、《走り》を必死に“探っている”ということでは、ワークスもプライベートも何も変わらなかった。だから、走行していての事故も多かったです」
「あと、そのコースの占有料というのが、ものすごい値段でね! これは、いまでもちょっと信じがたいんだけど、《鈴鹿》のコース、1時間の占有借り切り料というのは、二輪が10万、四輪では25万円でした。これは、メーカーだからこそ払えたというプライスだったでしょうが、それにしても……。だって、さっきのスポーツ走行のときの換算方式をここで適用すると、いまのおカネで1時間350万円超ですよ!」
(2)自動車メーカー、そして輸入車ディーラーが“関与”と“支援”をし始めた!?
――先ほどの“事故”というのは、コースアウトしてしまったりとか?
「なかなか、そこまでは(鈴鹿を)攻めきれない!(笑)……と言うか、それ以前の状態での事故ですよ。やれ、車輪が外れた、ブレーキが故障で効かなくなった、タイヤがパンクした、エンジンがブローしたとか、そういうレベル。ただ、そうは言っても、もちろんクルマの転倒にまで至った事故も、10台は超えてたはず。そして、そういう状況を見て、ついに、自動車メーカーがヒソカに動き始めました」
――え……?
「今日でもそうでしょうけど、当時はとくに、ユーザーの“口伝え”、つまりクチコミですね、それがクルマ(市販車)の評判に大きな影響がありました。だから、あのクルマは《鈴鹿》を走ったらこうなってしまったとか、さらには、極端な話ですけど、どこそこのコーナーではコケちゃったとか(笑)、こういうのはマズいわけですよ。そこで、トラブルに対処するというか、そういうトラブルが出ないようにしようと──」
――ははあ、何らかのサポートが?
「4月の10日頃から、一週間に渡ってのオフィシャル・トレーニングが始まりました。レースの本番まで、もう一ヵ月を切ってます。この“オフィシャル・トレーニング”というのは、グランプリ・レースに正式にエントリーしたドライバーとクルマのテスト走行がクラス毎にできるというもの。エントラントにとっては、ここで初めて、相手がどのような顔ぶれなのか、そのクルマとドライバーがわかったわけです。ただ、このとき、“スズキ”の姿は見えなかったですねえ」
――その“スバル vs スズキ”のお話は、また後日のお楽しみということに(笑)。
「ハハ、そうですか(笑)。……でね、この“トレーニング”が始まったときに、《鈴鹿》のパドックの景色が一変したのです」
――おお?
「国産の各メーカー、そして輸入車ディーラー、これらのサービスカーでパドックが埋まった。そして、そのサービスカーと、エントラントやドライバーとの間をメカニックたちが走り回る……」
――ワークスとはいわないまでも、セミ・ワークス的なサポート状態?
「そうです。各社による、有形無形のサービスのデリバリーが始まった。要するに“後方支援”ですね、その競争です。……で、こうなると、もう、どのメーカーもあとには引けません。でも、いまになって考えれば、これもすべて、既定の路線だったのかなあ……(笑)」
「そして、この種のサポートやサービスは、実は、自動車メーカーだけではありませんでした。タイヤ、プラグ、オイル、エンジン潤滑剤、オイル添加剤、シートベルト、ワックスなどなど、いろいろなサプライヤーが《鈴鹿》のパドックに登場しましたが、中でも一番多忙だったのはタイヤでした」
――それは?
「いまと違って、当時は、ラジアル・タイヤではなく、そして、チューブレス・タイヤもまだ一般的ではありませんでした。だから、サーキットを走ると、タイヤが“パンク”しちゃうんです(笑)。それは、釘を拾ってタイヤに穴が開いたとかそういうことではなく、タイヤと、その中にあるチューブが高速走行時に擦れ合って、その摩擦熱でチューブが傷んで空気が抜ける。あるいは、高速走行でチューブがズレてしまい、エアを失って同じく“パンク状態”になる」
――ははあ!
「いまでは、笑い話ですけどね(笑)。それから、日本初のシートベルト。……といっても、今日の市販車のような三点式ではなく、ましてやフルハーネスなんかではなくて(笑)、左右から腰回りを縛るだけの“一本ベルト”ですが、「高田ベルト」が熱心に装着をPRする光景が深く記憶に残ってます。それでも、ベルトの効用を試したドライバーは、どのくらいいたでしょうか? 」

現在ザウバーF1チームが採用しているシートベルトのTAKATAの原点ともいうべき『高田ベルト』。当時は、腰回りを縛るだけの“一本ベルト”だった。
――高田ベルト、現在の社名は「タカタ」ですね。シートベルトについては、リキさんは?
「ぼくは、そのベルトは装着しました。それは、シートから身体が外れない、腰を固定できてズレないというのが調子よかったからです。あと、ヘルメットへのサービスはまだ出ていませんでした」
「でもね、(自動車)メーカー各社は、このレース(グランプリ)には後援も協力もしないと申し合わせていたんです。でも、背に腹は替えられなかったんでしょうね。……というか、そんな“オキテ破り”もしたくなるほど、クルマがトラブったんだな」
――当時の日本メーカーによる市販四輪車が、のちに、タフでテクニカルであることにおいては世界一とまで言われるようになる《鈴鹿》の厳しさにビックリして?(笑)
「そういうことですよね。当時の国産車は、その市販車のほとんどは、こんな高速サーキットで、しかもタイムを競って走るような“予定”もなく、作られていたから(笑)。でも、レース前の段階では、人命に関わる事故がなかったのは幸いでした」
第二十五回・了 (取材・文:家村浩明)