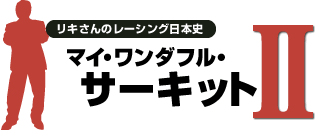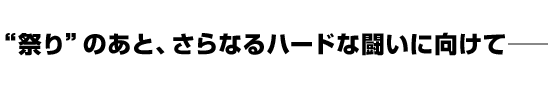(1)「この日を忘れない、必ず、スズキを打倒する!」
――さて、日本初の大規模な、かつ本格的な四輪車のレースが行なわれた1963年ですが、この第一回GPから翌年の第二回GPに至るまでの“一年間”というのは、日本のクルマ史、またレース史の中でも、極めつけと言ってもいいくらいに?
「フフ、そうですよ(笑)。すごく、おもしろい時期。だから、大いに語りたいですね、何でも聞いてください!」
――とくにリキさんの場合は、いち早く“ワークス・ドライバー”という立場になられたという状況で。でも、第一回GPでは?
「ええ、惨敗と言うべきでした。エントリーの仕方など、総合的な戦略も含めて、スバル・ワークスは、すべてに敗れました」
――レースを終えて、リキさんとしては、まずはどんな思いを?
「誰かに会うたびに、“なぜ、400クラスに出なかったんだ?”って聞かれてね。そう言われても、ぼくの意向だったわけじゃないんだけど(笑)。700cc以下のレース、対トヨタ・パブリカ戦に、ぼくと小関選手が回って、そのせいだったかどうかは、もちろんわかりませんが、400cc以下のレースではスズキに完敗した」
「これは、ぼくを四輪レースの世界に引き込むカタチになったお二人、酒井さんと西山さんからも指摘されました。お二人が“リキちゃんが出てればねえ!”と言ってくださったのは、面はゆさもあったけど、嬉しかった」
――とはいえ、当事者としては悔しさの方が?
「いや、悔しさというよりも、スズキの実力を侮っていた、また、レースの何たるかをわかっていない富士重の技術者に、半ば諦めの気持を持ってましたからね。だから、ぼくとしては、予想通りのことがそのまま起こったというだけ……。でも、そんな読みが当たってもしょうがないわけで(笑)複雑な心境でした」
――でも、ドライバーとしては高い評価を受けた?
「まあね。西山さんをはじめとするクルマやレースに詳しい方々からは、スバル450でパブリカに食らいついていたこと、そして、多くの三菱500にハッキリ後塵を浴びせたことは、評価していただきました」
「ぼくとしても、この(対700ccパブリカ)レースに出たおかげで、互角のマシンでレースするなら、絶対に負けないぞ!という自信も生まれました。内心では、“クラス優勝”したのは俺だという自負もありましたし」
――そうなると、これでは終われない!……ですよね?
「そうです(笑)。でもそれは、ぼくだけじゃなくて、富士重工というかスバル・チームも、その気持ちは強かった。何といっても、完敗したその夜の夕食会で、『この日を忘れない、必ず(スズキを)打倒する!』という決意表明がなされたくらいですから」
――え、その晩に? まずは初のレース挑戦への労をねぎらって……とか、そういう雰囲気ではなく?
「いやいや、いきなり、リベンジ宣言!(笑)ぼくも同じだったけど、それ以上に、メーカーも悔しかったのでしょう。とくに、実際にレースを闘った“チーム”の人たちはね」
「ただ、その夜は、“鬼畜米英! 欲しがりません勝つまでは”というか(笑)、要するに、敵に対する“戦時意識”みたいなものが濃厚にあって……」
――さすが、旧・中島飛行機だと?(笑)
「ええ。ここ(富士重)はやっぱり、戦時には、そういう時間を過ごしてきた会社なんだなあという感を深くしました」
――その晩、とくに“燃えて”おられた方というと?
「それはやはり小関(典幸:故人=スバルのモータースポーツの“オヤブン”として、スバルエンジン搭載のフォーミュラカー・レース参戦や、赤城小沼での氷上イベントの仕掛け人として知られる)で、彼は剣術の居合抜きの達人なんですよ。国定忠治の義理人情、根っからの上州気質で、だから仇討ち的な思想が強かったのでしょう。やたらと“江戸のカタキは長崎で”なんて言うものですから、言ってやったんです。“江戸のカタキは江戸で取るもんだ! 鈴鹿のカタキは鈴鹿で返すんだよってね(笑)」
――おおー!(笑)その会合はサーキットのそばで?
「チームは、このときは、四日市の町外れにある料理旅館に宿泊していました。だから、スタイルとしては、床は畳で、そこにコの字型にお膳を並べて……という、日本古来の宴会ですね」
「ただね、誤解のないように付け加えると、夕食会の雰囲気は、決して殺伐としたものではなかった。また、“ああすればよかった、こうすればよかった”といった繰り言や後悔でもなく、どうすれば、もっと速いクルマに改造できるか、こういう改造はできないだろうかなどの方法論が多かった記憶があります。ただ、400ccクラスのドライバー、つまり社員ドライバーたちはうなだれっぱなしでしたが」
――その段階で、スバルは来年もGPに出場するという流れになっていたわけですよね?
「そうです。そして実際にもスバルは、これに関しては、とても俊敏な動きをしました。何といっても、5月3日にレースが終了して、その後、直ちにレーシング・チームの再編が行なわれましたからね。そして7月1日には、当時、就任したばかりの横田信夫社長のもと、その直属という組織形態での異例ともいうべきプロジェクトが発足しました。そのテーマはただひとつ、『打倒スズキ』です」
「こういう動きになったもうひとつの理由は、レースの結果に対して、多くのスバル・ユーザーから『いったい、どういうことになっているんだ!』という落胆と抗議の電話が殺到したこと。これも影響していたでしょう」
――それは、何で“俺のスバル”が負けるんだと?
「ええ。庶民の憧れを実現してくれた、クルマをそんな身近な存在にしてくれた日本で最初のモデルが『スバル』だった。だから、それだけ期待も注目度も高かった。それと、なぜスバルが、名も知れぬスズライトごときに──いや、実際、そんな存在だったんですけどね、スズキは。それに、なぜ負けたのか。こういう疑問もあったようです。ここで初めて、メーカーは、400cc以下というのがそういう重要なクラスであったことに気づいたんですね」
――ははあ~! そうすると、リキさんご自身の“身分”も?
「ぼくがチームに残る、つまり、これ以後も継続してドライバー契約をする、それは当然だというのは、そもそも富士重の意向でした。だから、ぼくとしても、何のためらいもなく再契約に応じました」
――そして、すぐに「翌年」のための活動が始まった?
「そこからあとの一年は、もう盆も暮れもなく、ただひたすら、市販車を強力なマシンに変貌させることに集中しました。クルマがまだまだサーキットに持ち込める状態ではないという時期は、榛名山の有料道路を早朝に借り切り、そこをテストコースとして走りました」
――「第一回」に参戦したメーカーの場合は、社によっての多少の温度差はあれど、そういう“燃えた”状態で、第二回に向けて“突っ込んで”行ったのでしょうか?
「まあ富士重のみならず、レースに対しての四輪メーカーのお粗末さというのは、どこでも話題になりましたから。したがって、レースに関わったメーカーであれば、それに気づいたでしょうし、もっと真剣に取組まねばならないと思ったはずです」
「それと、トヨタの抜け目のなさです(笑)。これにみんな(他メーカーは)驚いたというか、もっと言えば、カッカしてましたから。とにかく、TVでも週刊誌でも、日本中が『トヨタ優勝!』の広告だらけ。そりゃあ、来年はトヨタだけに“いい思い”はさせねえぜ!……となりますよね」
――なるほど……。
「当時の日本の自動車メーカーで、こういった競技の結果の影響の大きさを知っていたのは、トヨタとニッサンだけだったでしょう。1957年にトヨタはオーストラリア・ラリーに参加していますし、翌年にはニッサンも出ています。ですから、精神的にはGPには出なければ損だというのは、わかっていたでしょう。ただ、ニッサンはサファリ・ラリーへの参加の準備が“進みすぎていた”ので、フェアレディで対応したということです」

初の日本GPで大成功を納めたトヨタは、後に自粛するほど積極的なPR活動を行なった。写真は、雑誌に掲載された数ページにわたるトヨタの広告の一部。
(2)レーシング・ライダーはレーシング・ドライバーになれるか?
――《大久保力》は来年もスバルで走る! これが決まった頃、リキさんの周辺に何か動きはありましたか? 同じような立場であったドライバーの方々などで?
「ウン、これはすでにいろいろなところで喋っていますが、“あの田中健二郎さん”から、いろいろ聞かれましたね。ぼくが二輪から四輪の世界に移ったように思われていましたから、四輪って、いったいどんなところなんだという興味があったのでしょう」
――何で、四輪に転向したんだと?
「ええ、それも含めて。また、タナケンさんには、お前は二輪では勝った試しはないし、四輪へ逃げたんだろうって思われてましたから(笑)。……で、四輪メーカーというのはどういう内情なんだ、そして、契約はどうなっているんだ、とね。内心ではぼくをバカにしていることがわかってたから(笑)、ぼくも多少意固地になって、オーバーな表現も交えて、クルマ(マシン)作りのこと、おカネのこと、そして、メシ、寝場所まで話してやりました」
「そうしたら、二輪との大きな違いに驚いていましたから、この話はすぐに関係者の間に広まったはずです。この話だけが直接の原因ではないとは思いますが、このとき、つまり1963年当時の四輪メーカーが、やはり二輪のライダーは“使える”と見たのは間違いありません」
――レースするなら、二輪のライダーがいいぞ、と?
「そうです。それで、いろいろなメーカーが二輪の(レーシング)ライダーに接触し始めた」
――なるほど、リキさんがその動きの契機となったわけですね。ただ、客観的に見ても、当時に、“ちゃんとした競走”をしたことがあるという人たちは、事実上、四輪界にはいなかったはずで?
「二輪は《マン島》にしても《アサマ》にしても、そういう歴史とキャリアを経て、そして、1962年の鈴鹿サーキット完成を迎えていた。また、二輪メーカーでは、すでに世界チャンピオンになっていたメーカーが、それも複数あった。これに較べたら、四輪メーカーは、レースではヒヨッコでしかありません」
「ただね、実際にサーキットで四輪車に乗せて見ると、“大したことはないな”という二輪ライダーも多かったようです」
――それはたとえば、べつに速くなかった、あるいは、四輪という“マス”を動かすことがそんなに上手じゃなかったとか?
「ひとつはね、要するに、サーキットを走るとなれば、スピードが話題になります。そうなると四輪は、二輪ほどのスピードが出る乗り物ではありません。そこから、ライダーにとっては“おもしろくない”という表現にもなります」
――スバルで鈴鹿サーキットを走って、二輪の50ccより遅いと(笑)おっしゃってましたよね。この“50cc”は、もちろんレーサーでしょうけど。
「二輪の場合は、市販車がベースだといっても、サーキットで競走しようというときには、完全なレース仕様になっています。それに較べると、そういうのに慣れたライダーが四輪に乗ってみても、その四輪は、そのへんを走っているのとあまり変わらない。そういう(レベルの)クルマでサーキットを走るから“曲がらない/止まらない”で、果ては、コケる、ぶつかる……となります」
――ははあ!
「だから、そんなクルマであっても、そこから、そのクルマのポテンシャルを存分に引き出すという感性がないと、仮に二輪の名ライダーであっても、四輪には向いてないということになります」
――フム、少なくともこの時期の四輪レースは、そういうクルマ(市販車・改)でレースしていたわけで?
「それと、動力源そのものを身体で抱いて、そして身体全体で操る二輪と、人間が動力源を遠隔操作するような四輪とでは、むしろ相通じるものは少ないとも思います。ムリヤリに共通点を探せば、スピード、それも高速に対する感覚と、その分析力と扱い方ぐらいでしょう」
「四輪は、身体の周りをいろんなもので囲まれています。二輪のように、風、路面、雨、そして高速への不安をじかに感じることはありませんが、しかし四輪は、とにかく“曲がらない・止まらない”(笑)。ですから、ひとつ間違えば、ガードレールや土手に簡単に激突する」
「そのようなときに、二輪なら、身体の移動で何とかしよう、あるいは、あるタイミングでマシンを手放して安全に転んでしまおうとか、瞬間的にいろいろ考えることができて、実際にも何らかの対応ができます。しかし四輪では、シートベルトに縛り付けられた身体を動かすこともできず、クルマの挙動任せ……」
――ライダーが“できること”に較べると?
「ええ、ドライバーは何もできない。ただ、逆にいうと、だから、どうするかということです」
「四輪はひっくり返らないという印象がありますが、とんでもない。当時のクルマは簡単に転びました。四輪という、イメージでは安定しきった感のある乗り物が、実は相当に不安定なものであるとわかったとき、“どうすれば巧く曲がれるだろう? どうすれば、もっと速く走れるだろう”“長年、二輪レースをやってきた俺をナメんじゃねー!”という心境になって(笑)、そこから、こうなったら、俺が一番巧く(速く)四輪車を扱えるようになってみせる! こういう気持ちを強く持ったことを思い出しますね」
――この“不自由なもの”を操ってやるぞ、と?
「そうです。その“もっと巧く、扱ってみせる”という、ほとんど猛獣使いに似た心境は、その後のレース活動でも変わることはありませんでした」
「四輪のテストを受けて不採用になった二輪ライダーが異口同音に発していたのは、“四輪はツマラナイ”でした。これ、なかなか都合のいい表現でね(笑)。要するに、思うがままに四輪を扱えないという結果で、その原因は、四輪へのイメージが甘かったことなんですが」
「それと、二輪の経験や応用ですね、これらを四輪にどう活かすか。総じて、四輪をどう扱うか。それがわからなかった。でも、そういう“わからない・できない”ことを認めたくない。その気持ちを“ツマラナイ”という表現に転嫁していたのでしょう」
「ですから、いくら二輪で速くても、四輪ドライバーになれるかどうかは、まったく別問題なのです。とはいえ、その逆、つまり“四輪→二輪”は、もっとむずかしいですけどね(笑)」
第三十回・了 (取材・文:家村浩明)