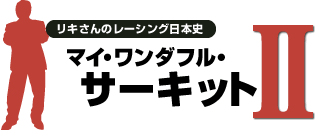(1)1963年初夏、その闘いは始まった!
――今回から、1963年の第一回日本グランプリに敗北して後の、スバル・ワークスとリキさんの動向ということで、お話を伺っていきます。まず、スバルはチームの組織を変更し、スズキへのリベンジを期す! そして、ドライバーは「大久保力」で行く。ここまでは、すでにお話しいただいてますよね?
「『大久保力で行く』という表現が、正しいかどうかはわかりませんが(笑)。ただ、63年のように、700クラスと400クラスの二本立てはムリだと。それは、あまりにも甘すぎたという反省はすぐに行なわれ、そこから、次回は400クラスに絞るしかない。こういう決定はなされましたので」
――必然的にドライバーは?
「ええ。社員ドライバーのエースである小関典幸と、社外の契約ドライバーであるぼくに多くの期待がかかった。それは事実でしょうね。そして、ぼく以上に期待できるドライバーを探そうと思えばできたのでしょうが、このときは、そういった余力がなく──これは資金的な意味ではありませんが、それより、もっと優先すべき問題があった」
――それは?
「いかに、もっと速いマシンを作るか。クルマ(市販車)をどう改造するか。こういう展望というか願望、また“焦り”の方が先行していました」
――ははあ、ともかくクルマが負けてたじゃないかと。ということは、スバル側は1963年の敗北については?
「ええ、敗因は全員が明確にわかっていました。参戦のための準備などが、あまりに短時間であったこと。そして、市販車性能から見ての甘すぎた予測です。レースが市販車そのもので行われるのではないことは、一般ユーザーもメーカーも知ってはいたのですが、やはりベース車の市販車性能での比較を第一に考えてしまっていた。だから、実際に負けて、ようやく、それがまったく当て嵌まらない世界があることに気づいたのですね」
――市販車同士で比較した場合に、仮に優位であっても、それはサーキットでは意味を持たない?

国際法典に基づいた規則書は、1963年には存在せず、1964年の第二回GPの2カ月前にやっと完成にこぎ着けた。
「そうです、チューニングはアリですから。市販車を改造することは一切できないというレースとは違いますし、改造範囲も規定にあるわけで。また敗北は、車体より、非力なエンジンに原因があったという声は、社内では少なくなかった。レースで負けたのは“三鷹”のせいだと公言してはばからぬ者もいましたね。富士重工のエンジン製造の工場は三鷹工場でしたから。今日の名称は、三鷹製作所になってるのかな」
――おお!
「もちろん、レースの基本がわかってきてからは、エンジンがどうの、車体がどうのという単純な問題ではないことに気づいていくのですが。そこから、それじゃあ何をどうすればいいんだという、その後のプロセスにつながっていく。とにもかくにも、群馬の呑龍工場は車体関連全般、そして三鷹工場はエンジン、それぞれに最高の開発をするしかない。ここから、再出発しました」
「エンジンと車体は一体なものですが、ただ、最初から両者のマッチングを考えていたらアブハチ取らずになる恐れがある。当時の技術開発はそんなものでした。ゆえに、それを自覚した上で、群馬と三鷹、お互いの独自開発を優先する。そして、その次の段階として、両者が持ち寄ったものを組み合わせて調整していく。そういう方策を採った」
――新チームでの、初めての全体会議のようなものは?
「1963年5月3日の“敗北の夜”に、次回はどうしようかという対策は、すでに出始めていた。そして、それから1ヵ月半ぐらい経った頃でしょうかね。群馬の呑龍工場への集合がかかり、そのときに、グランプリ・チームの面々がぼくにも紹介されて、その陣容が明らかになりました」
――6月の半ばくらいですね?
「ここで、監督、設計、生産と製造、整備、そしてドライバーなど、それぞれの明確な役割が発表されました。前回というか、この二ヵ月前の初回グランプリでは、こういった役割はハッキリしていなかった。ぼく自身のマシンでさえ、どこでどう作られ、誰がその専門メカニックなのか、ぼくが知らなかったくらいですから(笑)。というわけで、ここでやっと、チーム体制と“やる気”を実感した記憶があります」
「もちろん、それとともに、ぼく自身に課せられた重みというか、そういう責任と役目も新たなものになりました。それで、新チームのテーマは、口に出さずとも“打倒スズキ”であったでしょう。しかし、この時点で、単にスズキに、またマツダに勝つといった単純なものでなく、もうちょっと別の意味が、このチームには付加されていたような気がしています」
――とおっしゃいますと?
「ウーン、もっと抽象的なというか、壮大なスケールでというか。単なるレースでの勝利ではなく、スバルの名誉を取り戻すんだと」
――いったん地に落ちた「中島飛行機」の威信や尊厳を?
「そう! それを回復するための特殊部隊。失われた名誉を取り戻す、その尖兵がわれわれなのだ……。そうした位置づけが、どうも、このチームにはあったような気がしてなりません」
(2)“戦時”だったので、盆暮れ・夏休みは関係なかった!
――そのチーム内での、リキさんご自身のジョブは?
「ぼくに課せられたもっとも大きな仕事は、与えられたマシンの、その最大のポテンシャルを引き出すことでした。そうやって、その仕様の実状を明らかにする。そこから、改良点の発見や、現状技術の分析・熟成も可能になります」
「そういうテストは、これはお話し済みですが、まずは、手近な榛名山有料道路注を借り切って行ないました。ただ、榛名山で答を出したものを、実際にレースの本番ステージである鈴鹿サーキットに持ち込んでみると、榛名山での判断が間違っていた。そういう場合もしばしばありましたね」
――それはたとえば、どういったことでしたか? もちろん、榛名山と《鈴鹿》では、速度がかなり違っていそうですが?
「要するに、榛名山のつづら折りの道を全開速度で登ったり下ったりして、急ブレーキ時のフラつきもなくなった、ブレーキのフェードも起きなくなった。また、どんなハンドリングでも転倒しなくなった、車輪がぶっ飛んでしまうようなこともなくなった……とします。そういう結果が出て、これだったらサーキットに持ち込んでも、かなりの走りができるだろう。そう思っていたものが、実際のサーキット走行になると、期待していたほどではなかったということ」
「原因は、もう、単純です。早朝に借り切った有料道路を自由自在にぶっ飛んでみたって、たかが最高速度は(時速)100キロぐらい。そこから20~30キロへの急減速や急加速をしたというのが、榛名山でのテストの実態です。サーキットとは“絶対速度”が異なっていた。いわばモノサシの違い、そこからの判断の間違いということですね」
――5月にレースが終わってからの最初の数ヵ月。一応、お盆休みあたりまでというのをひとつの区切りとすると、その頃は?
「いや、ハッキリ言って、そういう区切りはありませんでした。何しろ、富士重にとっては“戦時”だったから(笑)。ぼくは、新しいマシンができるたびに、群馬に呼び出されるのですが、それにはお盆も夏休みもなかった。そして、行けば、呑流工場内の車内コース、そして榛名山を走り回りました」
「そうやって、新マシンや、改良を施したクルマをドライブするたびに気づいたのは、クルマというのは、こんなにも変わるものかということ。進化や進歩といえるのかどうかはわかりませんが、少なくとも、前回にテストで洗い出した点については、格段に改良されたものが、ぼくの前に出てくる。指摘したこと、検討したことは、研究されて、確実に別のもの、新仕様になっていた。この動きは、すばやかったですねえ!」
――おお、メーカーの本気度が見えてきますね。
「技術陣が日夜を分かたず行なってきた改造、また、それを確認するための、榛名山道路の異常な走り(笑)は、そもそもは、どんな悪路でも乗り心地良く、静かで、大人4人が乗れて……ということで企画されたファミリーセダン(スバル360)を、凶暴なまでのスピードマシンに変えた。これには正直、たまげました」
「それでも、メーカーの上層部は、まだサーキットに持ち込めるに至っていないと判断したのか、なかなか、鈴鹿サーキットでのテスト話はありません。もっとも鈴鹿では、コース借り切りの依頼が殺到していて、思うようなスケジュールでコースが取れないという事情があったことは、後に知りましたが。ぼく自身は、新しい仕様で、早く《鈴鹿》を走ってみたい。何度か、そういう、はやる心を持ったことを憶えています」
――なるほど!
「それと、もうひとつ、ぼくにとって忙しかったというか、時間を取られたことがあったんですよ。というのは、前年の1962年(6月)に、マン島のTTレースで大事故を起こして“死に損なった”高橋国光が、日本の病院での治療がようやく一段落して、温泉治療とか山歩きとか、そういうリハビリを始めたのが、この頃だったのです。そのため、“クニ”が体力回復の目的でどっかに行くぞという、そのたびに、ぼくが運転役で駆り出された」
――それはそれは! ちなみにクニさんが、あるいはお二人が、最もお気に入りだった温泉というと?
「たぶん、病院からの紹介だったのでしょうが、湯河原や箱根湯本にはよく行きました。また温泉だけでなく、東京・奥多摩の高尾山を登ったり。でも、いま思えば、あんな“リハビリもどき”が体力の回復に役だったんでしょうかねえ。“クニ”にとっては、そうした体力的なことより、生まれて初めて、じっくり自分を見直したり、さらには、これからのレース界に復帰できるのかどうかといった不安を癒したり……。あれは、そうした時間稼ぎでもあったように思えてなりません」
「そうしたことに加えて、モーター・サイクリスト誌のテストレポートや、一方では、MFJのアルバイト事務という仕事も、相変わらずありました。そんな中で、富士重の仕事を優先しなければならず、時間の管理は、けっこう厄介でした。ぼくにとっての1963年の後半というのは、そういう意味でも多忙な時期でしたね」
第三十一回・了 (取材・文:家村浩明)