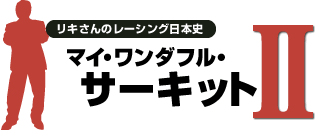(1)レースは“走る実験室”だった!
――第二回GPのお話を伺っていて印象的なのは、リキさんの二輪レースにおけるキャリアが活かされ、そして、そこで獲得されていたノウハウが投入されていたことです。
「……というか、この時点では“ワークス・チーム”とはいえ、メーカーがレースの実戦経験が少なかったのは事実でしょう。2サイクル・エンジンでのキル・スイッチの装着にしても」
――キル・スイッチ? バイクで、緊急時にエンジンを止めるためのものですよね。
「そう、電気系をカットする装置。でも、非常時にエンジンを止めるんじゃなくて、走行中に適宜、このスイッチをオンにする。それによって、燃料を燃やさず、エンジンに生ガスを吸わせる。こうやって、エンジンのシリンダーを内側から冷やす」
――おお~! それは二輪のレースでは?
「ウン、常識! 裏ワザでも何でもない、みんな知ってる(笑)。ただ、こういう提案をしても、誇り高き“旧・中島飛行機”富士重工の技術陣は、その効果を疑問視していた。だから、メカニックの芳賀くんと相談して、ぼくのクルマにだけはキル・スイッチを装備してもらった」
「このキル・スイッチとか、前回に触れたダイナモの“切れる予定のベルト”とか、こういう仕様って、トレーニング中に、チームにぼくがいくら提案しても、まったく採用されないんだよね(笑)。繰り返しになるけど、ぼくは、自分の知っていることをやらずにレースを終えてしまうのはイヤだったから、メカニックの協力も得て、やるべきと思うことは全部やったのです」
――それだけ、2サイクルエンジンの冷却というのはシビアなのでしょうね。そうか! そこであの“機密”も?
「八重洲出版から1991年・夏に出された“日本GP優勝マシンのメカニズムを探る”/『オールド・タイマー』の創刊号で、メーカーに所属する小関氏が全部語ってるから、外様のぼくも喋っちゃうけど、スバル・エンジンは、基本はファンも回す強制空冷方式です。……で、それだけでは、レース時における冷却性能が足らないので、時々、水を吹いた(笑)」
――小関さんが、この記事の中で、予選の二日目に、スバルの後ろを走っているとフロントガラスに水滴が付くと、スズライトのドライバーから言われたときは「ちょっとばかり、焦ったね……」と語っておられます。そうやって飛び散るくらいには、水を使っていたということですね?
「エンジン冷却の裏ワザです。シリンダーの温度が400℃以上になったときには、エンジンルーム内に水を噴射する。そうすると、温度が低下するという仕組み」
――ということは、エンジンを水冷式に?
「いや、空冷の基本構造は変わってはいない……というか、これは変更できませんからね。だから、熱した空気を冷たい空気に変えてやる…という意味になるのかな(笑)」
――ちょっと微妙な感じも?(笑)
「レギュレーション上? それは問題ありませんよ、エンジンを水冷式のように覆っているわけじゃありませんし。小関君は『規則違反ではないはず』と語っていますが、この時のレースでは、どのメーカーでも基本構造を変えない範囲内で、可能な限りの限界性能に挑戦していました。だから、いろいろな裏ワザ(笑)というのかな、そういうのはありましたよね」
「足回りにしたって、市販仕様のままではレーシングスピードで走れないわけですから、構造を変えずに工夫しなければなりません。だから、歴史を見ていくなら、レギュレーションに対してどうだったのか云々よりも、当時のそうした工夫の度合いや、アイデアの中身などを評価すべきでしょうね」
――ははあ!
「エンジンの潤滑にしても、オイルは、混合と分離給油、その両方のシステムをレースでは使いました。チームは、混合比8:1くらいのガソリンを使ったけど、ぼくとしては混合比は10:1でもいいのではないかと思ってた」
――その方がエンジンのパワーが出る? 市販車は二輪にしても、2サイクルのエンジンは、その多くが「混合給油」だった時代ですよね。
「ウン、この場合は、分離給油との複合なので。それで(オイルは)補えるから、混合の比率は薄くてもイケる、と。少なくとも、レース距離を走る限りは。ただ、クルマなら、ぼく独自の仕様を作ることもできたけど、燃料については、ぼくだけの設定をするというのは不可能でした。というのは、ガソリンはチーム全車で共通の燃料でしたから」
「レースで使ったこの『分離給油』方式は、1964年7月に登場した新型(マイナーチェンジ)のスバルで、すぐに採用されています。その意味では、この時期、日本のクルマにとって、たしかに、レースは格好の“実験室”だったのです」
(2)「このレース、スバルが勝つようにしてくれ!」
――予選を終えて、そして、決勝を迎えるまでの間に、チームがどう動いたのかということにも興味があります?

手前から片山義美(マツダ)小関典幸(スバル)大久保力(スバル)。車重の重いマツダキャロルはローレシオの一速ギアで最初に飛び出すだろう、と想定したリキさんは独自のギアセッティングで対抗した。
「決勝の前に、作戦会議がありました。そのときに、佐藤監督は“クサビ作戦”を採ると言明しました。スバル車で走るのは7台。レースが始まって一周したら、後方の4台はピットに入れる。そして、頃合いを見計らって再スタートさせ、この4台は他社チームのブロックに回る」
――然るべき場所にクサビを打ち込むようにして、敵を遮断する?
「……ということかな。これは軍事用語でもあって、騎兵隊が用いる作戦なのだとか。ただ、これがうまくいったかどうかは知りません。ぼくはひたすら走っていますから、後ろのことはまったくわからない(笑)。ともかく、このときのスバルGPチームは、社長直属のチームで、監督やエンジニアは、レースの結果にクビがかかってたから……」
――おお!
「その全体会議後に、副監督の部屋に、監督、副監督、小関選手、そしてぼくの四人が集まった。そのときに、監督が言ったのは『この一戦は、何としても、スバルが勝つようにしてくれ!』ということでした。そして、『きみたち二人のライバル意識はわかってるが、互いに意地の張り合いで共倒れになるようなことだけは、絶対に避けろ!』とも」
――「勝つようにしてくれ」という表現は、なかなか興味深いです。
「監督の言われることは、よくわかりますが、むずかしいですね。レースですし、それにまだ23~24才の若造ですし(笑)。ただ、小関選手と二人で話しているうちに、共倒れなんてみっともないということは、お互いわかっていますから、そういったことは絶対にしないという二人の共通の認識になっていきました」
――ええ。
「まずは、スタート後の1コーナーで、片山(義美)が前にいる状況になったら、二人で追いかけようということで一致しました。次に、スタートでは、片山が先に飛び出すだろうという想定があった。なぜなら、あれだけ車重が重いクルマで、そして4サイクルエンジンなので、1速のローギヤはかなり低いレシオになっているはずだからです」
――なるほど!
「スタート直後に“1速での片山”がまずリードする……というのは、大いに考えられる展開。さらに、どちらからともなく、スタート後に、ぼくと小関が同時にアタマに立っていたら、1コーナーに5メートルでも先に入る態勢になった方が、そのまま先行してレースを行なう。二番手となった方は、他車のブロックに回る。こういう合意になった」
――ははあ、その約束は?
「もちろん、結果的にも守られました。実際の決勝レースでは、スタート時に、ぼくは1速のまま、シフトせずに引っ張り続けて、2速に入れたときには首位に立っていた」
――おお、メカニック芳賀さんの想定通りですね!
「副変速機付きバージョンの場合は、おそらく、低1速~高1速~低2速……というようなシフトをしたはずです。でも、ぼくは“シンプル4速”だったから、そういう忙しいことをしないで済んだ」
「ストレートエンドで、ぼくは『俺がもらったぜ』と、手を挙げました。小関は『わかった』というように、左側(アウト側)にクルマを寄せた」
――“OK、俺はインには行かないよ”と?
「ぼくのセッティングは、とにかく直線スピード重視のセットです。というのは、エンジンが“一番”じゃなかったからね。チームは、クルマの総合性能を考えてのセッティングで、キャンバーにしてもトーインにしても、コーナー重視の仕様だったけど。でも、それだと、タイヤの抵抗が大きい」
「ぼくはコーナーはガマンしてもいいから、ストレートを速く!……というセッティングにした。そういうクルマだったので、コーナーでの他車との競り合いは、できるだけ避けたかった。ストレートで、可能な限り他車を離しておいて、そして、コーナーに入って行くように──」
「それができたのは、小関がブロックしてくれたからです。ただ、彼の高性能エンジンは、8500以上も回るはずだけど、でも、ブロックなどで走りやラインを変えたりすると、オーバーヒートや、プラグがカブるという恐れがあった。そしたら案の定、途中で、ミラーから小関の姿が消えてしまった……」
第三十七回・了 (取材・文:家村浩明)