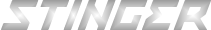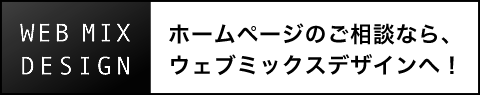シリーズVSC :その29・飛躍的に向上した安全性

今では強固なモノコックも、1966年当時は、クラッシュするとこうなった。1966年モンツァのイタリアGPでクラッシュしたギンサーのホンダRA273は、コクピット部分が大きくネジ曲がっている。
歴史の中に、モーターレーシングの機微が隠れている
イギリス期待のトム・プライスは、1977年第3戦南アフリカGPで、クラッシュして出火したマシンに消火器を持って駆けつけようとコースを横断したオフィシャルと共に不慮の死を遂げた悲劇のドライバーになりました。
現場は長いストレート。トラブルでコースの反対側に止まったマシンから火が出ているのを見た新米オフィシャルが、消化器を持ってコースを横断。しかし、時速300km/hで走ってきた白いシャドウに撥ね飛ばされてボロ雑巾のように回転、持っていた消火器がプライスを直撃する間の悪さが重なった悲惨のアクシデントでした。
仮にHALOを装着していたら、プライスは死なずに済んだかもしれません。しかしそれ以前に、HALOが開発されるほど安全対策が行き届いていれば、オフィシャルが不用意にコースを横断すること自体あり得ないことです。
シートベルト装着がF1で普通のことになったのは1968年以降。それまでは、シートベルトをしていた方が危険、という考え方もあり、さらに1950年代にはレーシングスーツではなく、半袖。ヘルメットは皮製で、戦前のレーサーの写真を新聞で観た日本人の感想は、“近づくと食われそうに怖い人”だったとのことでした。
1970年に入る頃から、ジャッキー・スチュワートが先頭に立って安全性が叫ばれるようになり、F1ドライバーが組織するGPDA(グランプリ・ドライバーズ・アソシエーション)も積極的に安全を主張、FIAがこれに呼応する形で安全が高まっていきました。

2016年、激しくクラッシュしたアロンソのマクラーレン。カーボンファイバーのコクピットは変形していない。
ボディ構造は、ドライバーを護る“クラッシャブル・ストラクチャー”と呼ばれる衝撃吸収構造が採用され、パイプフレームからモノコック、そしてカーボンファイバーと軽くて強い素材の採用で、コクピットは強固になっていきます。さらに、1994年のアイルトン・セナのアクシデントをきっかけに、ドライバーの頭部を護るためにコクピット左右が防護壁として盛り上がる形が規定され、プロテクターを外して乗り降りするのがF1の普通の光景になりました。
雨の時に視認性を高めるテールランプなど、細部の規定も進化し、そして今年から、ドライバーの頭部を護るHALOが装着され、F1は飛躍的に安全に生まれ変わりました。
マシンの安全性が高まり、さらに、大きな衝撃でヘルメットにかかる荷重を吸収するHANSデバイスをドライバーが装着することで脛骨の損傷が激減し、1994年のセナ以降の犠牲者は、2014年に日本GPで、間の悪い偶然の重なって撤去作業中の重機にクラッシュして翌年亡くなったジュール・ビアンキの1件だけになりました。
そして基本的に、カーボンファイバーのモノコックがドライバーを保護するようになった結果、マシンがバラバラになった2007年カナダGPのロバート・クビツァ、2010年バレンシアGPで宙を飛んだレッドブルのマーク・ウェバー、2016年開幕戦オーストラリアで、グティエレスのハースに追突し、回転してバラバラになったマクラーレン・ホンダから這い出したフェルナンド・アロンソのようなアクシデントでも、ドライバーはけがもしない素晴しい結果になりました。ちなみにクビツァは事故の翌年、同じカナダGPで優勝しています。
ただし、安全性が高まったことを喜んでばかりいられないかもしれません。気になるのは、安全性が高まると、ドライバーの危機管理意識が下がり、アクシデントが増えること。今年のF1を観ていると、50年前なら起こりえない接触事故が続いています。
派手なクラッシュも迫力という意味ではF1と切っても切れない見どころかもしれませんが、闘いは走って決まるもの。フェアプレーと安全の精神がドライバー全員に行き渡り、フェアで高度な闘いが展開されることを期待したいものです。
[STINGER]山口正己
photo by Honda/PIRELLI