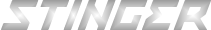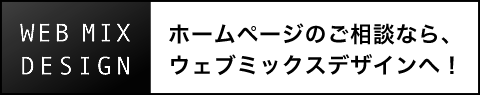ホンダの“復活”に期待を込めて–思い出す宗一郎の思想

1966年モンツァ、第一期で不信にあえいでいた頃のホンダF1チーム。
◆真実の言葉
![]() 以前見た深夜のテレビ番組、『F1 世界最速への挑戦 ~本田宗一郎を継ぐ者たち~』を思い出した。世界最速を目指す技術者の戦いを描いたドキュメンタリーだ。
以前見た深夜のテレビ番組、『F1 世界最速への挑戦 ~本田宗一郎を継ぐ者たち~』を思い出した。世界最速を目指す技術者の戦いを描いたドキュメンタリーだ。
当然、ホンダに期待を寄せた番組だったが、その中に印象深いコメントがあった。“なんでチャンピオンを取れなかったのですか?” という質問に、第一期ホンダF1の最後を共に戦ったワールドチャンピオン経験者のジョン・サーティースは、キッパリと言った。「やめたからですよ」。非常に深い、そして真実の言葉として響いた。
サーティースがドライバーだった第一期最後の1968年は、コンベンショナルな、つまり競争力の高いRA301でタイトルを狙えるはずだった。
RA301は、大幅な軽量化を計ったV12エンジンは、出力で他を圧し、サーティースと中村良夫さんが綿密な計画を立てて計画していたポテンシャルの高いマシンになるはずだったからだ。
しかし、空冷RA302が本田宗一郎のごり押しとも言える方針で進行し、つまり1968年はホンダの中に、水冷V12搭載のRA301組と空冷V8搭載のRA302組の“ふたつのチーム”が存在、開発力も予算も分断され、結果としてRA301の開発に歯止めがかかることになった。
『もしも』は許されないが、もしも空冷推進計画がなく、1968年のRA301にホンダのエネルギーや予算のすべてを投入できていたら、ホンダはチャンピオンになれた可能性があった。少なくもと、数戦の優勝は可能だったはず、というのがサーティースの言葉の裏に込められたメッセージに違いない。

革新の粋を飛び越えて佐野彰一主任設計者が書いた空冷エンジン搭載のホンダRA302の設計図。
空冷エンジンを搭載したRA302は、ごり押しで参戦したフランスGPでジョー・シュレッサーが亡くなるアクシデントを起こしてしまう。数周走ればオートバーヒートを起こすエンジンでは、サスペンションセッティングもままならず、参戦じたいに無理があった。だが、世の中、そう薄っぺらい上辺だけのものではない。
マイナスイメージの負の歴史を背負ってしまったRA302はその一方で、空冷に関係したエンジニア全員が、空冷3000ccのF1エンジンが成功しないことを分かっていながら開発を進めていたという。だが、エンジンの主任設計者だった後に三代目社長となる久米是志さんは、未知への挑戦という意味での開発が「非常に興味深く、充実したものだった」と回想している。このことは、別のストーリーにつながる可能性を示唆している。
もうひとつ『もしも』が許されるなら、もしも1969年もホンダが参戦を継続していたら、コンベンショナルなマシンでタイトルが取れたはず、という意味の他に、サーティースの言葉から想定できるさらに深いストーリーがある。
サーティースの言葉の“深さ”は、空冷F1を邪道と否定しながら、『もしも』第一期ホンダF1が、1968年で活動を休止せずに継続していたら、近距離テレメーターを採用して開発した軽量シャシーのRA302が、翌1969年、さらに軽量化できたはずの水冷V12を搭載して、強烈なポテンシャルを持つマシンに進化していたはずだ、という言葉が実現した可能性があるからだ。
サーティースは、その後、RA302を鈴鹿でテストし、イタリアGPのフリへー走行でもトライしている。
空冷エンジンは、オーバーヒートを克服できなかったが、シャシーの主任設計者だった佐野彰一さんの言葉が、別のストーリーも思わせた。
佐野さんは、宗一郎が空冷エンジンを提案した裏に、“軽量化への思い”があったのではないかと仰った。水の分だけ軽くなれば、クルマとして完成度が高くなるからだ。シャシーを担当した佐野さんは、空冷化の理由のひとつを、設計者を思いやる宗一郎の優しさと解釈していたのだ。
それを受けて佐野さんは、マシン各部の強度を確認するために、先行テストの役目をもたせた前年のイタリアGPに優勝したRA300に、ある仕掛けを載せた。センサーとそのデータを飛ばすためのアンテナを搭載し、近距テレメータを使ってデータを集め、徹底した軽量シャシーを作り上げたのだ。
当時としては異端だったそのマシンは、その後のF1マシンに多大な影響を与えた。常識を覆して極端に前方に位置するコクピットや、その後、ロータスが採用するサイドラジエターの方式でF1の定番になる低いノーズ、フェラーリが真似をしたエンジンの搭載方法などの他に、二分割のリヤウィングを電磁モーターで操作するためにステアリングにスイッチボタンが付くなど、きわめて先進的なマシンだったのだ。
宗一郎が、“無茶”と思える空冷エンジンをごり押ししなければ、これらのメカニズムが登場しなかったはずだ。
失敗を含めてそれを糧にして継続する。そのことが重要だと、サーティースは言ったのだ。
1954年、宗一郎は、藤澤武雄副社長が原案を創ったとされる『檄文』の中で、“我がホンダの使命は、日本の工業界の啓蒙にある”とぶち上げ、こう宣言している。
“私の夢は、自動車レースで世界の覇者になることだ”。
これが、4輪を生産するようになる10年も前に発した言葉であることも、サーティースの言葉は思い出させてくれた。
こうした深さは、現在のホンダ陣営がかみしめているに違いない。ホンダは、新たに、長い航海を始めている。
※この記事は、以前掲載したものを、加筆訂正し、写真を加えて再編集したものです。
[STINGER]山口正己
photo by Honda