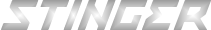『スクーデリア一方通行』の筆者である加瀬竜哉/本名加瀬龍哉さんが急逝されました。長い闘病生活を送りながら外には一切知らせず、“いつかガンを克服したことを自慢するんだ”と家族や関係者に語っていたとのことですが、2012年1月24日、音楽プロデュサーとして作業中に倒れ、帰らぬ人となりました。
[STINGER-VILLAGE]では、加瀬さんのなみなみならぬレースへの思いを継承し、より多くの方に加瀬さんの愛したF1を中心とするモーターレーシングを深く知っていただくために、“スクイチ”を永久保存とさせていただきました。
[STINGER-VILLAGE]村長 山口正己
王者は何処から?
’10年第7戦トルコGPは、’50年からF1に参戦し続けるフェラーリにとって、記念すべき800戦目のグランプリとなった。ひとことで800戦と言っても60年の歳月と、その間に起きた多くの世界情勢や突発的な出来事を乗り越えての偉大なる数字である。そしてもちろん、フェラーリよりも長い参戦歴を誇るチームは存在しないので、他の追従を許さない圧倒的な大記録、となる。フェラーリはこれまでの800戦/60年間で15のドライバーズ・タイトル(2位マクラーレン:12回)、1958年制定のコンストラクターズ・タイトルは16回(2位ウィリアムズ:9回)と圧倒的な数字を残し、今尚F1に君臨し続けている。多くのF1ドライバーが言う通りフェラーリに乗って世界王者になることは究極の目標であり、ことにイタリア人ドライバーにとっては夢のまた夢なのである。
F1ワールド・チャンピオン。その栄誉ある称号を持つ者は、これまでの60年に及ぶF1史の中で僅か31人しか存在しない。もちろん、その中にはミハエル・シューマッハーのようにひとりで7回も獲得する者もいれば、ヨッヘン・リントのように自らの死後にチャンピオンが確定した者もおり、それぞれに多くのドラマが存在する。
まず初めに、この60年に及ぶF1史に於けるワールド・チャンピオン一覧を御覧頂こう。

…..この31人の偉大なる王者の中で、複数回タイトルを獲得しているのは半数にも満たない僅か14人。皇帝ことシューマッハーの7回を筆頭に、’50年代の黎明期を引っ張ったファン・マヌエル・ファンジオが5回、続いて四天王時代を生き抜いたアラン・プロストが4回。3回組には自らの名を冠したシャシーで王者となったジャック・ブラバム、スター・ドライバーの第一人者ジャッキー・スチュワート、大事故から奇跡の生還を果たしたニキ・ラウダ、ブラジルが生んだ孤独な風雲児ネルソン・ピケ、そして不世出の天才アイルトン・セナらがいる。2回獲得組は’50年代のアルベルト・アスカリ、’60年代のジム・クラークとグラハム・ヒル、’70年代にはエマーソン・フィッティパルディ、’90年代にミカ・ハッキネン、そして近代F1の’00年代を代表するフェルナンド・アロンソらがいる。そしてもちろん、現役チャンピオン・ドライバーのシューマッハーとアロンソを含み、一昨年王者の若きルイス・ハミルトンや昨年王者のジェンソン・バトンにも年齢的/環境的に見てまだチャンスはあり、今季WRCに参戦中のキミ・ライコネンにも2度目のF1チャンピオン獲得のチャンスは充分残されている。
とは言え、シューマッハーの5年連続を含む7回という記録はあまりにも突出していると言わざるを得ない。この記録を敗るには相当な勝率と年月が必要となり、今季のような混戦を勝ち抜くのは極めて難しいと言える。ことに複数年、それも連続タイトルを獲得するとなると”所属チームの長期に渡る安定した強さ”が求められる。’00〜’05年のフェラーリはまさにそれにあたり、しかもフェラーリが絶対的なエースとしてシューマッハーを扱ったことが大きな要因であることは疑いようがない。よって、トップ4による混戦、という今季のようなシーズンが続くと、その可能性は俄然小さくなってしまうのである。
さて、この表からは解りづらいかも知れないが、これまで最も多くのF1世界チャンピオンを輩出して来た国はイギリスである。ただしこの”イギリス”にはスコットランドやアイルランドも含むが、その人数は10人と、全体の約3割を占める。自動車メーカーやレーシング・チームも多いモーター・スポーツ大国であるイギリス勢がそれだけ強いのは当然と言えば当然かも知れないが、そういう側面で見ると意外なデータが見えて来る。
このイギリスの10人に続くのは3人、ブラジルとフィンランドである。メンバーはブラジル勢がエマーソン・フィッティパルディ、ネルソン・ピケ、アイルトン・セナ、そしてフィンランドがケケ・ロズベルグ、ミカ・ハッキネン、キミ・ライコネンというラインアップである。この2ヶ国は少なくとも自動車産業からは縁遠く、ブラジルに至ってはF1のホーム・グラウンド、ヨーロッパですらない。フィンランドはその環境故にラリーは盛んだが、トラック上のレースでもこれだけ強いのは意外でもある。また回数でもブラジル勢はフィッテイパルディ2回、ピケ/セナが3回ずつと計8回で、イギリス勢の14回に続く2位、フィンランド勢もハッキネンが2年連続王座を獲得している。
「コンプレックス、と言えばその通りかも知れないね」ピケは分析する。「貴族のように誇り高きエマーソンがヨーロッパのドライバーを相手に勝利し、貧富の差が激しいブラジル国民は熱狂したんだ。それはサッカーのペレも同様で、つまり自国から世界的/国民的ヒーローが誕生したわけだ。それを見た俺達が『自分達にもやれる筈!』と思ってヨーロッパに渡って来たのは大きなきっかけだったと思うよ」セナもまた、ブラジルという祖国をヨーロッパから見た際、同じような価値観を持って発言していた。「ブラジルには貧しい子供達が大勢いる。彼らの世界的な活躍のきっかけになれたら嬉しいね」彼らの目線は”南米から見たヨーロッパ”、という大きなスケールだったのである。
フィンランドはご存知の通りの”ラリー大国”である。が、結果的に多くのF1ドライバー(つまりトラック競技者)を生み出していることを考えれば、これは天性のドライビング・センスと運転技術向上環境がスバ抜けている、としか思えない。「あまり区別はないよ」現在WRCに参戦中のライコネン(’07年王者)の言葉である。「大きく分ければ運転する、という意味で両者は同じ。ただ、イベントと言う意味ではラリーの方が遥かにオープンで楽しいね」…..内向的なライコネンらしい見解だが、彼らにとってそこが氷上であれ荒れ地であれクローズド・サーキットであれ、そう大きく変わらないものなのかも知れない。そういえばモナコやラスベガスのようなストリート・サーキットを、激しくテール・スライドさせながら強引にマシンを振り回すケケ・ロズベルグの勇姿が想い出される。
では、本来モーター・スポーツ大国と言われる他のヨーロッパ諸国の実情はいったいどうなのか。
例えばフェラーリ、そしてかつてはアルファロメオやマセラッティらが活躍したイタリアはと言うと、これまでに総勢98名ものイタリア人ドライバーがF1に参戦したが、なんと’50年代のジュゼッペ・ファリーナとアルベルト・アスカリ以来、ひとりも世界王者が出ていない。近年最も王座に近づいたイタリア人ドライバーは’85年にプロストに敗れたミケーレ・アルボレート(フェラーリ)だったが、以降フェラーリは総帥・エンツォによって「イタリア人ドライバーがフェラーリに乗るのとプレッシャーに押しつぶされてしまう」と自国イタリア人ドライバーを避けるようになり、参戦するドライバーの人数こそ膨大だがなかなか王座にまでは手が届かない。
近代F1でイタリア人ドライバーとして最も成功したのは鉄人リカルド・パトレーゼと言えるだろう。しかし257戦の参戦歴を持つパトレーゼのイメージは”ベスト・オヴ・セカンド・ドライバー”である。所属チームの戦闘力的に、最も王座獲得のチャンスが大きかった’90年代前半、パトレーゼはウィリアムズ・ルノーでナイジェル・マンセルの従順なNo.2を演じてしまい、そのキャリアは終焉に向って行った。またその将来を有望視されたエリオ・デ・アンジェリス、アレッサンドロ・ナニーニらは志半ばでそのチャンスを失った。現役ドライバーではヤルノ・トゥルーリ(ロータス)、ヴィタントニオ・リウッツィ(フォース・インディア)らがいるが、彼らの現在の環境を考えても、王座獲得が少々遠いところにあるのは否めない。そしてイタリアはあくまでも”フェラーリの国”であり、国民そのものもイタリア人ドライバーにかける期待は小さいと言わざるを得ない。そりゃイタリア人ドライバーが乗ってフェラーリが勝つところは観たいだろうが、我がフェラーリの勝利のためならドライバーは誰でも良い、が彼らの本心である。よって、イタリア人は少々母国ドライバーに対して冷たい国、と言えるかも知れない。
続いてはフランス。FIA本部があり、モーター・スポーツ発祥の地であるこの国からのF1世界チャンピオンは、実はアラン・プロスト(王座4回)ただひとりである。そしてプロスト引退後も、将来を有望視されたジャン・アレジ、オリビエ・パニスら以降、有望なフランス人ドライバーは出ておらず、昨年のロマン・グロージャン(ルノー)を最後に今季はフランス人ドライバー不在のF1シーズンとなっている。
フランスは’73年、当時期待の大型新人・フランソワ・セヴェールを失ったのが大きかった。師と仰ぐジャッキー・スチュワートの元でレースを学んだセヴェールは、次期チャンピオン最有力候補として有望視されながら、最終第15戦アメリカGP予選中に事故死。以降、かつての国営企業ルノーの威信を背負ったジャン・ピエール・ジャブイーユも、リジェの看板スターだったジャック・ラフィー、フェラーリに抜擢されたルネ・アルヌーらもタイトル獲得には届かなかった。それどころか昨年はアメリカン・フォーミュラを圧倒的な強さで制したセバスチャン・ブルデー(CART4年連続王者)がトロ・ロッソをシーズン中に解雇されるなど、フランス人F1ドライバーは完全に冬の時代を迎えている。ブルデーは嘆く。「僕らフランス人ドライバーの経済状態は決して良くはないんだ。それに、現代のF1はあまりにも高価過ぎるよ」プロストの4度目のタイトル獲得から早17年。モーター・スポーツ大国・フランスの名は既に過去のものとなってしまった。
が、更に意外なデータがある。メルセデス、そして撤退したBMWやポルシェも含め、強豪メーカーを擁するドイツ出身の世界王者も、これまたミハエル・シューマッハーただひとりなのである。
これまでにF1に参戦したドイツ人ドライバーは全部で55名。が、’61年にウォルフガング・フォン・トリップスがフェラーリで2勝を挙げ、初PPを獲得した第7戦イタリアGPで事故死、’75年第4戦スペインGPでマクラーレンのヨッヘン・マスの”ドタバタ勝利、実はこの3勝が、シューマッハー登場以前のドイツ人F1ドライバーの勝利の全て、なのである。マスの3勝目から17年間、ドイツはポルシェ、BMWらメーカーの活躍の影で優秀なドライバー不足に陥っていた。’85年9月、かのセナでさえ恐れた期待の新星、ステファン・ベロフがスパ1,000kmレースで事故死し、ドイツの夢は断たれた。現在でこそ多くのドイツ人ドライバーがグリッドに並ぶが、’80年代にはマンフレッド・ヴィンケルホックひとりが下位チームを渡り歩いているような状況だった。
大きな変革は’90年代にメルセデス・ベンツが行った若手ドライバー育成プログラムである。シューマッハー、ハインツ・ハラルト・フレンツェン、そしてオーストリア出身のカール・ベンドリンガーらの若手有望株をグループCのマシンに乗せ、前述のマスの指揮の元で英才教育を実施、その甲斐あって’90年代には多くの有望なメルセデス系・ドイツ人ドライバーがF1へとステップ・アップした。ちなみにF1でのドイツ人ドライバーによる勝利数は全部で109。その内訳は前述のトリップス2勝、マス1勝、そしてラルフ・シューマッハー6勝、フレンツェン3勝、セバスチャン・ヴェッテル6勝…..そう、残りの91勝は、なんと全てミハエル・シューマッハーによるものなのである。多くのF1ドライバーを輩出しているように見えるドイツだが、実際には極めてシューマッハー1色だったのだ。
さて、反対に真のモーター・スポーツ大国、と言えるのがイギリスである。何しろ現役王者のバトン、そして一昨年の王者ハミルトン。もちろん近年のみならず、記憶を遡ってみても各時代にひとり、確実にその時代を代表するイギリス人ドライバーが存在する。デイモン・ヒル(’96年王者)、ナイジェル・マンセル(’92年王者)、ジェイムズ・ハント(’76年王者)。そして’60年代にはジャッキー・スチュワート(’69、’71、’73年王者)、デイモンの父グラハム・ヒル(’62、’68年王者)、ジム・クラーク(’63、’65年王者)、そして2輪でも王者経験を持つジョン・サーティース(’64年王者)、’60年代はイギリス人4人で実に6度の王座を獲得する勢いである。クーパー、ロータス、BRMを初め現在マクラーレン、ウィリアムズといった強豪メーカー/コンストラクターを擁するイギリスは、イタリアとは確実に逆の考え方を持つ。60年のF1史の中でイギリス人ドライバーは153人おり、その中でチャンピオン経験者は10人。つまり最も効率良く王者を輩出しているのがイギリスなのである。
さて、気になるのはそれ以外の国である。’97年王者ジャック・ヴィルヌーヴは、カナダ人初のF1ワールド・チャンピオン。’82年に事故死した父、ジル・ヴィルヌーヴの成し遂げられなかった夢を叶えた2世ドライバーである。マリオ・アンドレッティ(’78年王者)、フィル・ヒル(’61年王者)はアメリカ人、まだインディ500がスケジュールに組み込まれていた時代、アメリカ人ドライバーにもF1でのチャンスは存在していた。オーストリアはニキ・ラウダ(’75、’77、’84年王者)ヨッヘン・リント(’70年王者)という天才を生み、オーストラリアはジャック・ブラバム(’59、’60、’66年王者)、デニス・ハルム(’67年王者)、そしてアラン・ジョーンズ(’80年王者)を輩出。シューマッハーに次ぐ5度の世界王座獲得者、ファンジオは南米アルゼンチン出身、ちなみにファンジオはアルゼンチンのベロン政権の支援で”南米代表”としてヨーロッパへ進出したエリート・レーサーであった。
…..さて、現状に眼を移そう。
現在ルノー在籍中のヴィタリー・ペトロフは’84年9月8日、レニングラード出身のロシア人ドライバーである。ペトロフはカートを経験せずに母国の自動車メーカー”ラーダ”の支援でアンダー・フォーミュラへ参戦、’05年に母国でフォーミュラ1600選手権を制し、その後目立った成績では’06年のユーロF3000選手権3位、’09年のGP2選手権2位などを経て今季ルノーからF1デビューとなった。
ペトロフはF1初のロシア人ドライバーである。当然母国からの経済的支援は大きく、持ち込み資金は1,500万ユーロ(約17億円)と言われている。しかしソ連崩壊後のロシアに於いて、国際的な自動車産業の発展へ向けた影響力は大きく、バーニー・エクレストンは’13年にもロシアGPを開催したい意向を表明している。もちろんペトロフは現在ロシアを代表するF1の第1人者であり、国際的な大スターである。そして今季のルノーの戦闘力も意外に高く、第7戦トルコGPでは多くのロシア人ファンの前で最速ラップを記録する走りを見せた。上手く行けばこのままペトロフがロシア人初のF1世界王者となる可能性もある。少なくともラーダという自動車メーカーの存在が現在のロシア情勢とF1を繋ぐ役割は大きく、例えば消え去った日本のメーカーとは捉え方が違っているのかも知れない。
続いて、インドの大富豪ビジェイ・マルヤ率いるフォース・インディア。このインド・ナショナル・チームにはドイツ人ドライバー(エイドリアン・スーティル)とイタリア人ドライバー(ヴィタントニオ・リウッツィ)しかいない。マルヤは「確かに我々のチームにインド人ドライバーがいれば最高だよ。だが、残念なことにまだインド人ドライバーはその水準に達していない。今我々に必要なのは優れた能力を持つドライバーであり、ナショナリズムは優先すべき事項ではないんだ」ちなみにF1史上初のインド人ドライバーは’05年にジョーダン・トヨタを駆ったナレイン・カーティケヤンである。ミシュランのドタバタ劇で出走6台となった第9戦アメリカGPで4位となった以外目立った成績を残すことは出来ず、僅か1年でシートを喪失し、ウィリアムズのテスト・ドライバーとなった。フォース・インディア創立時にはドライバーとして噂には上ったものの採用されず、現在はスーパー・リーグ・フォーミュラで闘っている。
そして今季、HRT(ヒスパニア・レーシング)からデビューを飾った史上ふたり目のインド人ドライバーがカルン・チャンドックである。”アイルトン・セナの甥”という、極めて目立つ存在であるブルーノ・セナをチーム・メイトに持つチャンドックはそれでも開幕戦予選がシェイク・ダウンとなった新チームで健闘し、時折セナを上回るパフォーマンスを披露。第6戦モナコGPではチェッカー直前のトゥルーリ(ロータス)との接触でリタイアするまで、13位を走行する活躍を見せていた。ちなみにチャンドックの父であるビッキー・チャンドックはインドのラリー王者経験者であり、昨年のFIA会長選挙の際にもその名が取り沙汰された、インドのF1での鍵を握る人物である。フォース・インディアのマルヤは「彼が上手くやれれば、我々のチームのドライバーに指名する可能性はあるよ」とチャンドックへの期待を寄せる。
ルノーでロシア出身のペトロフとタッグを組むロバート・クビサは’84年12月7日、ポーランドのクラフクにて誕生。ポーランド国内のカート選手権を総ナメにし、イタリアへと渡ったクビサはワールド・シリーズ・バイ・ルノー初代王者となり、そして’06年にチームを離脱したヴィルヌーヴの代役でBMWザウバーからF1デビュー、ポーランド初のF1ドライバーとなった。’08年第7戦カナダGPでの初優勝はポーランド人にとって初のF1勝利となり、史上唯一のポーランド人F1ドライバーでありつつ、次代のチャンピオン候補のひとりである。「ポーランドでは、既に僕はひとりで街を歩けなくなってしまった」”国民的ヒーロー”の誕生だ。「多くの人が僕を見つけると群がって来て、もう買い物や食事なんて出来やしないんだ。それは望んだ生活ではないけれど、自分がポーランドを背負っていることは痛感するよ。でも、プレッシャーにはならない」
…..ポイントはここである。仮にこれが日本人であったなら、そこには確実にプレッシャーという”見えない敵”との闘いが存在するからだ。少なくともマスコミはそう扱うだろう。
が、多くのF1ドライバー達は、必要以上に国の威信を背負わない。仮に背負っていたとしても、それを負の要素にすることはあまりない。ここが我が日本と決定的に違う部分なのである。
少なくとも中嶋悟はその”ニッポン代表”という特殊な環境に苦しんでいた。’87年、当時34歳の中嶋は全日本F2選手権3連覇という、ジャパニーズ・フォーミュラ・チャンピオンとして名門ロータスから堂々のF1デビューを飾った。が、その内状はエンジン・マニュファクチュアラーであるホンダとの結びつきによる、若きエース、セナのNo.2としての参戦であり、英語も苦手な中嶋は確実にヨーロッパ資本のF1で苦しんだ。もちろんF1以前に国際レースへの出場機会は多かったが、最高峰であるF1は全てのレベルがあまりにも高かった。セナは中嶋を”自分と同じ、非ヨーロッパ民族”として歓迎したが、中嶋自身はその意識レベルのあまりの違いに驚いたのである。
鈴木亜久里は中嶋に比べてオープンな性格も幸いしたが、それでもF1ドライバーとしてのキャリアの大部分をナショナリズムによって苦しんだ。純日本態勢を目論んだフットワークで元フェラーリ・ドライバーのイタリア人であるアルボレートに惨敗。片山右京はバブル崩壊という経済事情の煽りを受け、支援の継続に苦しんだ。また両者共に、日本のメーカーとのスポンサー契約を重視し、トップ・チームへの移籍を諦めるという決断を行っている。
が、昨年の中嶋一貴がトヨタのF1撤退と共にシートを喪失した横で、僅か2戦でその有望な将来性を示して見せた小林可夢偉が、メーカー支援もTDPも全く無関係のところでペーター・ザウバーの心を動かしたのは、これまでの”ニッポン代表”というイメージを完全に払拭するものと言えるのである。
そう、ナショナリズムとは、メーカーが母国ドライバーを連れて動き回ることではない。優秀な母国ドライバーを放っておけない企業が、ドライバーを支援するのが真の姿なのである。
…..さて、第7戦トルコGPではシューマッハー1色のドイツ人F1王者に名乗りを上げたドイツの若武者と、ブラバム/ハルム/ジョーンズ以来の王座を狙うオーストラリア人とが激突。その脇をふたりの現役イギリス人王者が駆け抜けて行った。第61代・F1ワールド・チャンピオンへの道は極めて険しい。シューマッハー以来ふたり目のドイツ人王者誕生か、それとも30年ぶり/4人目のオーストラリア人王者なるか。いずれも大国・イギリスの現役王者ふたりが阻止せんと立ちはだかるシーズンから、ますます目が離せない。
「自分以外が勝者なら、別に誰が勝とうが興味はないね!」/ジェンソン・バトン(’09年王者)