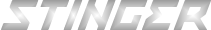『スクーデリア一方通行』の筆者である加瀬竜哉/本名加瀬龍哉さんが急逝されました。長い闘病生活を送りながら外には一切知らせず、“いつかガンを克服したことを自慢するんだ”と家族や関係者に語っていたとのことですが、2012年1月24日、音楽プロデュサーとして作業中に倒れ、帰らぬ人となりました。
[STINGER-VILLAGE]では、加瀬さんのなみなみならぬレースへの思いを継承し、より多くの方に加瀬さんの愛したF1を中心とするモーターレーシングを深く知っていただくために、“スクイチ”を永久保存とさせていただきました。
[STINGER-VILLAGE]村長 山口正己
跳馬の全て!
先日、筆者主催の某イベントにて”F1紹介コーナー”を行い、そこで筆者は深紅の跳馬がデザインされたフェラーリ・キャップを被って「皆で小林可夢偉を応援しようぜ!」という、ワケのわからない行動に出た(爆)。ちなみに’06年の同イベントではBAR・ホンダ/佐藤琢磨キャップ、ついでにシャツもBAR・ホンダ仕様。この時はゲストに村長・山ちゃんを迎え「ニッポンのF1をどうすべきか」について論議…..フム、それで琢磨ウェアなら筋は通ってる。で、今回はトークの相手がいるワケでもなかったので、単に「」カッコイイっしょ?、F1!」と思えるモノで良かった。そしたら選択肢はフェラーリになった、というワケ。もちろんホンダもトヨタもいなくなって、応援すべき日本チームは存在しなくなったんだけど、少なくとも筆者はF1を良く知らない人に紹介するにあたり、レッドブルでもフォース・インディアでもHRTでもなく、フェラーリを選んだ、ということ。
…..F1イコール、フェラーリである。いやいやそんなことないよ、マクラーレンもメルセデスもいるよ、って言うだろうけど、F1イ=フェラーリで正しい。反対に、F1=シューマッハーでもなければ、F1=可夢偉でもない。もちろんバーニー・エクレストンでもない。が、F1=フェラーリ、という図式のみ、正論なのである。
で、前回のコラムで記した通り、フェラーリは’10年第7戦トルコGPでなんとF1参戦800戦を迎えた。当然ながら前人未到の大記録、偉大なるフェラーリにしか出来ない、そして絶対に誰も抜くことの出来ない偉業なのである。
…..ちゅうワケで、先日のイベントでありがたいことに「モナコGP観ました!面白かった。可夢偉選手応援します!」などというメッセージを受け取ってしまった以上、F1ビギナーの明産に筆者自身がこのF1に必要不可欠な要素、フェラーリについて詳しく話しておかなければなるまい。なるべく解りやすく、んでなるべく簡素に…..それが一番難しいな(爆)、ガンバリマス!。
“フェラーリ”はひとことで言うとイタリアの自動車メーカー、である。が、例えばGMやトヨタのような巨大企業ではなく、FIATという大きな自動車メーカーの傘下に位置する、スポーツ・カー専門のブランドである。創業は1947年、設立者の名はエンツォ・フェラーリ(1898〜1988)。
エンツォは元々アルファロメオというイタリアのスポーツ・カー・メーカーのテスト・ドライバーを経て、’29年に自らのレーシング・チームである”スクーデリア・フェラーリ”を設立、アルファの準ワークス・チームとして活動。’47年にエンツォはアルファを退社して自社製マシンを開発するようになり、’50年には始まったばかりのF1世界選手権に参戦するようになった。ちなみにエンブレムの跳馬のデザインはイタリア空軍のエースであるフランチェスコ・バラッカのトレード・マークで、エンツォの兄であるアルフレッドが同飛行隊にいたために譲り受けた、と言われている。翌’51年第5戦イギリスGPにてF1初勝利。かつての所属先であるアルファロメオを破ったことから「私は母を殺してしまった」という名言を残す。’60年代にフェラーリは経営難となってFIATに身売りし、エンツォは市販車部門を事実上手放し、自らはF1を初めとするレース部門のみに関わるようになる。’70年代には世界的好景気の中でスーパー・カー・ブランドとしてその名を広め、日本でもランボルギーニ、ポルシェらと共にスーパー・カー・ブームの立役者となった。エンツォは’88年に90歳で大往生、’94年に国際モータースポーツ殿堂入り、’00年には自動車殿堂入り。自動車史に永遠にその名を残す、偉大なる人物がエンツォなのである。
さて、そういうワケでエンツォはフェラーリというスーパー・カー・メーカーの社長さんだったのは確かなのだが、エンツォ自身はあくまでも”レースこそ我が命”という人物だった。よって、イタリアでは「フェラーリはレースの資金のために市販車を売っている」と言われているほどである。F1にもメルセデス・ベンツやルノーを初め、多くの市販車メーカーが存在したが、フェラーリは唯一、レースを”市販車を売るための広告活動”とは捕らえていなかった。よって市販車も安全性や耐久性よりも美しさと速さを重視、当然ながら高価なものばかりとなった。しかしその徹底ぶりは逆に熱狂的なフェラーリのファンを増加させ、唯一無比の自動車ブランドとしての地位を確たるものとした。結果的にイタリア人はフェラーリを”象徴”とし、エンツォを”神”と崇めたのである。そして、高価で媚を売らないフェラーリの車は世界中のセレブの興味の対象となり、究極の選択にして裕福の象徴ともなった。しかしエンツォはその開発に殆ど関与することなく、興味と言えばF1で自らの名を冠したV12エンジンのマシンが勝利することのみ、であった。エンツォ自身はメカニックやエンジニア部門の人間ではなかったが、若い頃にパッカードに憧れ、ハイ・パワー・エンジンこそ美学、という価値観の持ち主であった。そして自らのマシンを駆るレーシング・ドライバーを愛し、一喜一憂した。つまり、エンツォは完全なカリスマとして、世界にその名を轟かせる存在なのである。
さて、続いてはF1レーシング・チームとしてのフェラーリ、に的を絞ってみよう。
’50年代、ことにコンストラクターズ選手権の存在しない黎明期には多くのドライバーがフェラーリのマシンを駆ってF1GPに出場した。ワークス・チームはイタリア人ドライバーのアルベルト・アスカリをエースに据えた。フェラーリ初勝利はアルゼンチン人ドライバーのフロリアン・ゴンザレスにより、’51年第5戦イギリスGPで成し遂げられた。この年はアスカリが2勝を挙げて選手権2位となり、翌’52年にはかつての所属チームである宿敵アルファロメオを破ってアスカリが世界王者となった。’53年もアスカリの強さは揺るがず2年連続王座を勝ち取り、フェラーリは黎明期から既にF1のトップに君臨する存在となった。
’54年はマイク・ホーソン(イギリス)、モーリス・トランティニャン(フランス)らが活躍、しかしシーズンはマセラッティ、メルセデスなどを渡り歩いたアルゼンチンの天才レーサー、ファン・マヌエル・ファンジオが席巻していた。そのファンジオは’56年にフェラーリへ移籍してここでも圧倒的な強さでタイトルを防衛、しかしファンジオが再びマセラッティへと復帰した’57年は未勝利に終わり、’58年はホーソーンがタイトルを奪取した。
’60年代はアメリカ人のフィル・ヒルが活躍し、’61年に初王座に着いた。’64年には2輪でも王者となったジョン・サーティースがチャンピオンとなり、フェラーリはコンスタントにトップを奪っていた。が、F1はロータスやクーパーなどのイギリスのコンストラクターが台頭し、手軽なフォード・コスワースV8エンジンとヒューランド製6速ギア・ボックスを使用するチームが活躍し初め、フェラーリら12気筒エンジン勢は苦戦を強いられるようになって来た。エンツォの「12気筒エンジンこそフェラーリ」という概念により、彼らは’64年のサーティース以降、10年に渡って選手権制覇から遠ざかってしまう。
’73年、フェラーリは起死回生を計り、若干25歳のルカ・モンテツェモーロを監督に抜擢する。イタリア・ボローニャ生まれのモンテツェモーロはフィアットのジャンニ・アニエリ会長の息子と噂される私生児で、弁護士になるためにローマ大学卒業後にコロンビア大学に留学、そこでエンツォ直々の誘いでフェラーリのチーム・マネージャーに就任。’74年にフェラーリ入りしたオーストリア人のドライバー、ニキ・ラウダと共にフェラーリを生まれ変わらせることに成功、”横置き型トランスミッション搭載”を意味する”T”の着いたフェラーリ312Tはコスワース勢を凌ぐ速さを見せ、’75年にラウダが初タイトルを奪取。翌’76年に第10戦ドイツGPでラウダが瀕死の重傷を追うも奇跡的に復活、最終戦富士で「雨のため危険」と自らマクラーレン・フォードのジェイムズ・ハントとのタイトル争いを放棄するもコンストラクターズ選手権を連覇、翌’77年はラウダが完全復活して2度目のタイトル獲得+コンストラクターズ3連覇を成し遂げ、’79年には南アフリカ出身のジョディ・シェクターが初のタイトル獲得。フェラーリはモンテツェモーロの指揮の元、黄金期を迎えた。
’80年代に入るとF1はターボ・エンジン全盛となる。当然12気筒派のエンツォの想いとは裏腹なものとなるが、フェラーリは早い段階でターボ開発に着手し、’81年に1.5L・V6ターボを投入、’82〜’83年とコンストラクターズ選手権を連覇。しかし’82年にはエンツォ自身のお気に入りだった若きカナダ人ドライバー、ジル・ヴィルヌーヴがチーム・メイトのフランス人、ディディエ・ピローニとの激しい確執を経て事故死、ピローニも同年中に再起不能の事故で離脱するなど、フェラーリの内状は決して良い状態とは言えなかった。’80年代中盤からは再びフェラーリに冬の次代が訪れ、新たなチーム監督にラリーでランチアを指揮していたチェザーレ・フィオリオを起用。’88年にはエンツォが90歳で他界。直後のイタリアGPではゲルハルト・ベルガーとミケーレ・アルボレートが地元で1-2フィニッシュを成し遂げ、16戦15勝を挙げたマクラーレン・ホンダに一矢を報いる、エンツォの弔い合戦としてファンは熱狂した。
’90年代はそのマクラーレンで王者となったアラン・プロストとナイジェル・マンセルの布陣で幕を明けた。エンジンは全チームNA(自然吸気)エンジンが義務付けられ、フェラーリは’89年から再び伝統のV12エンジン・ユーザーとなる。またフェラーリは他に先駆けてF1初の斬新なセミ・オートマティック・トランスミッションを採用。しかし’90年こそシーズン終盤までマクラーレン・ホンダのアイルトン・セナとタイトルを争ったが、翌’91年からは様々なハイ・テクノロジー分野開発で遅れを取り、フェラーリはまたも低迷。フェラーリはフィアット役員となっていたモンテツェモーロを再び招聘し、社長兼マネージング・ディレクターに任命。’93年にはラリーとスポーツ・カー選手権で実績のあったジャン・トッド(現・FIA会長)を監督に起用し、チーム態勢の立て直しに着手。期待の若手ドライバーだったジャン・アレジはこのチーム改革に乗れず僅か1勝でフェラーリを離脱、’96年には、ベネトンで選手権2連覇を果たしたドライバーのミハエル・シューマッハー、テクニカル・ディレクターのロス・ブラウン、そしてマシン・デザイナーのロリー・バーンを一気に引き抜き、’99年にはようやく16年振りのコンストラクターズ選手権制覇を達成した。
’00年代に入るとフェラーリは圧倒的な強さを見せ、シューマッハーがドライバーズ選手権5連覇(’00〜’04年)、コンストラクターズ選手権6連覇(’99〜’04年)を達成。’02年には全17戦中15勝、F1通算150勝を記録した。シューマッハー引退後は宿敵であるマクラーレン・メルセデスから移籍のキミ・ライコネンが’97年選手権を1ポイント差で制して初タイトルを獲得するが、マシン開発分野でレギュレーション対応に遅れを取ることが増え、苦しいシーズンが続いた。チームはトッドの引退後に若きステファノ・ドメニカリをチーム代表に任命、バーン引退後は直属の部下だったアルド・コスタがデザイン部門を取り仕切っている。
…..そして’10年、フェラーリはルノー在籍時にフェラーリ/シューマッハーを苦しめたスペインの英雄フェルナンド・アロンソ(’05〜’06王者)を新たなエースとして起用、フェリペ・マッサとのコンビで開幕戦バーレーンGPで1-2フィニッシュと、好スタートを切った。しかしレッドブルやマクラーレンなどのライバル勢に開発の遅れを取っていることは明白であり、今後の選手権が苦しいものとなるのは明らかである。
…..こうしてフェラーリの歴史を文章にまとめて見ても、実際にはフェラーリの魅力は全然伝わらない。書いてる自分がモドカシイ(爆)。ちなみに筆者が初めて観たF1(’76年インジャパン/富士)ではラウダが豪雨を嫌い、序盤に自主的にリタイアしたために正直そこまでの印象には残らなかったし、その独特のV12サウンドもウェット・レースのペースでは解らない。しかもスーパー・カー少年だった筆者にとって、フェラーリ=ディノ246、または308GTBかデイトナ、というのがイメージの全てだった。よって、どちらかと言うとフェラーリを魅力的に感じ始めたのはジル・ヴィルヌーヴの登場と重なっていた気がする。つまり、フェラーリの全盛期にF1を観始めたわりに、実は低迷して喘ぐフェラーリに興味を惹かれた、というのが正直なところである。
フェラーリの人気を分析するにはまず、総帥エンツォ・フェラーリの存在である。
自動車産業に於けるカリスマは何人もいる。フェルディナンド・ポルシェ、フェルッチオ・ランボルギーニ、そして本田宗一郎…..しかし、これら全ての自動車カリスマの頂点に立つのがエンツォ、と言っても過言ではない。
アルファのテスト・ドライバーとして念願のモーター・スポーツへ足を踏み入れ、チーム・マネージャー職まで与えられながら上層部との激突によりアルファを去り、そして自らのチームを興し、遂には古巣アルファに打ち勝つ…..これだけとっても充分に魅力的なストーリーだが、その深紅のボディに描かれた跳馬-カヴァリーノ・ランパンテ-の美しさがイタリアのみならず世界中のファンを引きつけることとなった。ちなみに深紅、というのはあくまでもイタリアのナショナル・カラーであり、決してフェラーリ特有のものではない。が、燃えるような赤、という誰もが望み憧れる色を世界中で最も制服しているのは他ならぬフェラーリであると断言出来る。当然、アルファもマセラッティも深紅のカラーリングで闘っていたわけだが、今では深紅=フェラーリ以外の何物でもない。
次に、そのV12エンジンの存在。’70年代、多くのコスワースV8ユーザーに圧されながらも伝統に拘り続け、一際甲高いエンジン・サウンドを轟かせていたのはエンツォの「エンジンこそ全て」というポリシーに基づいていた。ある意味、シャシーをないがしろにしていたとも考えられる点だが、むしろそれはフェラーリの絶対的な個性となり、流行に左右されず、我が道を行くスピリットに人々は魅了されたのである。
またエンツォ自身、’56年に最愛の息子であるディーノを病気で亡くして以降、人前に殆ど姿を現さなくなり、そのカリスマ性に拍車がかかった。そして何より、エンツォの魅力はその”レーサー魂”にある。F1に参戦する他のどんな自動車メーカーも景気や成績により確実に市販車の売上とチーム運営の狭間で苦しむが、エンツォは完全にレーサーであり、市販車業務は事実上”建前”と言えた。自らかつて採用を断られた経緯のあるフィアットに身売りした際も、スクーデリア・フェラーリの勝利のためであるなら厭わない、という姿勢が明確であった。そう言ったエンツォのスピリットが真のレーサー魂として人々の心を打ち、捕らえて止まないのである。
カー・ナンバー27…..。かつてF1は現在のように前年のコンストラクターズ選手権に基づいたチームごとのカー・ナンバー制度ではなく、新たなチャンピオン・チームが前年の王者と入れ替わる時代だった。’79年、ジョディ・シェクターの王座獲得によりチャンピオン・ナンバーを付けていたフェラーリは’80年の王者ウィリアムズ(アラン・ジョーンズ)とのナンバー入れ替えにより27、28番が割当となった。ジル・ヴィルヌーヴは’81〜’82年に不振のフェラーリを屈辱のカー・ナンバー27で走り健闘、’82年の悲劇の死により伝説のナンバーとなった。以後、フェラーリではアラン・プロスト、ジャン・アレジらの人気レーサーがこのナンバーを継承することとなり、覇権の移ったマクラーレン時代にはアイルトン・セナも27番で走行、カー・ナンバー27はF1で1番と同様かそれ以上に栄誉あるナンバーとなったのである。もちろん、現在のレギュレーション/出走台数からカー・ナンバー27はF1には存在出来ない。
ちなみに’95年のインディ500優勝者、ジャック・ヴィルヌーヴはジルの息子であり、この際のカー・ナンバーも27。ジャックは’97年にF1世界王者となり、父の夢を叶えてみせた。
F1のような最高峰カテゴリーに於いて”一貫性”というのは非常に難しく、ことに大きな組織/FIAによる度重なるレギュレーション変更はフェラーリのイメージを保つには難しい状況になることもある。’06年に義務付けられたV8エンジン・レギュレーションはハイ・パワー・エンジンに拘るフェラーリにとっては大打撃であった。エンツォ存命中であればF1撤退もあり得たかも知れないが、現状フェラーリがサーキットで轟かせているエンジン音は充分にカン高く、V12時代を彷彿とさせる。最も、他のチームも同様にV8とは思えないサウンドを響かせてはいる。が、そこで深紅のルックスと”望む”サウンドのイメージが一致してしまうのがフェラーリの偉大なところなのである。
フェラーリの特色、と言えるのが通称”お家騒動”と呼ばれる人員交代劇である。エンツォの「フェラーリは悪くない。それに関わる人間が悪いのだ」とのスピリットにより、多くの関係者/ドライバーが出入りすることとなった。しかしこれはある意味”人材を育てる”という環境とは程遠く、成績が悪ければ誰かが責任を取ってチームを去る、というのがフェラーリの恒例人事となってしまった。特に’80年代後半から’90年代にかけては顕著で、チーム・リーダーもドライバーも長続きしないシーズンが続いた。そう言った意味では、トッドを迎えた’90年代後半からの”一貫性”が数年後に身を結び、そして長期に渡る圧倒的強さに繋がったのは、モンテツェモーロ傘下での”脱・エンツォ思想”に基づいた成功例、と言えるだろう。そうでなければ、現在のドメニカリ・フェラーリ態勢はとうに崩壊していたに違いない。
ティフォシ。”熱病患者”を意味するこのイタリア語は、スバリ熱烈なフェラーリ・ファンを指す。60年間というF1の歴史を常にその名で、常にその色で走り続けているマシンなど他に存在しない。ティフォシ達はその深紅のマシンの動向に一喜一憂し、他の地元イタリアのチームやドライバーへの扱いとは明らかに違う。例えフランス人監督の元でドイツ人ドライバーが日本製のタイヤと南アフリカ人の設計によるエンジンで勝利しても、それが深紅のフェラーリであること、が最重要となる。実際エンツォのアルボレート起用以降、フェラーリは積極的にイタリア人ドライバーをフェラーリに乗せない。むしろ昨年のルカ・バドエル、ジャンカルロ・フィジケラらの結果を見ればその意味も良く解るだろう。フェラーリとティフォシにとって必要なのは、我がフェラーリを速く走らせることの出来る人間であり、その国籍は全く厭わないのである。
偉大なるフェラーリは決して新人の登竜門などではなく、ある程度の実績を持ったドライバーが乗るもの…..これは特に’90年代以降に顕著に見られる傾向である。それは他チームのようにテスト・リザーブ・ドライバーとして若手が乗る機会を得られるようなチームではないことをも意味している。事実、シューマッハー引退後、そして昨年のマッサの事故後の代役ドライバー人事騒動を見れば解るように、フェラーリには若手ドライバーの支援システムが存在しないのがネックとなっていた。そのために昨年から新たに”フェラーリ・ドライバー・アカデミー”が設立され、ジュール・ビアンキ、ダニエル・ザンピエーリ、ラファエル・マルチェッロ、そしてミルコ・ボルトロッティらの若手有望株達が所属。ちなみについ先日アカデミー加入が発表された最年少のランス・ストロールはカナダ出身の11歳である。果たしてマクラーレンに於けるルイス・ハミルトンのように、未来のフェラーリを背負って行ける逸材を発掘出来るか。しかし、フェラーリのドライバー交代説の際に囁かれる名前は、相変わらずモトGP王者のバレンティーノ・ロッシばかりなのが現実である。
「いつかはフェラーリ。それを夢見るのはドライバーとして当然のこと」とはセバスチャン・ヴェッテルの本音である。「もちろん今のチーム(レッドブル)に満足している。でも、先のことなんて解らないよ。フェラーリは伝説の存在であり、他のどんなチームとも違う特別なものなんだ。数年先だったら移籍もあり得るかも知れないね」ヴェッテルのフェラーリ入りに関してはバーニー・エクレストン自身が裏で画策している、との噂が立つほど。同様にヴェッテルの同僚であるマーク・ウェバーやルノーのロベルト・クビサらにもフェラーリ移籍の話題が上った。つまり、F1で活躍を見せるとフェラーリ入りか、という憶測が流れる仕組みだ。しかし、現在フェラーリはエースのアロンソに加え、現在不振に喘いでいるマッサの契約を’12年まで延長したばかりである。「我々はファミリーなんだ」…..その家族の一員となることは、他のどんなチームに加わることよりも栄誉あることなのだろう。
こうなればある意味当然、という考え方も出来るが、フェラーリのF1での影響力や発言力は大きい。それは他チームから「フェラーリだけがF1で優遇されているのではないか」という憶測、及び妬みを生む。が、バーニー・エクレストンが’08年にこれを公然と認める発言をし、話題となった。
これまで何度となくFIAと参戦チーム側が運営法や資金面で激突を繰り返し、何度となくチーム側が労働組合的に結束し、独自の選手権を立ち上げる動きを見せた。が、その水面下でFIAはフェラーリを買収、労組からの離脱を成功させていたのである。…..こうした特殊な例も、フェラーリの名の下にはさほどの事件性が感じられず、マスコミも深追いしない。それもまたフェラーリの魔力のひとつ、と言えるだろう…..。
筆者が個人的に最も印象深いフェラーリのレース…..ひとつに絞るのは難しいが、’88年第12戦イタリアGPは鳥肌が立ったレースである。
エンツォ没後役1ヶ月、地元イタリアの観衆は完全にエンツォの弔い合戦の様相。しかし現実にはアラン・プロスト/アイルトン・セナのマクラーレン・ホンダ勢がここまでシーズン全勝、健闘するフェラーリ勢はゲルハルト・ベルガー/ミケーレ・アルボレートを擁してグリッド2列目からのスタート。レースはいつものようにマクラーレン勢が圧倒的有利に先行、しかし34周目にプロストがエンジン不調でリタイア、フィニッシュ目前の49周目にはトップのセナが周回遅れを抜き損ねて接触し、リタイア。これでベルガー/アルボレートのフェラーリ1-2態勢が完成した際の、あのモンツァのスタンドの様子は忘れられない。飛び上がる人、泣き叫ぶ人、呆然とする人…..世界中の全ての観衆が、偉大なるエンツォの強大な影響力を思い知った、正に伝説の神懸かった1戦であった。
’50年のF1世界選手権誕生から参戦し続ける(ただし初戦は’50年第2戦モナコGP)フェラーリのF1参戦800戦。以来、優勝回数211回、表彰台フィニッシュ計632回(2位223回/3位198回)、ポール・ポジション獲得203回、最速ラップ樹立221回、年間ドライバーズ・タイトル獲得15回、コンストラクターズ・タイトル獲得16回…..これらは当然ながら記録である。現在グリッド上に並ぶどのマシンよりも古くから、そしてどのマシンよりも威風堂々と存在するフェラーリ。
…..ここでその魅力を伝えるのは極めて難しいが、TV中継でも一際目立つ深紅のあのマシン、あれがF1の醍醐味であり、象徴なのです!。
「レーシング・マシン。それは強力なエンジンに4つの車輪を付けたものだ」/エンツォ・フェラーリ