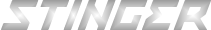『スクーデリア一方通行』の筆者である加瀬竜哉/本名加瀬龍哉さんが急逝されました。長い闘病生活を送りながら外には一切知らせず、“いつかガンを克服したことを自慢するんだ”と家族や関係者に語っていたとのことですが、2012年1月24日、音楽プロデュサーとして作業中に倒れ、帰らぬ人となりました。
[STINGER-VILLAGE]では、加瀬さんのなみなみならぬレースへの思いを継承し、より多くの方に加瀬さんの愛したF1を中心とするモーターレーシングを深く知っていただくために、“スクイチ”を永久保存とさせていただきました。
[STINGER-VILLAGE]村長 山口正己
F1スポーツ論
“世界選手権”の名の下に世界各地を巡るF1。今でこそ全17〜18戦をそれこそ欧州/北米/亜細亜/中東と網羅しているが、当初はヨーロッパの、それもほんのイタリア/フランス/イギリスあたりの極地的な自動車メーカーによる”娯楽”に近い存在だったこのイベントが現在のように巨大なものになるには文化の発展や世界経済、そしてスポーツ観戦などの形式の変化など、様々な要因を以て50年以上の月日を擁した。反面、自動車レースにはいつも付いて回る疑問符が存在する。
「自動車レースは純粋なスポーツと言えるのか」である。
長くモーター・レーシングを見守って来た方々には、おそらく簡単な答が存在するだろう。それは自動車メーカーやレーシング・チームによる”技術競争”というスポーツと、ドライバーによる”運転技術”というスポーツが、共にレギュレーション/規則の下に競われているのだから立派なスポーツである、という答であり、自動車レースを”ヒューマン・スポーツ”という側面でのみ論議するのはあまりにも愚問である、という答でもある。しかし、一般的な”競技”というジャンルから見てモーター・レーシングが少々異端な存在であることも事実であり、普段から接する機会のない人や子供達が自動車レースを初めて眼にした際、その疑問と闘わなければならなくなることも事実である。その中身は「自動車なのか運転手なのか」である。
F1のプロモーターであるJPSKスポーツは、バーニー・エクレストンとの交渉に於いてF1開催を目指すインド政府に向け、フォーミュラワン・アドミニストレーションに対し開催確約金として3,650万ドル(約34億円)を送金するよう要請した。が、インド政府及びスポーツ大臣からの返答は「NO」であった。理由は、
「オリンピックなどの側面から見た際、F1は商業的なエンターテインメントであり、他者との争いに勝利することを目指すスポーツとは言えない」
というものだった。同時に、それらの資金はインド国内の他の分野で使われるべきで、国内のスポーツ発展に於いて何の影響も齎さないとし、事実上F1開催を”蹴った”のである。JPSKスポーツのスポークスマンであるサミール・ガウルはこの件について大筋で認め、F1はインドでの開催計画の断念を余儀なくされつつある。
…..よもや、アジア/中東地域でこれだけF1開催が浸透している現状でこの状況はさしものバーニーでも予想していなかった。反対にヨーロッパ以外の多くの国がF1誘致に四苦八苦している状況の中、上り調子のインド・チームであるフォース・インディアの存在も含め、最も有利な状況下にいる、しかも経済的に発展中のインドからこの返答が返って来るのは衝撃的でさえある。何故なら、深刻な金融危機と煙草を初めとした広告規制の激しいヨーロッパを見切って中東/アジアにターゲットを絞ったのはF1サイドの方なのである。
このスクイチでも紹介している通り、こうしたサーキット/開催国に絡むトラブルは後を絶たない。イギリスGPはドニントンなのかシルバーストーンなのか、ドイツGPはニュルブルクリンクなのかホッケンハイムなのかという問題も、モーター・スポーツ発祥の地・フランスGPや北米のカナダGPなど、本来F1の歴史に欠かせなかった筈のグランプリがカレンダーから除外されているのも、全て政治的/経済的な交渉の末の結果である。先日鈴鹿サーキットが’11年までの日本GP開催を確約したが、それ以降の確定的要素は存在しない。全てはF1という巨大ビジネスと、それに伴う国際的な政治力によって決まって行くのである。
フォース・インディアのチーム・オーナー、ビジェイ・マルヤは経済成長期にあるインドの大富豪のひとりである。’07年にスパイカーF1チームを買収し、母国インドでF1のムーヴメントを起こし、地元GPで勝利することが目標、とする。当然ながら当初は最後尾を争う状況だったが、つい先日の’09年第12戦ベルギーGPではジャンカルロ・フィジケラがチーム初のポール・ポジションを獲得し、決勝レースでもフェラーリのキミ・ライコネンとチェッカー目前までトップ争いを見せ、大殊勲の2位表彰台を獲得するに至った。このフォース・インディアの存在は、明らかにインドでのF1初開催に向けて強力な要素となる筈だった。が、インド政府はF1をインドの発展のために身銭を切ってでもやるべきイベント、とは考えなかったのである。それにしても「F1はスポーツではない」とは随分な豪語だ。
それがスポーツであるかどうかの論議は別として、F1世界選手権は巨大な興行/イベントである。当然巨額の資金が動き、観客のチケット代金も一般的なスポーツに比べれば割高である。理由は明白で、それが広大な敷地/設備と高額な道具を使用すること。そしてその選手権に参加しているのがチームや選手個人だけではなく、世界を代表する自動車メーカーだということ。が、例えば野球やサッカーを例にとれば、スター選手とそうでない選手、若手とベテランが切磋琢磨し、スポンサーの付いた所属チームの契約下で他チームと選手権を争う、という点では全く同じである。しいて言うなら、野球やサッカーにあってF1にないものは徹底した”ナショナリズム”だ。
確かにフェラーリはイタリアの象徴であり、メルセデス・ベンツはドイツが誇るメーカーである。が、チーム監督や選手であるドライバーを初め、そこにあるのは”国際色”である。確かに自国のスタッフ/スポンサー/選手で固めることは理想だが、チームにとって必要な人材が外国人であれば、彼らはそれを喜んで受け入れる。事実、前述のインド・チームであるフォース・インディアも、ドライバーのフィジケラはイタリア人、エイドリアン・スーティルはドイツ人である。
サッカーのワールド・カップも野球のワールド・ベースボール・クラシックも、出場する選手は普段所属しているチームの国ではなく、母国のナショナル・チームの代表選手として参加する。F1では競い合うのは選手個人であると同時に、参戦するチームそのもの、というカテゴリーを逸脱しない。例えばウィリアムズというイギリスのチームが日本のエンジン・メーカーと組み、ドイツ人ドライバーで世界の頂点を目指して闘うのがF1世
界選手権なのである。反対に、野球やサッカーのように普段ライバルである者同士が組んで闘うことはあり得ない。そういう意味では、このカテゴリーのナショナリズムは他のスポーツとは捉え方に大きな相違点が存在する。ただし、これはWRCなどの他のカテゴリーを含め、F1だけではなく自動車レース全般に言えることである。
次に、”スポーツ”という側面で考えた時、このカテゴリーには競技上、人間的な要素/才能以外に非常に大きな特徴が存在する。それは”道具の善し悪し”である。
自動車レースでは当然ながら各チーム/メーカーが用意した”クルマ”という道具を選手が操作する。そして、選手本人が元気でもクルマが音を上げてしまうことや、その性能の善し悪しなどで成績が大きく左右される。ただし、これは自動車に限ったことではなく、例えばヨットや射的など、オリンピックにも登場するような競技に於いてもそういったカテゴリーは存在する。にも関わらず、何故か自動車レースは極端な話「クルマが良ければドライバーが下手でも勝てる」という表現で揶揄されてしまう。反対に、優れたドライバーでも「クルマがダメなら勝てない」となる。
’09年第10戦ハンガリーGPの予選中に頭部に重傷を負ったフェリペ・マッサの代わりにフェラーリから出走したテスト・ドライバーのルカ・バドエル。彼は’99年を最後にF1の実戦には出走していない38歳、もちろんその10年間の間に多くのレギュレーション変更があり、当時とはサーキットもマシンも大きく変わってはいるが、バドエル自身が少なくともチーム・メイトで元ワールド・チャンピオンのキミ・ライコネンと実力を比較される位置にいたことは確かだった。そして、その結果は非常に顕著に表れた。バドエルはライコネンから常に秒単位の遅れをとり、予選/決勝を通じて通常の同一チームのふたりのドライバーの成績としては異例の差がついた。極端に言えば、ライコネンは極めて勝利に近い位置で闘い、バドエルはほぼ全編に渡って最後尾争いをすることとなった。単純に、同一のひとつのチーム/クルマを使用して、これだけの差がついたのはドライバーの違い、と言うことが出来る。ま、先に答を言ってしまうのなら「最高のドライバーが最高のクルマに乗れば無敵」ということになるのだが、サーキット・レイアウト、クルマのポテンシャル、開発力、戦略、技術陣の状況判断など、多くの要素が噛み合うことでレース結果が左右される以上、全てが理想的に機能しなくては最高の結果を出すのは困難である。
近年、この自動車レースに良く似た事態を引き起こしたのが水泳である。ある特定のメーカーの開発した水着の着用により、多くの選手が世界新記録を初めとする自己ベストを更新し、オリンピックや世界選手権を前にスポンサー契約なども含めて多数の選手がそのメーカーの”道具”を使用することを望み、社会現象とも言える問題となった。水泳という、一見完全にヒューマン・スポーツに見える競技にすらこうした影響は存在する。おそらく、多くの陸上選手がウサイン・ボルトと同じシューズの使用を試すだろう。余談だが、’09年の世界陸上/200m決勝で、ボルトは「気分を変えようと」ユニフォームの下にTシャツを1枚余分に着た。そして自己の持つ世界新記録を0.11秒縮めて見せた…..彼にとっての”道具”とは、いったい何なのだろうか…..。
ウィリアムズ・チームのドライバー、ニコ・ロズベルグが興味深い発言をしている。「勝利のための要素の80%はマシン、ドライバーは20%だ」将来のワールド・チャンピオンと言われるスター・ドライバーの発言としては驚きだが、現実的な意味合いでは非常に納得が行く。「最高のクルマと最低のクルマの差は1周あたり約2秒、最高のドライバーと最低のドライバーの差は1周0.3秒だと思う」ロズベルグの所属するウィリアムズは過去にコンストラクターズ・タイトルを9回、ドライバーズ・タイトルを7回獲得した、F1で3番目に成功しているチームである。チーム・オーナーであり”闘将”の異名を持つフランク・ウィリアムズは「我々のマシンがトップ・チームより0.5秒遅くても、世界最高のドライバーがいれば勝てる」と言う。逆の見方をすれば、世界最高のドライバーを擁していても、0.5秒以上マシンが遅いのなら勝てない、とも取れる。
F1で2番目に成功しているマクラーレン(コンストラクターズ8回/ドライバーズ12回)は’88年、奇才ゴードン・マーレイによるMP4/4という名車に無敵のホンダ・ターボエンジンを搭載し、アイルトン・セナ(王座3回/故人)/アラン・プロスト(王座4回)という”最高の布陣”で闘い、シーズン16戦中15勝(1敗はトップ独走中のセナのリタイア)でWタイトル獲得、という圧倒的な強さを見せた。これは近代F1を語る上で、全てに於いて最高のものが揃った際にしか出ない結果として象徴的な例である。
そしてF1で最も成功を治めたフェラーリ(コンストラクターズ16回/ドライバーズ15回)は、F1史に残る天才ドライバーであるミハエル・シューマッハーを擁し、’00年から’04年までの5年間、Wタイトルを連覇し続けた。これでシューマッハーはベネトン時代の’94、’95年と合わせて通算7回のドライバーズ・タイトルを獲得し、チームもジャン・トッドの指揮の元、ベネトン連覇の立役者であるロス・ブラウン、ロリー・バーンらのスタッフを擁し、特に’02年は17戦15勝という圧倒的な数字を残している。が、この5年間及び前後のフェラーリの闘い方はマクラーレンとは決定的に違う点がある。戦略上のドライバーの扱い方である。
タイトル5連覇を成し遂げたシューマッハーの影で、チーム・メイトのルーベンス・バリチェロは常に”セカンド・ドライバー”だった。チームはシューマッハーのドライバーズ・タイトル獲得に全力を注ぎ、仮にバリチェロがレースをリードしていたとしても、2番手を走るシューマッハーにその順位を譲る、という行為をチームに強いられており、時にはバリチェロ自身が公の場でその不満を露にした。この流れはシューマッハーのタ
イトル獲得が決定するまで続き、如何に他チームのライバルをポイントで引き離していたとしても、フェラーリが手を抜くことはなかった。所謂F1″チーム・オーダー事件”である。
これは近代F1に於いて”スポーツマン・シップ”という点で大きく論議の対象となった出来事である。しかし、この件が問題視されるよりもずっと前/F1黎明期の’50年代に遡れば、エース・ドライバーの勝利のためにチーム・メイトがレース中に自らリタイアしてマシンを提供する、なんてことが当然の行為だった。’60年代にもエース/セカンド・ドライバーの立場はハッキリとしており、それに比べれば現在の選手権は相当”スポーツらしい”と言うことが出来る。が、そのスポーツの中にもオフェンダーとディフェンダーの役割がハッキリしている競技はいくつもあり、それを言い出したら野球ひとつ取っても敬遠/送りバント/犠牲フライなどはある意味スポーツマン・シップに逆らうものとして、時には野次の対象にすらなってしまう。が、これらを総じて”チーム・プレイ”と呼んだ時、その杞憂は愚問にさえなる。勝利/あるいは得点に向け、何かしらの犠牲を伴う監督の指示と、’02年のフェラーリの戦略に大きな違いはない筈である。が、結果に対して使用する道具の比率がこれだけ高い競技も稀であり、勝つために”手段を選ばない”という徹底度は極めて高く、フェラーリとシューマッハーの行ったことはその延長上にある。かつて「負けを拒否するのが勝者」と言ったのはNASCARドライバーのデイル・アーンハートだった。
本末転倒ではあるが、元来F1をスポーツとして論議するのは些か無理なハナシでもある。レギュレーションに則った開発/技術競争、酷暑の中で300kmの距離を体力と反射神経を駆使しながら闘うドライバーの行為は明らかなスポーツである。が、試合結果に関してのみ眼を向ければこれらの要素は霞み、研究/開発により多くの資金/人材を投入した裕福な富豪が所有するチームが勝ち、そうでないチームに足りないものが”金”であるという図式で語られてしまう。そこにはドライバーの才能や努力を無視し、馬力や性能に勝る道具優先の考え方によってモーター・スポーツを卑下する人々も存在する。しかし、それもある意味モーター・スポーツの見方/楽しみ方のひとつなのかも知れない。だからこそ、フェラーリを愛するイタリア国民はオール・イタリアンによるナショナリズムを望まないのかも知れない。しかし、例え勝利からはほど遠くても、予選16番手からスタートした弱小チームの無名の若手ドライバーが、天候に左右されるレースでほんの一瞬でも最速ラップを刻んだりするのがたまらなく面白い。そして「彼にトップ・チームのマシンを与えたらどうなるのか」という妄想と期待を抱かせる。そんな魔力があるのもF1ならでは、だ。
「あのクルマ(ウィリアムズFW15C)に乗りゃ、猿でも勝てるよ」’93年/ナイジェル・マンセル