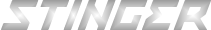『スクーデリア一方通行』の筆者である加瀬竜哉/本名加瀬龍哉さんが急逝されました。長い闘病生活を送りながら外には一切知らせず、“いつかガンを克服したことを自慢するんだ”と家族や関係者に語っていたとのことですが、2012年1月24日、音楽プロデュサーとして作業中に倒れ、帰らぬ人となりました。
[STINGER-VILLAGE]では、加瀬さんのなみなみならぬレースへの思いを継承し、より多くの方に加瀬さんの愛したF1を中心とするモーターレーシングを深く知っていただくために、“スクイチ”を永久保存とさせていただきました。
[STINGER-VILLAGE]村長 山口正己
F1スポンサー哀歌
11月後半、藁をも縋る状況であるニッポンのF1メディアに”小林可夢偉、ルノー移籍か“の文字が電光石火のごとく走った。可夢偉は複数の日本企業のバックアップにより、既に今季限りでF1から撤退したBMWから移籍のロベルト・クビサの同僚として’10年のルノーのシートに座るかも知れない、というもの。が、この1年でF1からホンダ/富士スピードウェイ/トヨタが去り、そしてブリヂストンまでもが’10年いっぱいでの撤退を決めたこの御時世で、本当にそんな殊勝なスポンサーが日本に存在するのか?。もし本当なら、これは既にF1を見切ったこの国の救世主と成り得るのか、そして可夢偉がヨーロッパのチームで日本を背負って立つF1ドライバーとして活躍する日はやって来るのか。そして、元来F1というヨーロッパ文化に於いて、日本企業はいったいどんな意味を見い出し、何故去って行ったのか。
ことの始まりはフランスのモーター・スポーツ誌”Auto Hebdo”の記事だった。トヨタのF1撤退によってシート喪失となった可夢偉が、日本企業のバックアップを受けてルノーに移籍する。ここから多くの方が連想するのがトヨタF1撤退発表時の山科忠TMG会長…..いや、山科忠専務取締役の”涙”だろう。「ここまで育てて来たふたりなので、出来れば何処かのチームに乗せたい」その言葉が無念に咽ぶサムライと映ったか、サラリーマン社会ニッポンの茶番と映ったかは人それぞれだが、少なくともメーカー単位で見れば「何処かのチームに乗せたい」などという資格はトヨタにはない。それが”日本”というカテゴリーであるならば中嶋一貴も佐藤琢磨も井出有治も同様な筈である。が、世界/F1に通用するドライバーを育てることを命題としたTDP(トヨタ・ヤングドライバー・プログラム)の頂点にようやく辿り着いた途端、それも素晴らしい走りを見せ、結果を出した途端に「急に辞めることになったのであとはご自由に」が通用しないのも、”何処かのチーム”に起用する権限もないのも事実である。
しかし少なくともセンセーショナルなデビューを飾った可夢偉が多くのF1関係者から絶賛される存在であることは間違いない。が、歴史的に見た際、”適切なタイミングに適切な場所にいる”ことが重要であるF1サーカスの中で、日本人は特にその立ち回りが上手くないことは認めざるを得ない。事実可夢偉が輝いた途端、その基盤となるトヨタがF1を去ったのはその典型例と言える。そしてそのトヨタの撤退は、ヨーロッパ社会から見て決してスタイリッシュではなく、全F1チームによる”コンコルド協定”という尊いルールを踏みにじるものだった。’12年までの参戦を確約しながら/もしくはF1チームに確約させておきながら、上層部は水面下で辞めるタイミングを見計らっていた。どうやら、日本人には「ギリギリまで頑張りました。でもダメでした」という美学が存在するらしい。ソイツはただの”嘘つき”だ。そして、その犠牲になるのはいつも”現場”なのである。
山科専務の涙がそういった政治的な背景を持つのか、それとも親心という極めてプライベートなものなのかは解らないしどうでも良いが、この無責任なお国柄と方針の中でその未知なる才能を活かす場を奪われる形となった可夢偉は今や”悲劇のヒーロー”である。急遽呼ばれた第15戦日本GPの大雨のフリー走行でマシンに慣れることも出来ず、デビュー戦となった翌第16戦ブラジルGPでは勝負強さは見せたものの荒さでライバル達から非難を浴び、迎えた2戦目の最終戦アブダビGPでキッチリ全てを学習し、素晴らしい走りでポイントを獲得してみせた。当然、翌年レギュラー・シートを得て更なる成長を期待されるドライバーである。今季のブライテスト・ホープ/ベスト・オブ・ニュー・カマーはブエミでもアルグエルスアリでもグロージャンでもなく、間違いなく可夢偉のものである。その期待の新星がこのままF1から消えてしまうことになれば大問題。「道は作ってやった/あとは自分でどうにかしてみろ」その逃げ道が使えないことは、それこそ山科専務の涙が全てを物語っている通りである。が、F1から去り行く日本企業に彼らを守ることは出来ない。誰もがその諦めを感じていた矢先のこの報道に、それが例え憶測であったとしても驚きを隠せない。
今回の報道で可夢偉をサポートするとされているのはPanasonicとKDDIである。
当の2社から何もコメントがない以上この報道自体が憶測の域を出ないが、この2社はトヨタのスポンサーとしてチームをサポートして来た日本企業であり、考え方によってはトヨタのF1撤退により、自らの意思とは関係なくF1での広告活動の場を失った側、という見方が出来る。もしも彼らが可夢偉と共にこの未曾有の経済不況の中でF1という夢を目指すのだとしたら…..それはちょっと”粋”な話だ。
Panasonicは松下電器が’08年にナショナルからブランド・ネームを改めた巨大家電メーカーであり、’02年のトヨタF1参戦時から常にメイン・スポンサーとして活動を共にして来たビジネス・パートナーである。KDDIは固定電話から携帯電話を中心とした情報通信事業を取り扱う有力メーカーであり、F1参戦2年目の’03年よりトヨタのスポンサーとなった。ちなみにトヨタは前身のKDD時代からの大株主でもある。もちろんこの2社とて現在の経済不況は他人事ではなく、Panasonicは三洋電機を傘下に収めて事業拡大を行い、KDDIは価格競争の激しい分野での革新的な時代の移行と向かい合っている。が、その中で両社がF1というカテゴリー/フィールドが今後のマーケティングに必要な場であると判断するのであれば、現状その”イメージ・キャラクター”を務められる人物が可夢偉しか存在しないのも事実であり、この噂の信憑性を高めるのに一役買っている。
Panasonicは昨年、契機満了だったトヨタとのスポンサー・シップ契約を’12年まで延長した。眼の前でホンダがF1を去り、スズキ、スバル、ダイハツ、そしてカワサキらが相
次いで主要モーター・スポーツ部門を閉鎖する最中に於いて、チーム発足以来常に共に歩んで来たトヨタへのサポートを継続する決定を行ったことは特筆に値する。が、その時点ではまだトヨタのお膝元である富士スピードウェイでの日本GP開催があり、トヨタにはホンダの離脱でこの先3年間の”ニッポンのF1″に於けるオンリー・ワンの位置が保証されていた。如何に経済状況が不利であれ、露出度の一貫性を考えればギリギリのギャンブルである。しかしそのトヨタが裏切った今、新チーム参入でコンストラクターの概念が再編成となる今、不透明なF1継続が彼らに齎すものは一体何なのか。
日本企業とF1との関係で最も密接なのは当然ながらホンダの参戦歴になるが、彼らは若年層への広告効果、という自動車産業としてのターゲットを持った上でのメーカー参戦及び技術供与であり、NGKやMobilなどの自動車関連企業などと共にここでは区別し、あくまでも協賛の形を取った”スポンサー”という概念のみで捉えた際の日本メーカー、を想い出してみよう。
’70年代に日本初コンストラクターとしてF1GPに挑戦したマキF1は、参戦2年目となる’75年に日本の時計メーカーであるシチズンのロゴを青い車体に纏って登場した。結果的に3年間の活動で非選手権レース以外での予選通過ならず、’76年に撤退を余儀なくされたこの日本の小さなチームが行ったのが最初のF1スポンサードである。ただし、決勝出場のなかった彼らに当然ながら広告効果は期待出来ず、第1期ホンダの撤退から’76年のF1インジャパン/翌’77年の富士での事故を経て、まだまだ日本にF1人気は定着しなかった。それらの状況が一変するのは’80年代後半、ホンダと中嶋悟、そしてフジテレビによる”F1ブーム”まで待たなければならない。
’83年にエンジン・サプライヤーとしてスピリットと共にF1へ復帰したホンダは翌’84年からウィリアムズへのターボ・エンジン供給を行い、ケケ・ロズベルグのドライヴで第2期初勝利を挙げ、’86年にはナイジェル・マンセル/ネルソン・ピケのコンビでコンストラクターズ・タイトルを獲得。翌’87年にロータスへのエンジン供給が決まると中嶋悟が日本人初のレギュラー・シートを射止め、フジテレビによる全戦テレビ中継がスタートする。
マシンのボディのみならず、放送枠では日本のCanon、EPSON、PIAAらがマシンやドライバーを起用したテレビCMを流し、その存在をモーター・スポーツのファン層へと知らしめた。やがて鈴木亜久里や片山右京らが中嶋の後に続き、東芝、GEO、JTらが続々とF1へと参入した。中でもJTはCABINとMild SevenブランドでF1へ深く関わり、’95年にはミハエル・シューマッハーを擁してベネトン・ルノーでWタイトルを獲得した。
日本人とスポンサー、という意味で忘れられない存在が井上高智穂である。井上はレーシング・ドライバーとしての目立ったキャリアは持たなかったが、自らのマネジメント能力を駆使してオフィス・サービスのユニマット/英会話のNOVAを持ち込みスポンサーとしてF1シートを獲得。結果も残せず、長期参戦にも繋がらなかったが、これがある意味日本企業のF1との関わり合い方を象徴する形態ともなった。’94年にF1ブーム最大の象徴であるアイルトン・セナがレース中の事故で他界すると、徐々に日本国内でのF1人気も下降を初め、以後日本企業はF1というワールド・ワイドなイベントに対して慎重になって行った。
多くのスポンサーが出入りするF1に於いて、イタリアのアパレル企業・ベネトンのスタンスは極めて合理的であった。彼らはいくつかのチームにスポンサー・ロゴを描き、マーケティングの拡大を狙うが、その露出に関して更なる飛躍を求め、遂にはトールマンF1チームを買収、チーム名称そのものをBenettonとした。そして彼らは本来自らが広告主であったチーム/マシンに他のスポンサー・ロゴを纏い、’94年にドライバーズ・タイトルを、翌’95年にはWタイトルを獲得する。そしてそのブランド戦略が成功した後、エンジン・サプライヤーであったルノーにチームを売却、「目標を達成した」ベネトンは悠然とF1から去って行ったのである。
日本でもF1で同じことをやった/目指した例がふたつある。ご記憶の方も多い筈の、レイトンハウスとフットワークである。
レイトンハウスは実業家である赤城明によって経営されていた不動産会社・丸晶興産のブランドで、’84年から国内のモーター・スポーツに関わり、F3000時代から個人スポンサードを行っていたイタリア人ドライバー、イヴァン・カペリを擁し、’87年にレイトンハウス・マーチとしてF1に進出。’89年にはマーチを完全買収し、’90年からチーム/コンストラクター名も”レイトンハウス”とした。同名のアパレルも展開するレイトンハウスはその個性的な”マイアミ・ブルー”と称されるカラーリングで話題となり、日本でも多くのファンを獲得。しかし翌’91年に赤城社長が丸晶興産と富士銀行の不正融資事件により逮捕され、チーム経営から撤退。2年間の最高成績は’90年フランスGPでの2位、その後マーチ・チームそのものも衰退し、’92年いっぱいで撤退、丸晶興産は’98年に破産した。
フットワークは’81年に複数の運送会社の合併によって出来た全日本流通を母体とする宅配便業者である。初代社長の大橋渡は’89年にアロウズを買収してF1チームのオーナーとなり、マシンを自社の配送トラックと同じカラーリングにペイント、’92年には無限ホンダ< /font>・エンジンと鈴木亜久里を擁し、オール・ジャパン体制を築く。しかし’93年に経営難からフットワークはF1チームを手放して撤退、残されたチームはコンストラクター名変更料を出し惜しみ’96年までフットワークを名乗るがその後再びアロウズへと戻る。最高成績は4位(’95年最終戦/ジャンニ・モルビデリの3位は既にフットワーク経営ではないので含まない)。その後’01年にフットワークは倒産し、大橋社長は証券取引法違反で在宅起訴され、’02年に執行猶予付きの有罪判決を受けている。
この両者に共通して言えるのは、既存のヨーロッパのF1チームをバブル景気による潤沢な資金で買収し、日本チームとしたものの、バブル崩壊と共に撤退を余儀なくされた、という点である。’90年10月、大蔵省の融資規制は急激な株価下落を呼び、日本のバブル景気は崩壊。その時点で日本のF1人気は頂点に達していた。彼らの他にも伊東和夫のエスポ(ラルース/鈴木亜久里)、中内康児(ミドリブリッジ/ブラバム)らが象徴的な存在であった。振り返れば’89年、日本企業である三菱地所がニューヨークのロック・フェラー・センターを買収したことに象徴されるように、歴史/伝統を重んじることなく、その瞬発的な資金力だけで買収という手段に出るのがバブル当時の日本のスタイルだったことは否めない。よって、その資金が底をついた時、多くの非難と落胆の中で去らなくてはならないのが日本企業の性である。そしてそれは20年近くを経た現在でも、少なくともF1に於いてさほどの進歩は見せていない、ということになる。
そもそもF1マシンにロゴを描き、広告効果を狙うという概念が持ち込まれたのは’68年のゴールドリーフ・ロータスである。それまでナショナル・カラーと参戦メーカーのロゴのみだったF1マシンに煙草マネーが持ち込まれ、”マシンは走る広告塔”となり、それによってチーム運営資金は飛躍的に潤沢となって行った。F1/モーター・スポーツと煙草ロゴの関係性については皆さんも心当たりが多いと思うが、’70〜’90年代にかけてF1とは切っても切れない関係性を築いた。John Player Special、Marlboro、GITANES、CAMEL、BENSON & HEDGES、BARCLAY、Lucky Strike、555、Gauloises、Rothmans、Winfield、West…..多くの煙草銘柄が、F1マシンのボディやウィングを彩った。やがてヨーロッパが煙草広告禁止に動くと同時にF1は規制の緩いアジア/中東へと開催国の枠を広げ、現在のような形態へと変化して行った。しかしその後煙草広告は完全にタブーとなり、現状ではフェラーリをMarlboroのフィリップ・モリス社がスポンサードしている以外は全て消えてしまった。
煙草メーカーに変わってF1マシンに多く描かれるようになったのがIT/コンピュータ関連企業である。Compaq、Hewlett-Packard、Acer、NOKIA、Vodafone、Lenovo、Telefonica…..世界最高峰の技術を争うF1GPに、彼らの注目が集まるのは当然である。しかしそれも時代の流れ/経済不況と共に各メーカーの負担は大きくなり、その多くが広告スペースから去った。現在世界市場拡大を狙うVodafoneがマクラーレンの冠スポンサーを継続し、2度の世界王者フェルナンド・アロンソをスペインのTelefonicaがバックアップするのみとなった。ちなみに日本のKenwoodはマクラーレンの公式ピット無線サプライヤーとして、来シーズンで’91年以来実に19年目を迎える。
また、所謂”オイル・マネー”と呼ばれる中東地域の企業もこの世界的な広告効果に興味津々であり、サウジアラビアのSaudia航空が潤沢な資金でウィリアムズにWタイトルを齎したのを筆頭に、インドのKingfisherがトヨタからフォース・インディアへ、ドバイのEmirates航空がマクラーレンをサポート。アブダビのEtihad航空はスパイカー〜フォース・インディア〜フェラーリとF1スポンサー活動を継続中である。またPETRONASはマレーシアの国営石油/ガス供給企業であり、BMWザウバーのスポンサーであると同時にマレーシアGPの冠スポンサーとしても資金を提供している。F1GP開催状況を見てもトルコ/バーレーン/アブダビの3国が世界選手権に名を連ね、近隣のアジアでもマレーシア/シンガポール/中国/日本、そしてここに’10年から韓国が加わる。オーストラリア/ブラジル/カナダなどの”アウェイ”を加算すると、今やヨーロッパ内でのF1開催は全GP中半分以下になってしまったのである。
市場の変化に於いては、世界的規模の金融機関のF1世界選手権への露出度合いも顕著に現れる。USF&Gはアメリカの保険会社、Santanderはスペインの大手銀行、オランダの金融機関であるING、RBS(ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド)、HSBC(香港上海銀行)、更にはCREDIT SUISSE(ファイナンシャル)、Allianz(保険)…..特に現在は”ユーロ”という通貨制度も相まって、金融機関が世界市場へ進出するのは比較的容易なことと言える。またドイッチェポストやDHL、Fedexなどは運送会社である。世界中を転戦するF1のイメージが彼らの広告戦略と一致することは疑いようがない。
現在、F1のグリッドを見渡して一際異端な存在がレッド・ブルである。レッド・ブルは’84年にデートリッヒ・マテシッツによりタイ産の栄養ドリンクの販売権を取得して興されたメーカーで、’04年にジャガー・レーシングを買収してF1チームを所有。他にも2輪、エア・レース、サッカーなど多くのスポーツ/競技の支援に積極的である。特にF1ではレッドブル・ブランドでワークス・チームとセカンド・チームのトロ・ロッソの2チームを所有し、自社ブランドのスカラシップによる若手ドライバーにチャンスを与えながら、遂に’09年にはタイトル争いを繰り広げるトップ・チームへと成長した。
一見、前述の日本のいくつかのスポンサー・メーカーと同様のようで、実際にはその内容たるや雲泥の差である。何しろ、多くの自動車メーカーが相次いでF1を撤退するような世界的な不況の最中にあって、世界的な販売戦略、更にはマテシッツの異常なまでの競技好きが相まって、その事業枠を拡大し続けている。大元となる商品販売に陰りがないのも特筆に値するが、如何なる際にもしっかりとした基盤を持った上で攻めのビジネスを展開するその一貫性は、恐らく島国・ニッポンの常識の遥か上を行っているのだろう。
家電メーカーであるPanasonicと通信事業のKDDI。誰もがF1に見切りをつける中、彼らの思惑がもし崖っぷちに立つ可夢偉とニッポンの救世主となるのであれば、それに続く武者の登場も期待出来る。ただし、当のルノーが果たして’10年のグリッドに本当に並んでいるのかは、少なくともクリスマス頃までは誰にも解らないことも付け加えておく。
「レースはチェッカー・フラッグ。白と黒。グレーはない。カネがなけりゃレースも出来ないんだ
」/デビッド・シアーズ