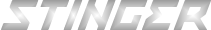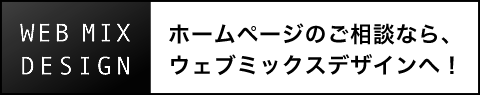ドリフト世界戦への期待

ドリフトの理解者ジャン・トッドFIA会長も絶賛!!
9月30日と10月1日、世界初のFIA公認ドリフト大会が、台場駅と船の科学館駅に挟まれた特設会場で行なわれた。2日間で20,055人の観客が訪れた世界初の大会は、日本の川畑真人が総合優勝。ジャン・トッド会長も9月30日の初日を視察し、盛り上がりの好感触に笑顔を見せた。
ジャン・トッド会長といえば、ミハエル・シューマッハ時代にF1チームのスクーデリア・フェラーリのチーム代表だったことは知られたところ。その前には、プジョーのルマン参戦や、WRCやパリ-ダカのマネージメントにも辣腕を発揮し、特にWRCやパリダカの経験から“ドリフト”の理解者としても名高い人物だ。

そのトッドF1A会長が太鼓判を押した『FIA Intercontinental Drifting Cup』、まずはスタートしたことを喜び、関係者一同に感謝を伝えたい。
今回は、“スタートすること”が最大の目的であり、関係者の苦労が忍ばれるところだが、今後に期待を寄せたいからこそ、現状に対して苦言も呈しておきたい。
1976年の日本GPからF1GP300戦ほど、ルマン24時間やインディ500、デイトナ500などの世界の主要レースや、グッドウッド・フェスティバルofスピードなどのワールドクラスのイベント、さらには、ジュネーブ、フランクフルトなど、世界レベルの各国のモーターショーや、全英オープンゴルフなどの国際的なイベントを見物した経験から、『世界』を改めて認識しておきたいと思う。
◆世界に見せるという視点–参加者のレベル

総合優勝した川畑真人、2位のアルカディ・サレグラセブ(ロシア)、3番手の齋藤太吾など上位陣の爽快なテクニックは、文句の付けようがないものだった。日々の鍛練と練習の成果が、お台場特設会場で発揮され、上位に君臨したのは実に見事で楽しめた。しかし、参加者全体のレベルを見ると、世界戦に相応しい“洗練”にはまだまだ遠いイメージを受けた。
そうなったのは、6月に突然開催が決まり、世界各国のシリーズ戦が終わっていない、つまり、チャンピオンが決まっていないところで決行してしまったからだ。とはいえ、ここについては、今後、参加基準をブラッシュアップして、さらなにレベルアップができることに期待しておきたい。
◆世界に見せるという視点–パレード

10月1日の競技開始を告げるパレードを見て、若干の違和感を感じた。19台の出走車がコース外周を回って所定の位置に付くのだが、大きな国旗を掲げたその様子が、まるで暴走族の隊列のように見えた。中には、箱乗りしている選手もいた。アピールはわかるが、もう少し“品格”が欲しかった。“世界戦”ということがどういことなのか、主催者も参加者も、グローバルな認識がほしいところだ。
◆世界に見せるという視点–まったりしたスタート前進行
1998年にデイトナ500を見物して、観客の意識を徐々に、そして確実に高めていくスタート前進行の見事さに舌を巻いた。オフィシャルや関係者に、そうした“テクニック”を学ぶための“視察”を推奨したい。
デイトナ500のスタート前進行についての詳細は、こちら。
◆世界に見せるという視点–マシンのカラーリングと仕上がり
9月29日、実践を前にした参加マシンをパドックで見物した。遠目では分らないけれど、細部の美しさに若干残念な部分が見えた。実際に、決勝日の走りを見る限り、スタンドからの距離では、細部までは分らない。さらに、接触の頻度が高いので、いちいちこだわっていられないという事情も理解できた。しかし、モータースポーツは、圧倒的な美しさの上にこそ成立する。ドリフトのクォリティが高いだけに、こうした部分が気になった。
Gをよどみなくつなげる走りはもちろん、エンジン音もマシンも、美しいことが絶対条件だ。国内の地方レベルの楽しい寄り集まりなら、肩肘張らずにいいかもしれないが、究極である“世界戦”は、そこを超越した美しさがほしい。
選手の言動や立ち居振る舞いも、回数を重ねる毎に成長し、文字どおりの“世界一決定戦”になってほしいと思う。これは、総合優勝した川畑真人を始めとする参加選手の意識向上に期待したい。ドリフトが可能性を秘めているだけに、レベルアップをしてほしいと心から思う。
ちなみに、1980年序盤、年間500戦の隆盛を極めたドリフトの先駆であるダートライアルが、若干似たような環境にあった。ダートの上を走ることから、マシンの美しさという点で、かなりレベルが低かったが、やがて全日本選手権となる過程で、美しさはきわめて大切との想いから、“ベストカラーリング賞”を所属した雑誌社から提供した。そうした流れの中で、ホコリで汚れたイメージのダートラも徐々に美しいマシンで戦われるようになった。選手や関係者の意識で、“本物”は寄り広く受け入れられる。
◆世界に見せるという視点–周辺のイメージ
特設会場であることから、さまざまな対応は簡単ではないことは最初から見えていた。特にVIPやメディアの対応が、主催者の頭痛のタネだったことは想像に難くない。
VIPのホスピタリティは、鈴鹿の日本GPで実績のある『ドミニク・ボーセ』というフランス料理のシェフを招聘して万全を期していた。野外のテントしかない悪条件の中で、この部分は及第点だった。メディアのために用意されたドミニク・ボーセのランチパックも好評だった。
そうした状況を理解した上で、参考までに、上海サーキットが行なわれる中国GPの話をしておきたい。
上海サーキットは、ストレートの両端に、9階の高さでコースをまたいぐ“空中回廊”があることが有名だ。1コーナー寄りのそこは、パドッククラブのVIP席になる。注目すべきは、最終コーナー寄りのもう一つが、報道関係者用のメディアセンターになっていたことだ。
2004年に初めて中国GPが開催されたときにそのメディアセンターに通されて、思わず唸った。スタート地点を上から俯瞰して見えるそこからの眺めが素晴しかったからではない。そういう場所に報道関係者の席を用意したことに感心したのだ。
文化も思想も違う世界各国からの取材陣がそこを訪れる。結果として、彼らはそこで感じたものを、各国で報道するのだが、往々にして、“気分”や“先入観”で情報が伝わる。
上海サーキットで行なわれたF1GPの情報は、各国で流れたが、知る限りで悪口はなかった。それは、空中回廊をメディアセンターにした効果ががなかったとは言えないだろう。あの場所から見下ろす感激を味わった誰もが、上海サーキットを素晴しい場所だと思ったはずだからだ。
上海サーキットは、まばらな色のシートが並んでいることでも知られる。均一になっていないのは、準備間に合わなかったせいかと思ったら、実は、“人が座っていなくても、観客が入って見える”という隠れた効果を狙ったのではないかと言われている。こうしたフェイクのリカバーはお勧めできないが、いいところを感じて、それ伝えてもらう気遣いは文化や言葉が異なる場合は特に気をつけておきたい、ということだ。
報道陣をチャホヤしろ、という意味ではない。揉み手をする必要はないけれど、どこかで不安な気分にさせると、そこを起点に情報が流れることになることを理解し、うまくコントロールして味方につける工夫を心がけておくと、自分たちの成したことが正しく伝わる、ということだ。
いずれにしてや、新たな試みがスタートした。10年後にどんな成長を見せているから、今から楽しみだ。
[STINGER]山口正己
photo by [STINGER]