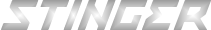世界に目を開け–2回目のドリフト世界戦見物
◆11月4日はお台場のドリフト世界戦、IDCを見物した。インターナショナル・ドリフティング・カップだ。去年、川畑真人が素晴しい走りで初代チャンピオンに輝き、盛り上がりを見せた大会の進化に期待した。
◆大きく進化したのは、コース設定。去年は、選手のレベルが見えない、という主催者の考えから大人しめの、つまりは低速気味なコース設定だったが、今年は、思い切った高速右コーナーから競技が始まるスペクタクルな設定で、満員のスタンドからは何度も歓声と拍手が沸き起こった。
◆残念だったのは、午後になってしとしとと雨が降り続き、熱戦に水を差したことだったが、それでもドリフトの魅力は伝わった。ロシア出身のゲオルギィ・チフチャンが美しい走りで2代目チャンピオンとなり、日本勢、中でも初代チャンピオンの川畑真人がトラブルで敗退してガックリきた。コース上でコクピットを降りた川畑は、場内放送の呼びかけに「悔しい。応援していただいたみなさま、申し訳ありませんでした」と深々と頭を下げた。この“悶々とした悔しさ”を1年間持ち続け、復活を期待したい。
◆ところで、勝敗の行方が、期待外れで残念な気分になるのは、勝負の世界では付き物だが、今回の第2回を見て残念だったのは、その理由だけではなかった。場内のムードが、もう一つ“世界”と言うには貧相だった。
◆雨が降って気分が沈みがちだったことを差し引いても、どこか取り残されたムードが払拭できないままだった。理由はいつくか思い当たる。
観客に広く伝える工夫
◆まず、イベントとしての進行が、リズミカルではなく、どこかもっさりしていた。MCの“ノリ”や、BGMを工夫する必要もありそうだが、全体の流れから、“年に1回”という特別感を感じられなかったのは非常に残念だった。もちろん、選手たちや主催者は、年に一度の緊迫感を感じていたはずだが、“いつものD1”のイメージから脱却できていなかった。
◆例えば、アクシデントの際のレスキューの動きなどは、場馴れを感じさせる手際の良さで見事だったし、NASCARを参考にしたレスキュー・トラックがかっこよかったが、その場馴れが、逆に、“年一度感”をなくして、ムードをまったりさせる要因だったのではないかとも思えた。
◆すでに30年近く前の話しになるが、オールスター・ダートトライアルという年に一度のイベントが行なわれていた。年間500戦といわれたダートラの頂点イベント、まさに“オールスター”だった。
◆当時のダートラは、クラスが5つあったが、スタート順は、後ろに行くほど改造度合いが大きく、つまりは速いマシンだった。クラス毎の出走順も、後ろにいくほど速い。これは、観客が面白く感じる工夫の現れ。後ろに行くほど速いから、タイムが順次短縮され、場内放送がそこに注目して絶叫するので、場内がひとつになりやすかった。そのムードのなかで走る選手のテンションも上がってさらに迫力ある走りが展開した。
◆転倒車両が出た場合のレスキューの動きも、事前に現場の動きがシミュレーションされていて、コントロルー・タワーから競技長が“レスキューA”と指示を出すと、パターンAの動きを予行演習しているオフィシャルが的確に動く。その指令を知らない観客にも、てきぱきとした動きが伝わって、競技のリズムがそこなわれなかった。
◆ダートラもドリフトも、サーキットのレースとは違って、スピード行事と呼ばれるジャンルだが、スピード行事の共通点は、オフィシャルの采配によって競技の面白さが180度変わってしまうところだ。サーキットレースでも、オフィシャルの運営能力は重要だが、それによってレース内容じたいが変化することはあまりない。しかし、スピード行事は、主催者の思考回路が如実に場内のムードに現れる。ダラけた進行は、スタートする選手の緊迫感を阻害して、それが観客に伝わるからだ。
◆例えば、ダートラで転倒した場合、スタート地点で集中して構えているドライバーのテンションが一端リセットされることになるが、リズミカルな運営なら、そのリセットもスムーズに行くが、ダラダラやられるとテンションが下がり、走りがグダグダになりかねない。参加選手のテンションの重要性を、コースサイドのオフィシャルも、場内放送のMCも、知り抜いていることが重要なのは、そういうことだ。IDCも、『慣れ』ではなく、年に1回という認識を新たに、3回目が行なわれることを心から祈りたい。
◆レスキュー・トラックがNASCARを参考にしているのなら、デイトナ500の進め方も参考になるはずだ。一事が万事、観客目線。トライアングルオーバルの理由もそれ、オーバールに沿った観客席の狙いは、“どこからもマシンが向かってくるように見える”。スタート前進行も、スタートでペースカーが3台いるのも、すべて観客にワクワク感を与えるためだ。
本当の世界戦を目指して
◆一方、今回のIDCの参加者は、13カ国からの20人だったが、日本を中心に、ロシア、や東南アジアが大勢を占めていた。スイスから参加したBMW-M2に乗るイヴ・メイエーが2位に食い込んだが、ヨーロッパとアメリカからの参加は、彼一人だけだった。世界を名乗るなら、欧米の選手の参加が是非ともほしい。いまのままでは、世界戦というよりアジアカップの域を出ていない。
◆事前の記者発表の時、川畑真人選手に、昨年のウィナーとしてFIAの表彰式に呼ばれた時のことを改めて説明してもらった。それは、IDCが“世界”を標榜しているイベントであり、そのチャンピオンの“重さ”を、広く知ってほしいと思ったからだ。土屋圭市名誉顧問に、“成り上がりの歴史を改めて振り返ってください”と質問したのも、その思いからだった。
◆FIAの表彰式は、毎年、タキシードにブラックタイのフォーマル・パーティとして行なわれているが、そのクォリティがあまり日本には伝わっていない。そのクォリティの高さを知れば、いかに世界では自動車のポジションが高く、それを使って行なわれるモーターレーシングの位置づけが世間からどう認識されているかが理解できる。日本発祥をひけらかす段階は終わっている。
◆話は飛ぶが、マクラーレンのテクノロジー・センターの落成式に、イギリスの女王陛下が列席された。日本でいえば、レーシングチームの落成式に天皇陛下がお出ましになる、ということだ。要するに、自動車は、そういうポテンシャルを持っている。
◆そのポテンシャルの中でIDCが行なわれている。お山の大将が世界に進出しても、自分たちの楽しみの範疇から抜けだせない限り、IDCに未来を見出すことはできない。逆の言い方をすれば、世界に君臨できるポテンシャルを、日本発祥のドリフトは持っている。そしてその可能性を伸ばすも殺すも、主催者の采配次第。お山の大将が世界の冠をいただいた。次の次元にドリフトが進化するために、何が必要か、ここでじっくり考えて、1年後の“三度目の正直”につなげてほしいと心から思う。
◆ついでに今回感心したのは、優勝したチフチャンのマシンが綺麗だったことだった。カラーリングのセンスではなく、汚れや傷を放っておかない、という思考回路が素晴しい。上手いからぶつけず、だからよりマシンを大切にしているのかもしれないが、“見せる”、もしくは“観てほしい”ことを、外からの目線で捉えているに違いない。これは、チフチャンのドライビングテクニック以上に見習いたい考え方だった。
photo by Tokyo Drift/[STINGER]