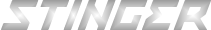もっとも身近なワールドチャンピオン

いちばん好きなフェラーリは、デイトナ、と教えてくれた2013年鈴鹿。
◆ニキ・ラウダが亡くなった。思い出は数限りなくあるけれど、中でもいまでもインパクトが残っているのは、最初に本人を目の当たりにした43年前。

初めてラウダを見た1976年富士スピードウェイの人生初のF1取材パス。
◆出逢いは、1976年10月24日の雨の中で決勝レースが行なわれた富士スピードウェイのF1世界選手権inジャパン。“日本GPという名前じゃなかったんですよ”、という下りだけで一晩語れそうな、日本のモーターレース史上にさん然と輝くレースだ。そのレースで、ラウダを初めて目撃した。
◆1976年8月に、『auto technic』(オートテクニック)という1991年に休刊し、“しばらくお待ちください”と最終号に書いたまま今日になってしまって恐縮至極のモータースポーツ専門誌の編集部員採用試験を受け、翌年4月からの正社員を前に、アルバイトとして初めて取材パスをもらったのがこのレースだった。
◆実家の相模湖から、今は舗装されているけれど、当時は、快適なフラット路面だった須走を下った先から左に折れる抜け道をカウンターステアを当てながらいそいそと、従兄弟の中古車屋から借りたマークⅡのワゴンを飛ばして富士スピードウェイに、まさしくワクワクで到着した。
◆スタンド裏にクルマを停めて、グランドスタンドからピットを見下ろしたら、正面にまさにラウダの真っ赤なフェラーリが停まっているではないか。「あ、ホンモノのフェラーリだ」と当り前のことをつぶやいて、柵につかまった。つかまらないと、頭に血が昇って目眩で倒れそうになったからだ。
◆翌年の第2戦ロングビーチGPを『auto technic』から申請したパスで見物した。これが海外初取材だったが、決勝レースは4月3日で、本来なら4月1日付けで『auto technic』を発行していた㈱山海堂に出社しなければならなかったが、「帰国後の4月7日入社にしてください」と総務部に無茶振りして渋々了承されたというのはここでは関係ないが、そこでラウダの312Tに再会した。ラウダがポールポジションを奪ってマリオ・アンドレッティが優勝したそのロングビーチGPの記事が、『auto technic』に初めて書いたF1のレポートになった。
◆ラウダのライバルはジェイムス・ハント。当時から、優等生のラウダと女ったらしのハント、というイメージがあった。ロングビーチのガレージに供されたロングビーチの体育館の前で、ハントにインタビューした当時売り出し中だった名前が思い出せない金髪で細い女優が、もしかすると夕べハントと一緒だったか、もしくは今晩誘われたからではないかと邪推したくなるように、緊張で小刻みに震えていたのを思い出す。

◆その後、ハントは、1993年に45歳の若さで亡くなる直前までころBBCのコメンテイターとしてF1の現場に来ていたが、ポルトガルGPの帰りにロンドン行きの飛行機で一緒になったことがあった。斜め右前の席に座っていたハントは、機内で配られるワインの小瓶を何本も呑みまくって酩酊状態だったが、着陸の少し前に、当時はスチュワーデスと呼ばれていたキャビンアテンダントに、さらにワインを3本注文し、1本を飲み、残りる2本をポケットに入れて飛行機を降りたのを観て、複雑な気持ちになった。

お気に入りのフェラーリ・デイトナ。2013年鈴鹿のドライバー紹介で、ライコネンがコースを1周した。
◆鈴鹿の日本GPのドライバーズパレードは、オーナーの協力でビンテージカーにF1ドライバーを乗せてコースを巡る。ラウダがその中の1台、黄色いフェラーリ・デイトナを覗き込んでいたので、往年のフェラーリの中で、どれがいちばんのお気に入りかと尋ねたら、かすかにはにかみながら、その黄色いデイトナを指差して“これだよ”と言った。偉大な人の素朴な一面を見た気がしてとても嬉しかった。
◆メルセデスAMG F1チームの非常勤会長となってF1の現場に復帰し、ルイス・ハミルトンのよき理解者として、パドックで膝を詰めて話をするのが、去年までの特に金曜日によく観られる光景だった。ハミルトンとボッタスが激しい闘いを展開している今シーズン、70歳になって、ますますチームにとって重要なポジションでの仕事があった。

ハミルトンの予期相談役だった。
◆享年70歳。いまはただ、安らかな眠りをお祈りします。
合掌。R.I.P.
photo by [STINGER]