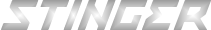桜井淑敏とその未来–②出力1500馬力!? 800m飛んだ破片

桜井淑敏が基盤を創ったホンダの研究所が、ネルソン・ピケとナイジェルマンセルを擁するウィリアムズF1チームに供給したV型6気筒1500㏄のホンダRA168Eエンジン。まさに宝石のような美しさだ。1988年には“セナ/プロ”コンビのマクラーレンにも供給、16戦15勝の金字塔を打ち立てることになる。
1988年F1シーズン、セナとプロストのマクラーレン・ホンダと、ピケとマンセルのウィリアムズ・ホンダ、そしてロータス・ホンダ。この5人を起用する原動力になった桜井さんは、ホンダF1の黄金時代を築く中枢として1986年9月のイタリアGPで初めて“現場”を視察した。
当然、自分たちが作り上げたエンジンには自信があったが、現実は厳しいものだった。公式練習が始まる前日、当時は木曜日に走行時間が設けられていたのだが、意気揚々とモンツァに乗り込んだ桜井さんの第一声は、「着いたときはもうエンジンが壊れていた」だった。
「とんでもないところに来てしまった」ことをいやでも突きつけられ、具体的にショッキングなF1のレベルの高さを知った。絶壁のように立ちはだかる高い壁。しかし、それでも、世界一になる夢は揺るがなかった。
トヨタがF1チャレンジをした時、担当役員の名文句がある。「やっとのことで頂点を究め、そこにチームの旗を立てようとしたら、すでに何本もの旗が立っていた」。F1の山の高さを如実に現する言葉だ。
当時のF1エンジンは、自然吸気は3リッターまで、加給着器付きが1500㏄と規定されていた。“ホンダなら3リッターV12だろう”と多くのファンは思っていたが、ホンダは、市販車でも経験のないターボを選んだ。計画段階で自然吸気の3000㏄V12も選択肢にあったが、重量も図体も大きくなることがネックとなり、最終段階で、3000㏄のV10と1500㏄ターボが残り、結果として1500㏄ターボが選ばれた。将来性を考えると、ターボで行くことが、市販車へのフィードバックを含めて可能性が期待できたからだった。そしてそうしたチャレンジングな姿勢こそ、ホンダがホンダらしい、そして桜井淑敏が桜井淑敏らしいところといえた。
1983年に登場したホンダF1ターボは、1500㏄というリヤタイヤよりも小柄なエンジンから1500馬力を絞り出していた。ホンダが公にしていた通称“公称出力”は650馬力だったが、この数値にも、桜井さんらしい逸話がある。
当時、土師守さんから責任者を引き継ぐことになる桜井さんは、後にフェラーリからマクラーレンを経て、スイスのザウバーに加わり、最終的にスイスにGEO TECというエンジン開発の会社を立げた後藤治さん、そして研究所でエンジンの基本設計を担当していた市田勝巳さんとチームを組んでホンダF1ターボの研究開発を進めていたが、この3人に最高出力を訪ねると、三者三様の答えが返ってきた。
当時のF1エンジンは、“1000馬力は越えている”と言われていたが、当時研究所にあったシャシーダイナモは1300馬力が計測リミットで、正確なパワーは測定できていなかった。そこで、“1300馬力以上と言われていますが”、と問うと、市田さんは、“さぁ、どうなんでしょうね”と答え、後藤さんは“そんなもんじゃないですかね”とニコリとし、桜井さんは、“もうちょっと行ってるかもね”と答えたものだ。異なる性格と思考の三人だからこそ、ホンダのF1エンジンは成功したに違いない。
ちなみに、1500㏄エンジンがいかに強烈だったかを物語る逸話がある。これはホンダのエンジンではないが、ブラバムに積まれていた当時ホンダのライバルだったBMWの直列4気筒エンジンが、モンツァのテストでエンジン・ブローを起こし、壊れたバルブが、エキゾーストパイプからライフルのように撃ち出され、その破片が、ストレースを越えて800m先の観客席に落下しているのが見つかった。テストで観客がいなかったのは不幸中の幸いだったが、げに恐ろしきF1ターボ・エンジンのエネルギーだ。
ここでもう少しそのエンジンの大きさが分かる話がある。ある時市田さんがエンジンを背にして座り、“エンジンの幅が肩幅と一緒でしょ”と笑ってみせたことがある。1500㏄V6ターボは、市田さんの肩幅がピッタリだった。計算ずくで完成した必要最低限の大きさ。テクノロジーの基本がそこに乗る人のサイズから割り出されていることが理解できた。
また、ブースト圧が上がるとノッキングが起きてピストンに穴があいてしまうため、通常の燃料は使えなくなる。そこで燃料に添加剤を混合して着火温度をに下げる工夫をしていたが、特にフェラーリの排気は、近くにいるとメがチカチカする異様な匂いがするものだった。パドックでは、“フェラーリのことだからニンニクを入れているに違いない”、というまことしやかなジョークがささやかれるようになっていく。
(桜井淑敏とその未来③に続く)