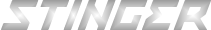暑気払いに、どうぞ 『双頭の夢 HONDA F1 魂のルーツ』(山口正己著/三栄書房)
『双頭の夢 HONDA F1 魂のルーツ』という本を2016年3月に上梓させていただいた。HONDA F1が1964年にデビューし、そこからの5年間の物語だ。
私は、1987年に『GPXpress』という世界初のF1速報誌を創刊したが、もちろんそれは、当時第二期F1時代を闘っていたホンダに触発されたものだった。ネルソン・ピケ、ナイジェル・マンセル、アラン・プロストアイルトン・セナの4巨頭を筆頭に、ホンダ・パワーが炸裂、中嶋悟さんが日本人初のフルタイムF1ドライバーとして世界に打ってて出た年である。
実体験としては、この第二期からになる。1976年日本GPからF1の現場に触れてはいたが、海外のF1の現場は、アメリカが中心だった。この1987年からは、年間二桁のF1現場を踏むことになる。
いずれにしても、1960年代のホンダF1第一期は、モノの本で活躍をうっすらと知っていたのだが、そこでマネージャーとして活躍した中村良夫さんを始め、第一期に関わった方々に当時の様子を伺うたびに、第一期ホンダF1に対する興味が加速していった。
元々、1960年代には、特別な思いがあった。ちょうど多感な高校生だったこともあるが、1960年代は、世界が動いた時だったと思うからだ。ビートルズが世界的に流行り、鈴鹿サーキットや富士スピードウェイか誕生した。
自動巻きの腕時計や、一眼レフカメラが世に出たのもこのころである。戦後20年、世界が驚く復興に、日本が向かい始めていた頃である。そういう時代の流れは、多感な高校生にとってさらにインパクトが強かった。
さて、『双頭の夢 HONDA F1 魂のルーツ』の“双頭”とは、火の玉オヤジである本田技研の創始者であり、創業社長である本田宗一郎さんと、その右腕としてホンダF1を推進した中村良夫さんのことである。
二人は、相反するスタンスでF1GPに夢を持っていた。“感覚派”と“理論派”という観方もできるし、“夢想派”と“現実派”とも対比できる。けれど、反対側を向きながら、信ずるところに突き動かされていた、という意味で、まったくふたりは同じようにそれぞれの「夢」を目指すという点で、同じだったとも言える。
第一期ホンダF1最後の年、徹底的に軽量化したV12を搭載するコンベンショナルなRA301で、中村良夫さんとジョン・サーティースはタイトルを狙っていた。タイトルとは世界チャンピオンのことだ。荒唐無稽に見えるが、中村さんとサーティースは周到に計画し、“世界チャンピオン”を現実の目標として定めていた。
結果的に、中村/サーティース主導のマシンは、モンツァでポールポジョンを奪った以外、第6戦フランスGPの2位と、第11戦アメリカGPの3位の2回の表彰台除くと、さしたる成績を残せなかった。それは、中村さんとジョン・サーティースがタイトルを狙って開発したRA301の開発活動の隣で、本田宗一郎さんが空冷V8のRA302を無理やり推進したからだった。
予算も開発も真っ二つに分割された。予算は半減し、戦力的にも一極集中にならなかった。ホンダ内に2チームが存在し、中村良夫さんの計画が予定とおり進まなかったのだ。
翻って、ホンダがF1GPに挑戦を開始した1960年という時代を振り返ると、第二次世界大戦とか太平洋戦争と呼ばれることになる“大東亜戦争”から20年が経過した日本は、敗戦の痛手から立ち直り、経済復興の鐘が鳴り響いていた頃である。
マッカーサー率いるGHQは、日本を骨抜きにするべく、例えば航空機の開発を禁止していた。しかし、そのおかげで、日本の自動車産業が華々しく発展することになった。
中村良夫さんだけでなく、スバル360を創った百瀬晋六さん、プリンスR380の生みの親である中川良一さんなど、その後、日本の自動車産業に名を残す多くのエンジニアは、航空畑の出身だった。もし、GHQが、航空産業の開発を禁止していなければ、彼らは当然、航空宇宙の分野に邁進したはずだった。
しかし、“最先端”である飛行機を奪われた彼らは、ある種仕方なしにクルマや鉄道に従事することになる。一方、航空産業の開発に制約がなかったアメリカは、トップエンジニアの多くが航空産業や宇宙開発に進んだ。その結果、自動車産業は、若干見劣りするエンジニアの手に委ねられることになった。その後のアメリカの自動車が、下り坂を歩んだのも、当然といえば当然だったのだ。
そんな潮流の中で、ホンダはF1に参戦した。
『双頭の夢 HONDA F1 魂のルーツ』
発行:三栄書房