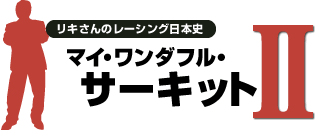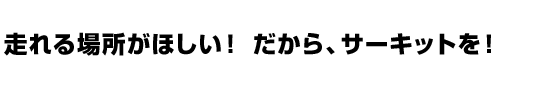(1)海外で本格的なレースを走って、見えてきたもの
――前回は、ホンダが「鈴鹿」へ来たのはなぜかというお話で、その理由は、何よりも《人》なんだ!という、いかにも宗一郎さんらしいエピソードでした。そうしたホンダ側の“鈴鹿市への信頼”から、やはりサーキットもここにということになったのでしょうか?
「まあ結果だけから見ると、そういうことになるんだけど。でも、ハナシはそんなに単純なものじゃなかった」
リキさんは語りはじめた。
「この頃、つまり50年代の末から60年代の初頭にかけて、ホンダは、やりたいこと、やらねばならないことが、大きく二つあった。ひとつは、爆発的なヒットになりかけていたスーパーカブという製品を、当時のメーカーでは、できなかったレベルと規模で量産すること。これが市販車分野でのホンダの重要事項で、そして、もうひとつは──」
――あ、海外レースですね!
「そう、ホンダが本格的に、海外でレースを始めた注1のが1959年です。これがマン島TTレースへの挑戦で、でも、この参戦にこぎつけるまでには、ホンダとしても、かなりの時間が必要だった。『あの劇的な宣言』からも、すでに五年の月日が経っていましたからね」
1954年3月という時点で、本田宗一郎は、「私の宿意と決心を申し上げ、このTTレースに出場、優勝するため、精魂を傾けて創意工夫することをここに宣言致します」という言葉で結ばれる「宣言書」を、社内と、そして全国のホンダ販売店に配っていた。
このときは、会社倒産の危機に瀕していた当時の本田技研とその関係者を鼓舞するためという要素もあったといわれる参戦宣言だったが、しかしその後に、海外レースに挑戦するための布石は着々と打たれて行った。リキさんは指摘する。
「本田さんは、この宣言をしてから欧州視察に出かけ、TTコースの下見もして帰国後、直ぐに荒川の河川敷にテストコースを造るんです」
「1954年のことです。二輪も四輪も、当時のメーカーには本格的なテストコースはなく、普通の道を走り回って、性能試験をしていたのです。ニューモデルなどは、人目につかない所や夜中がコース代わりなのです。ただ、ホンダコースも、直線が2キロだけで、まっすぐ行ったら、すぐにUターンして戻らなければならない、いまの基準ではテストコースとはいえないものかもしれません。ただ、このコースで重要なのは路面が舗装だったということ」
――なるほど、国内のレースは、ホンダのテストコースができた後に始まった《アサマ》は特殊なダートコースだが、いち早く舗装コースの必要性を見越していた?
「そうゆうことですね。何事も、しっかりしたテストを行なうには、まず一番に、それなりの場所、設備が必要という風土がすでにあった」
「場所や設備だけでなく、テストの方法も適材適所といいますか、市販前のスーパーカブなどの高速走行テストでは、後にマン島に出るようなレーサー試験室所属のライダーが担当して、実車テストチームとは異なるチェックをするのです」
――そういう流れがあったから、初挑戦のマン島でも、ちゃんと完走して、チーム賞も獲得し、最上位の入賞は6位だったという成果を上げた?
「1959年の初参戦では、まあ、傍目から見ればそうだったかもしれない。でも、このときのホンダがワールドレベルではなかったことは、本田宗一郎さん、河島喜好さんをはじめとする当事者たちが一番よく知っていた」
「これは、ぼくの本の『百年のマン島』にも書いたことなんだけど、この初参戦について、『エンジンの馬力は(略)他と較べて極端に悪いとは思わなかったですが、操縦性とブレーキの性能差は歴然としていた』と語っています」
――うーん、テストコースが直線で、エンジンの加速テストだけはできたけど……というように考えると、ちょっと悲しいというか、でも仕方がなかったというか?
「そうですね。こうした海外経験から、長い距離を走ってみて、はじめてクルマの不具合もわかる。こういうことがわかって、そのためにはもっとと高度なテスト場所が不可欠。それにはやはり、サーキットだ。こういう風潮がホンダのなかで高まっていくわけです」
――といっても、当時の日本には?
「うん、サーキットなんて、カゲもカタチも、そのような呼び名もない(笑)。さらにいえば高速道路も、東名も名神もなかったわけで、二輪や四輪が高速で連続走行するというシチュエーション自体が日本になかった」
「当時の通商産業省も、ロードコース建設に向けて、調査のための予算をつけたりしていたんだけど、本田(宗一郎)さんにしてみれば、そんなちっぽけな予算で何ができる? そんなもの、待ってられるかっ!……(笑)」
――じゃあ、俺がやる!……と?
「そうなるわけです。ホンダ内部に、レース場建設委員会というものがつくられたのが1960年の秋でした」
(2)「水田を潰してはいけないっ!
こうして発足した「レース場建設委員会」の長に就任したのは藤沢武夫だった。とはいえ、集められたスタッフにも、「サーキット」というものがどういうものか、まったく見えていなかった。リキさんは、笑いながら語る。
「外国帰りの社員から聞き取って、コースの長さは? まあ6キロ(km)くらいかな?と、そんな風に始まったらしい(笑)」

最初は、こんな形から鈴鹿サーキットの“デザイン”は始まった。
ただ、コース長が仮に6キロだとすると、それに付帯する設備も含めて、用地には30万坪が必要だというデータは、スタッフから藤沢に上がってきた。これに藤沢が応じて、「じゃあ、どこにつくるか?」ということになり、それなら、レース場をマネージメントする会社を設立しようという段階になる。1961年の1月、株式会社モータースポーツ・ランドが設立された。
「この会社の初代社長になったのが、三菱銀行の京橋支店長だった鈴木時太さん。これは藤沢さんが、ホンダの倒産危機のときに融資のOKを出してくれた人であり、ホンダの“いま”があるのはひとえに鈴木さんのおかげだという思いから。ここでも、何というか、やっぱり判断基準というのは《人》になっている。工場が鈴鹿に決まった経緯といい、当時のホンダの行動様式がよくわかる思想ですね」
こうして新会社もできたが、当初、本田宗一郎の頭にあったのは「本格サーキットをつくる」ということだけであり、その場所は未定で、鈴鹿に造る考えもなかった。そして「30万坪」という数値がひとり歩きをし始め、すでに稼働の鈴鹿製作所(21万坪)よりも広い土地をどうするのかの土地探しが始まった。
「レースの新会社は、ホンダよりもデカくなるなんていうデマも飛んでね(笑)。その会社が土地探しに動き出したので、ある土地では、社員が乗ってきたクルマのHマークから、ここにホンダが来る!ということで土地の買い占めが行なわれたりした。まあ、いいかえれば、この頃、ホンダの存在はそのくらいに大きくなっていたということなんだけど」
ちなみに、サーキット建設の土地探しを数えれば、水戸の射爆場跡、浜松の三方原、浜名湖北部・佐鳴瑚周辺、滋賀県土山、鈴鹿周辺では、隣の亀山などがあった。
ただし、サーキットを建設するにはどこも何らかの欠点があって、土地探しは難航していた。そういう状況のなか、昔の軍事施設の関係なのだろう、航空測量図や土地の高低図などが豊富にあった鈴鹿市が、検討地域として浮上してきた。
そして、現在の鈴鹿サーキットの北東部分を中心とする平坦な土地に、スタッフがコースを設定し、図面にしてみた。その段階ではそこは水田であり、ゆえに平らで、コースの全体も見通せる絶好の場所だ。
しかし、その図面を見た本田宗一郎は、これも“宗一郎伝説”のひとつになっている、有名な“カミナリ”を落とすのである。
「米のできる水田を潰したら、目が潰れる! お米を粗末に扱うな!」「レース場というのは、音が出るんだ。音が出てもいいような、米もできないような荒れ地を利用するとか、そういう考えが出せねーのか!」(『サーキット燦々』より)
「こうして、鈴鹿の丘陵地帯を中心に土地を確保(買収)していくのだが、誰もが賛成してくれるものではない。その場合は、コースのデザインを変更するとかね。例えば予定していた土地が買収できずスプーンのようなカーブになってしまった個所もある。このような苦肉の策、試行錯誤の結果こういう形になった……といった部分が『鈴鹿』にはけっこうあるんだよ(笑)」
リキさんはこう言って笑ったが、しかし、そんな“素人ワザ”から始まったサーキットが、結果として、世界でも有数の、また、ドライバーやライダーによって、こよなく愛されるタイプのサーキットになっていくのは、歴史のおもしろさというしかない。
第四回・了 (取材・文:家村浩明)
注1:ホンダは、1954年に、「サンパウロ市政400年記念レース」に参戦。これがホンダの海外初レースだった。