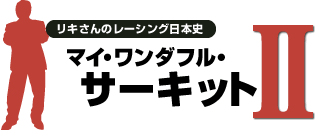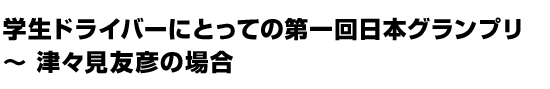(1)鈴鹿サーキットでのレース、野宿したぼくは、こんな経験もした!

40年近くの時空を飛び越えて思い出を語る津々見友彦さん(左)とリキさん。
――今日は、“噂の”津々見友彦さんに来訪していただきました!
リキ「いやあ、ありがとうございます。前回、最後に津々見さんのことで盛り上がっちゃって……」
津々見「え、そうなんですか? なんか、コワいなあ!(笑)」
リキ「なかなかね、いろんなところで遭遇はしていても、すれ違いみたいな格好になっちゃって、ゆっくりお話を伺う機会って、あまりなかったですよね」
津々見「こちらこそ、今日は、お話しできることを楽しみにしてきました。よろしくお願い致します」
――早速ですが、津々見さんにとっても、1963年の第一回日本グランプリにやってきたロータスなどのプロトタイプ・スポーツカーって、やっぱり衝撃でしたか?
津々見「もちろんです。こんなクルマがあるんだ、と! ぼくら、あのペタンコなヤツは“ワラジ”って勝手に言ってましたけど(笑)」
リキ「一方でスバルは、テントウムシだけど、あれは“便所のスリッパ”と呼ばれていた(笑)」
――そういう“衝撃の世界”に、この年から踏み込むようになられた津々見さんですが?
津々見「ぼくは高校を出たら、航空機のパイロットになりたかった。でも、自衛隊って給料安いでしょ。もっとも、いま考えると、ああいう組織って宿とメシは全部支給されるわけだから、そんなに安月給だということでもなかったけど。でも、それより何より、ほら、勉強に自信ないから(笑)。だから、パイロットの夢は早くに諦めたんですね」
――二輪でのレースは?
津々見「バイクは中学の頃から乗ってました。当時は、14歳から原付(125cc)には乗れたので。高校の時には自分たちでバイクのクラブを作って、ツーリングなどによく行ってました。浅間のレースも見に行きましたよ。でも、もちろんレースの経験はありません」
――では、四輪レースとの関わりは?
津々見「1962年のモーターショーで『スポーツカー』という本が売られていて、そこにいた式場(壮吉)さんや杉江さん(のちの徳大寺有恒氏)たちお三人と知り合いになる機会がありました。彼らは、のちに“レーシング・メイト”を設立することになりますが」
「そこからですね、ぼくと四輪の世界との関わりが始まったのは──。彼らはほんと、無類のスポーツカー、モータースポーツ好きで! そして、彼らの主なニュースソースは英国の雑誌でした。ぼくは、これらの方々と英誌を通じて、ファンジオとかスターリング・モス、あるいはフィル・ヒルといったドライバーの名を知り、そして、クルマを使ったこういう『スポーツ』があるんだということを知ったんです」
――なるほど、そこからレースに?
津々見「ええ。“オレがやるのはこれだ!”と思った。そして、その半年後に、鈴鹿サーキットで“日本・グランプリ”が行なわれるというのを知って、これは何としても出るぞ!と──」
――四輪車はお持ちだった?
津々見「いえ、そんなもの、ありません。だから父に『クルマ買ってよ』と言ったんだけど、クルマって高いでしょ(笑)。式場さんはポルシェを持ってた。これは、すごく高い。じゃ、それにちょっと似たヤツでワーゲンは? いや、まだ高い(笑)」
「そんなときに、バイクで通りかかった国道246号/山手通りの交叉するところのシェルのガソリンスタンドに“ポルシェ・チック”“ワーゲン・チック”な(笑)クルマを見つけた。それがDKWだった」
リキ「それは、いくらで売られてましたか?」
津々見「39万円でしたね」
リキ「ぼくが当時狙っていたパブリカ・スポーツも、新車で、ちょうどそんな値段。この頃の国産の“入門車”というか、ベーシックなクルマのプライスが、40万円前後というものでしたね」
津々見「ただ、このDKWは、実はエンジンが壊れてましてね。でも、ものを知らないから、壊れてるかどうかわからなかったけど(笑)。エンジンをかけると、ボロボロッといいながら回って、吹かすと“ガーッ”とすごい音がした。でも、クルマはこういうものだと思っていたので(笑)」
「そして、レース参加のための拠点を設けようと、大阪へ行きました。ちょうどできたばかりの箱根新道で、DKWで箱根を越えようとしたら、クルマが動かなくなっちゃって(笑)。料金所でエンジンを降ろしてバラしましたら、エンジンのローラー・ベアリングが焼き付いてまして……。もちろん、ぼくには直せず、友だちにSOSして助けに来てもらい、このときはいったん東京に引き返しました。」
――それは大変なトラブルですね。
津々見「ええ。あとで、田口さんという“DKWの神様”に教えていただいて、立川町のポンコツ屋でエンジンとミッションを仕入れて、載せ換えました。後日、そうやって直したDKWで、何とか大阪まで行けて……。大阪では、街でたまたまDKWとすれ違って、互いに、急ブレーキかけて止まってね(笑)。そのまま、そのオーナーの、山本さんとおっしゃるホウロウのバスタブ(風呂)の製作工場を経営してらした方の、その工場の片隅を“ワークショップ”みたいに使わせてもらって……。そういう感じで、もう、人に助けられてばっかり(笑)」
リキ「そのDKWは、それなりに古かった?」
津々見「ええ、ぼくが買ったそのDKWは、どうも“タク上がり”だったみたいです。……あ、“タクシー上がり”って、いまの人には、まったくわからないでしょうけど」
――うーん、僭越ながら(笑)ちょっと説明させていただくと、当時は、タクシーで営業用として使われた車両を、お役ご免としたあとで、一般に向けて中古車として販売することが稀ではなかった。これを称して、“タク上げ”“タク上がり”と言っていた?
リキ「ウン、だいたい合ってます(笑)。そもそも、まだクルマの総数自体が少なかったから、そうやって、可動するものは使い尽くした……という時代だったかな」
津々見「鈴鹿サーキットに行ったときは、たとえば鈴鹿峠の、トラック・ドライバー向けの食堂でメシを食って、そこでクルマも駐められたので仮眠したり。大阪の山本さんの工場でも、寝袋で寝ていたから、そういうのは、まったく苦じゃなかった」
――《鈴鹿》での練習代というのは?
津々見「だから、参加者ならタダで走れるとか、そういうときだけを狙って、走りに行った(笑)。そうそう、練習で、フィアット1500Sに乗っていた宇田川さんと知り合いになり、ディーラーの日本自動車を紹介してもらったり。そこはDKWも扱っていたので、そこから、イグニッションコイルを回してもらって」
「そして、ついでにクランクシャフトも交換したら、走っていて、クルマが“ザーッ”といわず、急に静かになった。初めて、エンジンが“ヒョーン!”と回るようになって……。それまでは、エンジンは、ゴロゴロ、ザーッと回るもんだと思ってた(笑)」
リキ「当時、津々見さんはおいくつでした?」
津々見「ぼくはこの年、21歳でした。だからね、野宿とか、そういう意識もなかったんですよ。自分の家じゃないところで寝るんだから、こういうの(寝袋)は当たり前だと思ってたし(笑)」
「そういえば、野宿のおかげで、こんなこともあったんですよ。サーキットのそばで野宿していたら、夜中に、コースからエンジン音が聞こえた。クォーン!という、かなりイイ音。何かのテスト中? 何だろうって見物に──夜中ですけどね(笑)、音の聞こえる方へ行ってみたら、ホンダの『S360』の走行テストが行なわれていたんです」
――え? まだ発売前ですよね。
津々見「……で、ぼくはそのまま、図々しく(笑)パドックまで入って行っちゃった。テストしてたホンダの人たちは驚いたでしょうね、夜中のパドックに、いきなり人が現われたんだから(笑)」
「でもねえ、そこで、すごいことがあったのよ! そのうち、テストスタッフのチーフみたいな方に、ぼくが『横に乗せていただけませんか』ってお願いしたら、何と『いいだろう』と、ぼくをテスト車の助手席に乗せてくれた」
「まだ、市販前のモデルですよ。テスト車ですからね、社外秘だろうし、普通はあり得ないことのはず。でも、“こんな時間に、熱心な坊やがいるもんだな”とか、そんなふうに思ってくれたのかしら? ともかくぼくは、テスト中の『S360』に、それも何周にも渡って、このとき乗ることができました」
――何か、夢の中のことのようなお話しですね?(笑)
津々見「そうでしょう! でも、このことを“公にする”のは、実は、今日が初めてです。というのは、社外の人間(ぼく)を、開発中のクルマに乗せた……なんていうのは、ホンダの会社員としては、やっぱりマズいんじゃないかと、ぼくなりに思ってたので。だから、ぼくがどこかで、こんなことを書いたり喋ったりしたら、それによって、このときの“チーフの方”にご迷惑がかかるようなことがあってはならない。それで、この“夜中のテスト車同乗事件”というのは、ぼくの中でこれまで、ずっとヒミツにして来ました」
――でも、もう時効かもしれませんね?
津々見「そうですよね、“この方”にしても、もう会社を退いておられるだろうし。もし何かの機会があったら、このときのことのお礼を申し上げたいとずっと思っていて、でも、誰にも言えなかったんです」
――これもまた、野宿のおかげ?(笑)
津々見「そうそう!(笑)こうやって、いろんな人に助けられて、また、いろいろ教えていただいてね。何とか、レースの日になるわけですよ」
(2)サーキットはコワかった! 二度とレースは走るまいと思った……
――津々見さんが出場されたのは、700~1000ccのツーリングカー・クラスですよね。
津々見「そうですね。ぼくが出たクラスは、相手が日野ワークスのコンテッサ。そして、それに乗るのは、あの“105マイル・クラブ”のドライバーということで、けっこうコワかったです(笑)。……あの、どうもぼくが先輩方にとっては、ちょっと目障りだったらしいのよね」
――それは、津々見さんが速かったからでは?
津々見「速くはなかったけど、経験がない割りには、そこそこ“走れた”のかなあ、いま思うと。でも、やはりクルマ(DKW)がよかったからだと思いますよ」
――練習走行で速い若僧がいる、ナマイキじゃねーか、と?(笑)
津々見「“ちょっとシメた方がいいんじゃないか”となったらしくて(笑)。それで、脅されそうになったところを、“105マイル・クラブ”のボスの塩沢さんや、同じDKWでエントリーしていた井口(のぼる)さんが取りなしてくださったようで……。『あいつは学生だぜ、そんなこと、やめとけ』と」
「井口さんには、ほんと、お世話になりましたね。《鈴鹿》の走り方がわからないときでも、『ボーヤ、引っ張ってやるから、ついて来い』と言って、井口さんがトロトロとヘアピンまで、ぼくをずっと引っ張ってくれて……。ヘアピンまで来たら、バイバイ!と手を振ってね。一瞬にして、井口さんは見えなくなっちゃいましたけど(笑)」
リキ「でも、本番でも、いいレースをされてましたよね?」
津々見「実際のレースのときでも、コワくてねえ……。いや、誰かに脅かされたとか、そういうんじゃないですけど(笑)。もう、スタート前がとても厭で、コワかったなあ! グリッドに就くでしょ、そうすると、ものすごく不安になって……。“やだー! 誰か、代わってくれー!”(笑)そんな様子が、離れたところからでも見えてたんでしょうかね。井口さんのヘルパーだった折懸さんが、ぼくのところまで、わざわざドリンクを持ってきて下さって……あれは嬉しかったなあ!」
「レースの終盤でも、コンテッサの山西選手にヘアピンで追いついたんですけど、それがまた、コワくて……(笑)。ヘアピンで、ぼくはアウトに行って、そしてスプーン・カーブを抜けて、そしてストレートを二台で並んで走って……」

山西選手との好バトル。後方のDKWに乗る津々見さんは、「もう怖くてレースをやめようと思った」が、その考えはすぐに撤回された。
「でも、そんな中でも、何とか山西選手の顔を横から見たら、彼も、けっこう緊張した顔をしてるの。それがわかったから、そうか、コワがってるのはぼくだけじゃないんだ!と思って(笑)」
――すごいなあ、初レースとは思えない!
津々見「そして、次は高速の左コーナーです。ぼくは、隣のコンテッサのボンネットだけを見てた。横目で見ながら、“あ、いま沈んだ!”という瞬間を待ってた」
――おお!
津々見「ボンネットが“沈んだ”ということは、つまり、そこでブレーキングしたということ。それまでは、絶対に(ブレーキを)踏まないで、ガマンしよう。“沈んで”から、ぼくはブレーキングするんだ、と」
「でも、そのあとのコーナーが、またコワくてね(笑)。だって、僕はアウト側で、二台が並んでコーナリングする格好でしょ。何かあったら、アウト側に弾かれちゃうかもしれないし。でも、このときの山西選手がとてもフェアなドライビングをしてくれて、ちゃんと、ぼくのクルマが走るラインが一台分開けてあった」
――ツーリングカー/700~1000ccのクラスは、5位:津々見友彦、6位:山西喜三夫というリザルトですね。その差が「0.1秒」で?
「でもねえ、レースって、こんなにコワいのかと思って。そのあと三ヵ月くらい、ずっとコワかったです。……で、思ってました、もう、こんなことはやめようと(笑)」
――コワいコワいとおっしゃりながら、レーサーとして、やるべきことは人並み以上におやりになってたような?(笑)
津々見「ぼく、日本で一番臆病なレーシング・ドライバーなので(笑)」
リキ「でも、アマチュアであのレースに参加するというのは、パーツの問題ひとつ取っても、大変だったでしょう?」
津々見「そういえば、タイヤで、おかしい話がありましてね。ダンロップのタイヤ・サービスに行き、“ぼくにも、タイヤをサプライして”と頼みに行くんだけど、いつ行っても、“ないよ”のひと言で冷たくあしらわれた。お前みたいなアマチュアの学生ドライバーに渡すタイヤはないという意味かと思っていたら、そうじゃなかったんですね。意地悪されていたわけじゃなく(笑)、ぼくのDKWのホイールが当時の国産車より大径だったので“そのホイールに付くタイヤはないよ”ということだったの」
「でも、ある日、“ほら、これだよ!”とタイヤをいただきました。結果的にも、それを使ってレースも走るんですが。でも、あとでわかったことですけど、それは実は、トラック用のタイヤだった(笑)」
リキ「当時、レース用タイヤとして一番いいのはダンロップだと言われていましたよね。でも、スバル・ワークスはブリヂストンとの契約があったので、ダンロップは使えなかった。ワークス契約という立場のゆえに不自由なこともあったのです(笑)」
――“タク上がり”のポンコツ輸入車で、野宿をしてレースに挑み、トラック用タイヤで鈴鹿サーキットでの初レースを5位でフィニッシュ! 60年代のロマンがいっぱいというようなお話しですね。今日は、どうもありがとうございました。
第二十九回・了 (取材・文:家村浩明)