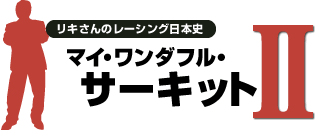(1)直線をどう速く走るかを追求した“ギリギリ・セッティング”で!
――『第二回日本グランプリ』での優勝、おめでとうございます。そして、レース終盤からチェッカーに至るドライバーの心象、視界の中にライバルが一人もいない情景など、大変興味深いものでした!
「ぼくはレースを始めたころ、ローカルレースで一度だけ独走したことがあったけど。でも、いやあ、“一番”を走るというのはむずかしいもので(笑)」
――スタートがラクではないと思われるギヤ比で、そして繊細なクラッチワークで、スタートから先頭に立って……。
「まあスタートは、けっこう上手く行きましたね。要するに、このレースを“成功させる”には、どういう手段があるか。それを考えた場合の、最も確実なのはこれだろうという策がアレだったわけです。もちろん、スタートを一発ミスればアウトになるというリスクはありましたが、そのリスクよりも(やれる!という)自信の方が勝っていたのでしょう」
――そして、コーナリング性能を犠牲にしてもストレートのスピードにこだわったセッティングで、あの《鈴鹿》を攻め切った!
「いや、ほんとに(コーナリング性能を)犠牲にしていたら、あそこ(鈴鹿)は走れないですよ(笑)。あくまでも、コーナリングにさほどの支障がなく、かつ直線走行で有利な足回りのセッティングはどういうものか。これを探したのです。そのため、限界を極めるというようなコーナーでの走りはできませんでしたが。でも、いくらコーナーを速く走っても、《鈴鹿》のコースを見ればわかるように、直線の距離の方が長いのです」
「ただ、一つ一つのコーナー(脱出の)速度が直線スピードに影響するのは事実です。ぼくの(セッティングの)場合、S字コーナーのように、右に左にとクルマの向きを瞬時に変えなくてはならない箇所はフラツキが大きいので、苦手というか危なかった。ですから、そこではクルマをダマしながらの走法でした」
「一方、1コーナーやスプーン、最終の250Rなどの単独コーナーでは、いったんクルマの進路をバチッと決めてしまえば、ステアリングの小刻みな修正で問題なく走れる。コーナリングを犠牲に……といっても、フワフワの足とか、そういうものではなかったですから。もっとも、もし、そんなセッティングだったら直線だって走れませんが(笑)」
――最終コーナーは?
「そうですね、一番スピードが出るコーナーで、そして、あんな小さな車体で、タイヤだって10インチでしょ。それで、150キロくらいの速度で曲がって、直線では160キロ近くになるように持っていくのですが、怖いというか、突然何が起こるかわからないという無気味さはありました。でも、クルマの物理的な限界性能は掴んでいますから、その範囲であれば、ドライバーの操作次第でどうにでもコントロールできます」
「ただ、あのコーナーは突如として風が吹くことがある。それは伊勢湾からの風で、真正面からか、左からか、あるいは右からか。そういう予測できない方向からの風です。それが向かい風や左からだといいのですが、S字の方、つまり右から吹かれますと、クルマはアッという間に、コースアウトしそうなくらいに寄せられてしまいます。これは怖いですよ! 二輪のレースでは、これ(右からの風)で吹き飛ばされてコースアウトという事故が結構ありました。死亡事故までね」
「空気抵抗については、高速になると車体下に流れ込む空気でクルマが浮き上がる……なんて、まだ知られていなかった時代です。『ダウンフォース』なんて、このあと、数年後に出て来た理論ですからね。ぼくのクルマなんか(走りながら)浮きっぱなしでした(笑)。将来、エアカーのレースでもあればコーチできるかな?(笑)」

表彰台で、チームメイトの小関典之、ライバルのスズキ・ワークスの望月修を従え、達成感あふれる笑顔のリキさん。
――それらのすべてを乗り越えての勝利!
「ぼくがいろいろと良かれと思うことを提案して、ぼくなりのセッティングにして、結果(勝利)も出た。これは事実です。でも、それができたというのは、そもそも市販車として優れていた『スバル』という“母体”があった故です。ベース車が貧弱だったら、何をやってもダメですから」
――リキさんのキャリアとスピリットを受け入れるキャパシティが『スバル360』にはあった?
「そうです。いいクルマがあって、それに、富士重・技術陣のチューンが施されて、すでにかなりのレベルになっているマシンがあった。それに“乗っかった”かたちで、ぼくが自分なりのアイデアを加えた」
「ただ、このときのクルマとチューンは、厳密には、レギュレーションの規定外というか、規則の想定以上のことをしてます。まあ、内規違反というか。でも情状酌量の範囲だな、免許証の不携帯くらいか(笑)」
――どのくらいまで“やってもいい”のか。そういうグレーゾーンを含めてのコンセンサスも手探りの時期?
「まあ“グレーゾーン”は、どこのメーカーにもありましたからね。何といっても、会社のメンツがあって、そして、社運を賭けてのGPでしたので。ドライバーの立場からすれば、どんなスピードでも乗りこなして見せるから“もっと速いマシンにしろ!”ですよ。スピードや馬力はいくらでも欲しがる。これは、ドライバーという特殊な人種の性(さが)ですね」
「そして、技術者としても、ドライバーが“震える”ような──素晴らしいマシンへの震えか、速すぎての恐怖の震えか(笑)、そのへんはともかく、エンジニアとしても、いいモノをつくりたいと思うのは当然です。ただ、プライオリティというのかな、まず第一に“壊れないで”というのが(技術陣には)あった。その前提のもとで目標を達成するというのが、彼らの務めなのです」
「このあたりのドライバーとエンジニア相互の満足というか、そういう妥協、サジ加減ですね。これは二輪レースであれば、かなり上手く、互いに理解し合えるレベルにまで、当時は達していました。でも四輪レースでは、そのへんの“着地点”など考えもしないままに、いきなり《鈴鹿》を走りだすことになった。まあ、こういう状態で、ドライバーと技術者の気持ちや判断が食い違っていたのは仕方のないことだったでしょう」
――歴史を見るに『if』はあまり意味がありませんが、もし、チームの規格通りのクルマで、リキさんがこのGPに出ていたら?
「もともと、ぼくはそんなに素直な人間じゃないので(笑)、その状態で走ることは絶対にない。でも、そういう『if』でしたら、馬力の大きい小関のクルマの前どころか、ぼくは小関の“後衛”すらできなかったでしょう。そして、片山や望月に追い回され、エンジンをブン回すことを強いられる小関が結局は潰れて、そして共倒れ。そんなケースだったと想定できます」
(2)1963~1964年時点での四輪レースと“二輪世界”
――リキさんがこのレースで、ご自身のクルマに盛り込んだ種々の対策や戦略は、二輪レースで用いられていたものが多かったと思いますが?
「繰り返しになりますけど、1963年という時点ですでに、日本の二輪のレースは豊富なレース経験を持っていた。また、ワークス仕様のマシンにしても、それを乗り手、つまりライダーの好みやクセに合わせて調整するのは、実戦ではまったく普通のことでありました」
――そうか、二輪レースで云々というよりも?
「ウン、あまり、車輪の数に囚われない方がいい(笑)。要するに、レースをどう闘うかということの歴史の差です。キルスイッチを用いて生ガスをシリンダーに吸わせるという“冷却”方式にしても、2サイクルのエンジンでレースをしていけば、二輪であれ四輪であれ、必然的に生まれるアイデアなので」
「日本の本格的な四輪レースは、このGPで二回目です。『第二回日本グランプリ』の前には、第一回があっただけ。この二回目で、初めて、各メーカーが“大激突”した。そのときに、クルマを速く走らせられる経験者を捜すと、多くの場合、それが二輪レースを経験した者であった」
――この時期、“レースを知る者”は二輪の世界に?
「ええ。でも、それは半分しか正しくありません。もうひとつ重要な側面があって、それは、ぼくらがオートバイでチョロチョロ走っていた少年期(1950年代の後半)に、すでに外国製スポーツカーなどの“速い自動車”に乗っている人たちはいたということ。そして、そういう中に、二輪(ライダー)にはない感覚を持っているドライバーも少なからず存在した。ですから、クルマを速く走らせるには二輪の経験が不可欠だったとは、簡単には言い切れません」
――ははあ!
「でも、二輪(レース)関係者とそうでない人たちとの、実戦における経験の差というのは、スバルだけでなく、他のワークスでもありました。プリンスで出場した生沢(徹)君のように、勝手に、自分流のレース運びに変えて走ったらガンガン速くなったという例もあったし」
――その“レース運び”とは?
「生沢君はプリンスでの二度目のレースですが、そんなに注目されたドライバーではありませんでした。ワークスとすれば、社員ドライバーもいれば、二輪の世界GP経験者・砂子義一もいる。そういう、第一回GPの時とは比べようもない人員を抱えたチームで、生沢君は、その他のうちの一人というような存在。チームではおそらく、彼は中堅グループであると見ていたでしょう」
「レースでの生沢君は、アクセルを中途半端に開けることしかできない位置にいたため、エンジンがくすぶり始めた。これは、思いっきりエンジンを吹かしてやらないと調子が出ない。そう感じて、そこから彼は、自分なりの走りに徹した。それが効を成して上位に進出してきたのです。しかし、ピットからは“抑えろ、抑えろ”のサインばかりが出る。それを無視して走った結果が、1500ccクラスでの優勝でした。チームはエンジンが壊れるのを心配したのでしょうが、クルマの調子を一番よく知っているのは乗り手ですから」
――おお!
「マシンのことは、ドライバーが最もよくわかっているのです。しかし、どうも技術者は、ドライバーを信用していない(笑)」
――それがちょっとフシギで(笑)。メーカーの技術者にとって少なくともこの時期は、レースは未知の領域であったわけですよね。それなら、レースでの先達諸氏に、知らないなら聞けばよかったのでは?
「プライドの高い技術者が、そんなことしませんよ(笑)、とくに四輪メーカーはね。彼らからすれば、オートバイの技術なんて“ナンボのもんじゃ”でしょう。世界GPでの活躍を薄々は知ってはいても、“二輪だからできる、四輪じゃそれはむずかしい”てな調子です。とにかく、素直じゃないんだな!(笑)」
――だから、リキさんの進言も?
「ええ。ぼくなんかが(チームに)拙い提案をしても、“うーん、二輪ならいいだろうけど、四輪ではねえ”と。もう、疑心暗鬼の塊で……。冒険したがらないんだね、四輪は。それがレース草創期のメーカーの状況でした」
「この年までは、クルマ(マシン)としては、市販車と同じカタチをした“特別車”をつくる。そういうことをやっていた。それが1966年の『第三回GP』になると、各メーカーの技術力を活かして、もっとレースに特化したクルマ、プロトタイプのレーシング・マシンをつくるようになって行きます」
(3)『日本GP』は軽自動車のイメージを決定的に変えた!
――二日間で17万人もの観客が押し寄せたといわれている『第二回GP』ですが、いま、このレースを振り返ると?
「この連載の35回目で、このレースの予選について語っています。そのときぼくは、スバル・ワークスチームの一員として、“ウチぐらい頑張って今日まで来たところはないだろう”と自負していた。しかし、それはとんでもない思い違いと思い上がりでしたね。スズキも、そして新参のマツダも、(スバルと)同じような性能になるくらいに研究していた。軽自動車という枠組みで、どのくらいのタイムが出せるのか。その性能比べが三社とも似たような水準で、それを知って驚嘆しました」
「1963年に、いわばバタバタと『日本GP』がスタートして、そこから一年が経って……。たかが400cc以下というクルマで、驚異的というよりも、ほとんど“狂気”のような(水準にまで達した)自動車に仕立てていた。日本のメーカーには、そんな技術力があったのですね。これは凄いことですよ、それも50年も前にね」
――そんなファナティックなクルマを操って?
「そう! そういう“危ないクルマ”で、レーシング・コースをブッ飛んでいた連中も、同じく50年前にいたので(笑)」
――この頃のクルマ(レーシングカー)は、やっぱり危なかったですか?(笑)
「何というかな、総体的には“危ない”という表現になるのでしょうが(笑)。でも、それは今日のような高度なレベルになった自動車と対比するからで、その時代には“こんなものか、もっとコーナリングのいいクルマはできないのか”程度の感覚でした。そして、そういう不安定なクルマを縦横に操作するのも、ドライバーの腕のうちとも思ってました。ちょっとヘンかな(笑)。とにかく、スピードは出るようになったけど、“曲がらない、止まらない”。そういうクルマではありました」
――なるほど!
「でも、《鈴鹿》の観客は、ぼくらが周回するたびに、どよめいていましたよ。まだ、マイカー時代に入る前で、“クルマ体験”を自身で実際にしている人は少なかったはず。それでも、このときに凄い歓声が沸き上がったというのは、それまでに何となく持っていた軽自動車のイメージが、ここで決定的に覆されたからでしょうね」
――もの凄いものを見たぞ!と?
「ええ。軽自動車で、こんなことができるのか! それと、この400cc以下のレースというのは、ぼくが出場したから言うのではなく、このGPでは、最も接近戦でバトルが行なわれたカテゴリーでした。参加した三メーカーの技術や力量が接近していたし、終わってみても、1位と2位の差も4~5秒しかなかった。小関にしても、6周目でやっと片山を競り落とし、ようやく最終周で、3位の望月を8秒離した安全圏内に入れた」
――もう一度、しつこく(笑)キーワードとして“二輪”を持ち出します。どうなんでしょう、リキさんのレーサーとしてのキャリアで、二輪との接点があった最後のレースがこれだったのでは? また、日本レース史としても、人(ライダー/ドライバー)であれ、各種のノウハウであれ、二輪と四輪がさほど“分化”してなかった最後のレースが、この『第二回GP』であった。こういう見方はいかがでしょうか?
「まあ、半分は当っているでしょう。ただ、それはメカニズムの面においてです。二輪の経験は、ぼくがレーシングドライバーとして現役であった時には消えることなく、ずっと応用できましたから」
――あ、そうなんですね!
「事実としてこの頃は、日本の四輪レースのほんとの創生期ですから、走り方やマシンのチューニング・プロセス、勝負の駆け引きなど、経験を積んだ二輪のキャリアの“ある/なし”は、たしかに大きな違いになりました。ただ、さっきも言ったように、この時点で、四輪で速く走る能力を磨いていた“四輪育ち”のファスト・ドライバーも台頭していた」
――二輪のキャリアなしで速い!というドライバーですね。
「ええ、そうです。ウチ(スバル)の小関もそうですし、トヨタの細谷四方洋、式場壮吉、多賀弘明、学生ドライバーからニッサンに入った津々見友彦、プリンスの杉田幸朗、須田祐弘。そして、ジャガーなどの重量車なら横山達……」
「ホンダは、多くの四輪メーカーが国内でシノギを削っているのを横目に、世界のF1に挑戦していきました。そのホンダは別として、国内で二回のGPを経験した四輪メーカーは、徐々に、レースの何たるかを理解し始めます」
「そのマシンつくりの急速な成長には目を見張るものがありましたが、ドライバーの中心は、北野元、高橋国光、砂子義一、大石秀夫、黒沢元治、生沢徹ら、やはり二輪経験者でした。そして、この後にデビューしてくる星野一義、長谷見昌弘も二輪組です。……ということで、“二輪色”がほんとうに薄くなるのは1980年代に入ってからですね」
――ははあ……。
「ホンダの初期のF1にしても、ドライバーはジョン・サーティーズのように二輪出身者です。ですから、オートバイ・レースの経験や素地が四輪のレースと決定的に“分離”するというようなことは、やはり《ない》のです。したがって、いまの時代であっても、そして、目標は四輪レースであっても、(レースの)入り口は二輪からというのは正しいと、ぼくは確信しています」
――『第二回GP』後のリキさんは?
「このレースのあと、ぼくは、ブリヂストンのタイヤテスト・ドライバーや、フォーミュラカー・レースの世界に入って行きます。レースのたびに、ぼくが哲学としていた座右の銘を、ここで紹介します。オートバイ世界GPの全盛期に本田宗一郎さんが常に言われていたことですが、それはこういう言葉──。『レースってなぁ、速く走りゃあいいってもんじゃねえ、速くゴールするもんだ』」
――それは、一瞬だけ、あるコーナーだけ、また、ある周回だけ速ければいいというものではない。レースにおいてライダー&ドライバーの成すべきことは、何より『完走』なのだ。こういう解釈でよろしいでしょうか?
「モーターレーシング、とくにロードレースというのは『人間の叡智が結集したマシンと、それを操る人間の能力の限界を競い合う、類い稀なる競技』です。ですから、たとえばそのレースが10周という規定であるならば、10周のすべてにわたって、マシンと人間の総合能力を最大限に発揮していく。5周だけトップでぶっちぎったって、それで終わってしまったら何にもなりません」
「ロードレースは、ボンネビルの速度記録のように、一人だけで絶対最高速度を出すこととは違います。また、マシンが介在した『人と人の勝負』でもあります。ですから、規定通りの周回をスタートからゴールまで消化する『完走』がすべての基本。そうやって完走したときに、初めて、その“上”が見えてくるものなのです」
第三十九回・了 (取材・文:家村浩明)