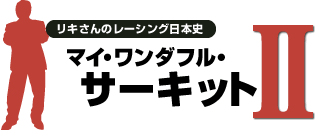耐久レースの大きな効果
――前回は富士スピードウェイで再開した日本GPは、どのような内容であるべきか、という課題から大馬力マシンによるハイスピードのスプリントか、いや自動車技術発展には耐久性を重んじる競技が望ましいなど、混沌とした中で、今度は世界で三つ目になる24時間耐久レースを開催することになった。まさに、行け行け!ニッポンの話(笑)と、その耐久レースに集中したトヨタはついに日本GPを見限った。トヨタ不参加の1967年GPは、日本の自動車レースが始まってから最も精彩を欠く内容で、GPを頂点とするこれから先のレース方針も迷走し始めた内容でしたね。
「そうです、とにかく華々しく開場して、たった2年目ですよ。要するに、鈴鹿から船橋、富士スピードウェイと次々に誕生して、これは新潟の間瀬サーキットや青森の陸奥湾スピードウェイなど、地方サーキット開場の流れにつながっていくのですが、走る場所が増えるのは結構だけれど、どのような種類のレースが中心になるのか、逆に解らなくなってきた。カートレースも始まりだしたりしてね」
――そういった背景で、富士で始まった24時間レースが耐久レースという新たなジャンルを牽引した?
「いえ、それは正しい分析ではありません。鈴鹿では、どういったカテゴリーをメインにしたら良いのか、大変な苦悩があった。何しろ日本GPの開催が富士というか東京圏に移ってしまったのは大きな痛手ですから。そこでテクニカルコースの鈴鹿サーキットにふさわしく/多くのチームクルーが参加できる/マシンの製作や改造がし易い/市販車にフィードバックできる技術が大きい、などの要素が広いレース内容とは何か、という考えから、コースの周回数を基準にするスプリントレース、要するに短距離競争ではなく、数百kmあるいは何時間というような長距離、長時間を競う競技を鈴鹿のメインイベントにする方向にしたのではないかと思います。それは1966年に早くも“鈴鹿300km自動車レース”、500km、1000kmのイベントに成長していったのです」
――そうだったのですか、私は富士24時間からと思っていましたから。それで、鈴鹿が300キロや500キロなら、こっちは24時間だぞっ!て(笑)。
「そう張り合ったわけじゃないだろうけど(笑)、鈴鹿では既に一年前に耐久レースを実施し、このカテゴリーを魅力あるイベントに育てるのに熱心だったからね。ただ、四輪自動車レースが始まって3年目に早くも耐久レースを実施できたのは鈴鹿にノウハウがあったからで、富士の初めてとは違うのです」
――ほー、鈴鹿ではずっと前から耐久レースを
「えー、オートバイ部門でね。既に二輪は世界のロードレースを席捲しつつあって、そこへ鈴鹿も出現したけれど、国内のオートバイレースはどのようなマシン、どういったレベルが適しているのか、やはり方針が定まらず、サーキットは出来たけれどクラブマン向けのレースがなかった時期があったのです。そこから、市販車を軽度にチューニングしたマシンで長時間走れるレースで底辺を広げていこう、という趣旨で1964年に18時間、翌年には24時間レースを開催していたのです」
――えっ、オートバイで24時間レースがあったのですね! ぜんぜん知らなかったなぁ。今でこそ世界耐久レースの8耐で知られる夏の祭典ですが。
「今年も7月末に39回目となる8耐は大盛況でしたが、これのルーツは52年前に芽生えたのです。でもねー最初の18時間、24時間は大変な目に合ってねー」
――リキさん、これも走っていたんですか
「いや、そう走ってばかりいませんよ(笑)。もう二輪は現役じゃなくて、MFJオフィシャルとして主催者側でしたから。
とにかく順位も周回数も混乱しちゃってねー(笑)18時間のときなんかレース終わって3、4時間経っても結果が出せない。結局、各チーム独自の記録と照らし合わせたりして、つじつま合わせたりね。四輪と違い何十台ものオートバイがゴッチャゴチャに走るのを目視とストップオッチで記録するのだから、もームリッ!(笑)。それでも懲りずに翌1965年には24時間レース実施しちゃうのだから」
――前年の失敗を改善して、もっと上のレースを、と。
「ええ頭の中は改善されてもねー(笑)。結局は物理的に正確な記録は難しい、24時間レースも結果発表ではトラブル続きで、その後、電光カウンターなどの計測器が発達するまでは人工的計測(記録)が可能な範囲の距離や時間のレースに落ち着いていったのです」
――各サーキットが独自の改善で耐久レースが確立されていった
「富士は今回ストーリーの1968年の24時間から全日本富士1000キロなど、鈴鹿は300、500、1000キロに加え、それぞれのコースレイアウトを加味した耐久レースを充実させていったのです。この流れは正解だったと考えます。GPとクラブマンのサンデーレースなどですが、その中間に耐久レースはビッグイベントの地位を確立していったのです」
モンスターマシン進出の背景
――それは肝心のGPの内容にも影響していった?
「とにかく前年(1967年)のたった9台のぶざまな内容を何とかしなければGPの将来は無い! とくに主催側の危機感は大きかったでしょう」
――新たなGPの方針が定まってきた?
「そんな簡単にまとまるような才覚あるメンバーの集まりじゃない、おっと言いすぎた(爆笑)。とにかくね、耐久レースの要素を無視できなくなった影響は大きいでしょう。それと、トヨタは2000GTの市販開始や、それをベースの耐久レースマシン、トヨタスポーツ800の登場でレース活動の場面も広がってきた。それで、日産の一人舞台、外国のレーシングカーばかりに翻弄されるのはトヨタとして座視できないでしょうね(笑)。これは僕自身の分析ですが、ヤマハ発動機との連携が成功し2000GTは期待以上の評価を得たこともあって、ヤマハが関わってレーシングカーの開発をすることになったのでしょう」
――それが、のちに数々のストーリーになるトヨタ7(セブン)の始まりですね
「そうゆうことになります。富士SW初のGP(1966年)はプロトタイプスポーツカーで始まりましたが、トヨタは翌1967年5月に市販できる状態まで進んでいる2000GTをレーシングチューンするのは、かなり制約があるでしょう。一方、プリンスのR380は日産との合併話もあって市販スポーツカーにする目標もないでしょうから“レースに勝つ”ためのチューニングは大胆にできますね。プロトスポーツといっても両者の生い立ちが違います」

GP復帰にトヨタが開発した初の本格的グループ7の3リッターレーシングカー・トヨタ7(写真上)。
G7レーシングカーの登場は街のコンストラクターやプライベートチームがS800などの母体を改装して製作の7カーへと波及した。林みのる氏が製作したマクランサは、その代表作で現在のコンストラクター『童夢』の基盤となった。
――なるほど、生い立ちですか、そうなるとトヨタの次の目標は完全なレース用マシンに特化できる。
「とくに1966年と1967年の日本GPは、プロトタイプスポーツカー中心だったのが、1968年からはプロトタイプレーシングカーも加わることになった。この辺りを整理しておかないとモンスターマシンばっこ(跋扈)の話や日本も世界のレース界の潮流に流されていく状況が解らないでしょう」
――多少、横道でもお願いします。
「日本の自動車レースは欧米に遅れている、と言いますけど、現F1が体系的に始まったのは1950年で、日本も、その13年後には鈴鹿で自動車レースが始まった。欧米は戦前からのレースが母体ですから、確かにレベルや社会環境は違うけれど、それでも戦後の新たなレースの在り方を巡って、F1のエンジン規定でも1500ccだ3000ccだ、スポーツカーはこうだああだ、とにかく1950~60年代は車両規定やレース内容がごろごろ変わる時代でした。これは戦後に自動車が急速に普及し、大中小問わず自動車メーカーが生まれ、レースの場で性能を誇示し、市場獲得が激化する時代でしたから。今でこそフェラーリやポルシェですが元は弱小メーカーですよ。そうなると、F1に出ない/出られないメーカー(チーム)はスポーツカーレースやラリーもそうですが、得意な競争のジャンルで優位に立とうとします。その結果、車両規定やレース運営にも影響するのは当然です。
FIA(国際自動車連盟)車両規定の区分を参考に示せば、大量生産されている市販セダンに軽微な改造をする=グループ1、大幅な改造=グループ2、市販2座席スポーツカー(GTカー)=グループ3、を筆頭に新しい区分(車両の種類)は次々に増え、同時に生産台数や改造などの規定がどんどん変わりますから日本はそれに振り回され、何が、どうあれば日本に適したレースか? なんて判断できませんよ」
――この分類でいくと従来のGPは、グループ6のプロトタイプスポーツカーですから、基本は市販車に近い構造、即ち、タイヤがはみだしていなくて屋根もあるクローズドボディーでヘッドライトも2つの座席もある、ウインカーも付いていてエンジンは2000ccですね。
「そうです、ところが前年の1967年に、いくらトヨタが出なかったとはいえ10台にも満たないGPでは先がないないっ!(笑)。何としても参加を増やす策として今までの参加車両クラスにプロトタイプレーシングカーを加えたのです。これはFIA区分の新しいジャンル、グループ7で、グループ6のプロトスポーツとは丸っきり異種のマシン規定です。
基本構造は、座席は2つ/ホイールが露出していない/屋根も要らない/最低重量制限なし/エンジン排気量なし、要するに走る、曲がる、止まる、に必要な完全な装置があれば良い、というマシンです」
――地上を走るためだけの究極のマシンという考え方ですね。
「まあそうですが、欧州では自動車レースのマシンとして、こうゆう発想はないでしょうね」
――アメリカのカンナムレースがこれですね。
「はい、米国はインディ500やデイトナのストックカーなど主として楕円形のオーバル・レースが盛んですが、米国型ロードコースというか、CAN‐AM(カナディアン‐アメリカン・チャレンジカップ、通称カンナム)、名前の通り1966年から始まった米国とカナダで年10戦行う米国最高峰のスポーツカー選手権です。
今、ホンダがエンジンを供給するF1のマクラーレンの前身がシボレーエンジンを搭載して連勝する一方で、ジョン・サーティーズなどF1やインディのビッグドライバーの出場と自動車レース最大の賞金など“全てが大迫力”の売りが脚光を浴びたのです。
その人気はシャパラルやシャドウなどの米国のコンストラクターだけでなくポルシェやフェラーリ、ローラ、BRMなど欧州勢も参加するほどでしたが、このレースマシンからグループ7規定ができたわけです。
エンジン排気量は無制限、製作の自由度が大きい通称7(セブン)カーと呼んだこのジャンルは、日本に芽生え始めた街のコンストラクター、プライベートチームが逸早くホンダS800やブルーバードなどのエンジンを利用してユニークなマシン製作が一気に広がる程の影響を与えました」
――その後、童夢に発展していくマクランサやコニリオですね。そういったコンストラクターやプライベートチームの7カー造りが始まり、日本GPにも影響した?
「本格的な影響になったのは、日産、トヨタが一斉に7カー開発にのり出し、1968年GPをにぎわせてからですが、このGPにホンダS800エンジンのマクランサやデルRSBシャーシーにトヨタの2600ccV8を載せた7カーも参加していますから、マシン製作のし易さでしょうね。実は僕もね、偶然のチャンスというか、極限まで排気量アップしたS800エンジンの7カーでエントリーさせてもらったのだけど、予選も満足に走れなくてね、えーい、この話はヤメ!(爆笑)」
――リキさんの予選落ちも聞きたいですが、まずはモンスターマシンに戻りまして(笑)。トヨタも本格的にのり出した、日産はプリンスのR380があって、体制とすれば日産が有利?
「1968年GPの参加車両は、グループ6(G6)とG7ですが、G6のプロトタイプスポーツカーは前年の2000ccから3000ccになり、G7のプロトタイプレーシングカーはエンジン排気量制限なしですから、条件を比較すればG7の方が有利でしょう。しかしポルシェカレラに代表されるよう数々のレースで鍛えてきたG6に対し、G7はどんな大排気量エンジンでも良いというものの、熟成されたG6エンジンに勝るものがあるかどうか疑問です。とくにレース距離は、前年の60周から80周に変わりましたから、その長距離に耐え切れる大排気量エンジンは数少ないでしょう」
――そうなるとマシン開発にはゼロから出発のトヨタは、どこを、何をターゲットにするか難しいでしょうね。多分、日産は2000ccエンジンのR380をもっと向上させるでしょうから、トヨタは3000ccのG7で対抗しよう、との狙いで?
「そこなんですよ、僕にも解りませんねー。G7は排気量無制限ですからカンナムのように5000、6000ccでも構わないですからね。ただ、世界のレース用エンジンの基準は大きくても3000ccですから、仮にカンナムマシンを購入して参加する者が出てきたとしても、排気量ばかり大きい米国車エンジン特有のV8気筒OHVが圧倒的な性能を発揮するとは思えないでしょう。やはり排気量は小さくてもDOHCなどの高度なエンジンに分があるとの考えが自然でしょうね。
――なるほど。
そう分析すると、トヨタが新しいレースマシンを開発するのは、日本GPで日産R380や世界的レーシングカーを購入してしまうプライベートに対抗できるものでなくてはなりません。かといって完成させたばかりの2000GT以上の開発なんか続けてできるわけありません。そういった立場からすれば日本GPがG7でも良いというのは渡りに船。しかし、新規開発車は日本GPだけのものでなく、いずれは欧州のプロトタイプスポーツカーに準じたG6に発展でき、著名な耐久レースやスポーツカーレースに出られるようなマシンの母体でありたいのがトヨタではないでしょうか。
「そうであるとすれば市販車並みの保安装置も不要、自由製作が可能なG7は恰好のジャンルですが、エンジン規模を選定すればスポーツプロトタイプに準じた排気量上限の3000ccを目標にするでしょうね」
――日本GPにG7を加える計画が前々からあったのなら話は別ですが、低調だった1967年GPの改善策でしょうから、そうなると、このGPが終わってからでないと車両規則は決められませんね。
「当然そうゆうことですね。多分、5月のGP後、遅くとも7月初旬には主導的内諾ができていたのでしょうね。GPクラス以外のツーリングカーやGTなどのクラス規定が整ったGP開催要綱の正式発表なんか後になったって構わないのですよ。そういった日程であっても翌年3月頃にはレースコースを走れるマシンに仕上がってなければなりませんね、それでも僅か8カ月の短期間で、日本の自動車メーカー、どこも経験も予想も無かったモンスターマシンが何台も登場したんですから! あの時代のニッポンって、いけいけガンガン(爆笑)」
――そうですよね、レース決勝の日まで数えても10カ月です。それほど次のGPの覇権争いの狙いは、トヨタの雪辱か、日産の復権か、という?
「既に本格的なレーシングマシンを所有する日産、世界に誇れる2000GTを世に出し、耐久レースの覇者がスプリントクラスも制す、それぞれの野望があるのは当然ですが、それだけで、ここまで熱くなるか、ということです」
――と、いうことは、もっと他の影響が?
「ええ、1966年GPでプリンスやトヨタに対抗するポルシェ906(瀧進太郎)、フォード・デイトナ・コブラ(酒井正)、アバルトシムカ(佐藤清人、オーナー:金原達郎)などのプライベートが出現したのですが、この時点ではプリンスR380のベストラップは2分05秒辺りで、5000ccエンジンのコブラでも、所詮は市販車の域は出ず、ワークスマシンの足元には及ばないと言われたものです」
――ドライバーがマシンに負けている?
「かどうか、ともかく超一流マシンを買っても、あくまで市販モデルであり、日本での整備やチューニングには限界がある。しかし、カネさえ出せば380や2000GTのタイムより強いマシンが買えることも解り始めました。日本も欧米のレース状況やマシンのレベルが知るようになった、ということで、ようやくモーターレーシングの知識も向上してきたようです」
――1967年GPで生沢さんが勝ったのは、そういった流れの一つでしょうか。
「前の話にもありますが、日産のR380A2になった4台と3台のポルシェ906(瀧、生沢、酒井)や5500ccエンジンのローラT70など僅か9台のスタートだったものの、結果はポルシェ906(生沢)が1位、2位R380A2(高橋国光)に約1分半の大差で3位は1周遅れです。この時、R380A2の予選タイムは2分02秒で、プリンス時代より3秒ほど向上しましたが、ポルシェ(生沢)は1分59秒を叩き出し、他のポルシェ(酒井)も2分02秒ですから、もはや、カネさえ出せばワークスマシン恐るに足らずです(爆笑)。ドルの山を送れば日本のメーカーが大資本かけて開発したマシンを打ち負かせるレーシングカーが送られてくるということです」
――でも、そんなこと出来る人、何人もいないでしょう
「メーカー筋も僕もそう思っていたのです。でも、瀧さん(進太郎)が、ドライバーを退いて大々的なレーシングチームを結成したのです。その内容が凄い。まず彼が二度のGPに使ったポルシェ906に加えてローラT70MK3、それも米国車エンジン5800ccと6300ccの2台、ポルシェ906の進化型910を1台、それと前年GPを走った安田銀治さんの5500ccローラT70MK2を買い取り、計5台の前代未聞のプライベートチームです。ドライバーも田中健二郎、長谷見昌弘、酒井正、片平浩、生沢徹の5人をそろえワークスチーム最大のライバルになったのです」
――ポルシェ一台だってびっくりなのに、瀧さんて、どこからそんな資金が?
「確かに、彼個人としても数千万円の用意は必要でしょうが、この時代、日本が世界の経済大国にのし上がったのを象徴するようにモーターレーシングが脚光を浴び、多くのスポンサー協力を得ることが出来たこともあります。その中でもブリヂストンタイヤの援助は大きかったでしょう。タイヤメーカーも覇権を賭けていたのです」
――陰で動いたのはタイヤメーカーということでしょうか。
「名神高速道路が全線開通し、東京・名古屋の東名高速道路完成で新時代の東海道が一年後に誕生する時代です。名神道路だけでも、路面にタイヤが破れ飛んだゴム切れが散らかっているのが珍しくない有様でした。高速走行に耐えられるタイヤの開発は、どのタイヤメーカーにとっても急務で、鈴鹿から船橋そして富士へと広がった自動車レースは正に強靭なタイヤ造りに恰好な試験場でもあったのです。
BSタイヤと僕の関係は、このストーリーに度々登場ですが、そのタイヤ開発(専ら高速用ですが)のテストドライバーが僕だったのです。無論、BSタイヤを納入している自動車メーカーでも社内テストはしていますが、僕はBS直属でした」
――それがレース活動にも影響されて。
「まっそうですが、とにかく鈴鹿、谷田部試験場、ガンガン走るたびにタイヤの向上は目を見張るほどでした。しかし、タイヤメーカーだけのテストも限界にくるのです。テスト用の車両はタイヤメーカーが購入するのですが、もっと最高速度が高い市販乗用車を望んでも、国産GTや最大排気量車をチューンしても平均速度200キロを2~30分維持できないのです。そういった状況の時に、瀧さんがポルシェ906を購入し、1966年GPの後、富士SWでのトレーニングの際、テストケースにBSが開発中の高速用タイヤを使ってみてもらったのが糸口なのです」
――そうなるまでのレースタイヤは?
「最初の富士での日本GPのGPクラスでは、圧倒的にダンロップで、トヨタ2000GTはグッドイヤー、ジャガーEタイプは市販車サイズでようやく出始めたBSですが、レーシングBSは皆無です。それが1年後のGPになると瀧とのテスト開発が進み、(僕はお払い箱ですが、クシュン)、瀧、酒井、生沢の3ポルシェがBSを使い、さらに生沢が優勝です。
日産のR380A2はプリンスR380のダンロップからファイアストンに変わっています。そして1968年GPになると、ダンロップ、ファイアストン、ブリヂストンとタイヤメーカーも覇権を賭けるのですが、タキレーシングのスポンサーはBSですから、当然としても、300km/hで疾走する5000cc、6000ccのモンスターマシンを支える6.60/12.50-15の巨大サイズ純国産レーシングタイヤが登場するまでになった日本の技術進歩に、もっと気づかなくてはなりません。ビッグマシン、スゲースゲーの幼稚さでは困るのです(爆笑)。
それで(笑)、タキチームがこれほどの体制を敷けたのは、彼が実家から持ち出した大金もあるだろうけれど(笑)、BSが陰じゃなく表で大きく支え、こういった活動にコカコーラなどの飲料水や化粧品その他多くのスポンサーの支援があったからです」
――これまでのいきさつがよく解りました、それでどのような闘いが?
「結局G7規定導入の効果か800ccから6300ccのマシンによるエントリーは35台と大幅に増えたのですが、その内容は次回のお楽しみー、ということで」
――次回もかなり話題が豊富なようで(笑)楽しみにしています。
第五十九回・了 (取材・文:STINGER編集部)
制作:STINGER編集部
(mys@f1-stinger.com)