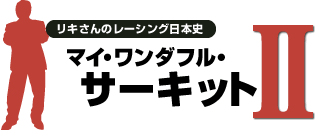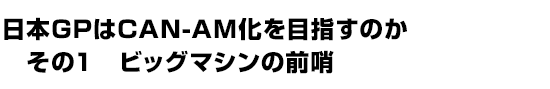――まずは、5月28日のインディ500で優勝した佐藤琢磨をお祝いしたいと思います。琢磨選手は、マカオGPつながりの後輩でもあることから、大久保さんの感慨もひとしおと思います。偶然、現地でその瞬間を拝むことができましたが、新聞の号外が出てほしいと思いました!!
「本当に素晴しいことですね。せっかくの快挙ですから、この偉業が広く伝わってほしいと思います」
――本当ですね!! さて、前回は、富士スピードウェイが50周年の記念を締めくくるビッグイベントや、西ゲート前に建設された『モータースポーツ顕彰碑』の除幕式など、久しぶりに賑やかなモータースポーツシーズンの幕開けでもあったところから、1968年以降のGPストーリーを小休止しました。今回から1969年日本グランプリに話を戻しましょう。
「まさに、古きを訪ねて新しきを知る、ということですね。『モータースポーツ顕彰碑』の意義が広く理解され、モーターレーシングへの理解が深まれば、建設のお手伝いをした者として嬉しい限りです」
――富士スピードウェイが50周年ということからも、いろいろ思い出すことも多かったのですが、何せ富士スピードウェイで育った私にとっては、富士スピードウェイ開業直後のインパクトが大変大きく影響を受けているのです。
「編集長は、富士スピードウェイ開場当初の話になると目付きが変ってきますねー(爆笑)」
――ええ、レースに感化されだした年齢でもあって、レース車のエンジンサウンドがいつも耳についています(笑)。
「おっおっ、それはホンモノだ(爆笑)。でも、富士の前に鈴鹿もあったでしょうに、編集長は富士に特別な思い出や感激があったようですね」
――鈴鹿サーキットは、1976年にモータースポーツ専門誌の『auto technic』の編集部員になるまで行ったことがありませんでした。なので、レースのイメージが富士でできあがってしまったわけです。私にとって、鈴鹿サーキットという存在は、遠い憧れの国みたいな印象でしたが、スポーツカーかフォーミュラかといわれれば、どちらかというと、スポーツカーが好きだったのは、富士スピードウェイ専門だったためと思います。その後の富士グランチャンピオン・シリーズに惹かれたこともありますが、1960年代終盤、特に1969年の日本グランプリには強烈なインパクトを感じたからだと思います。
「なるほど。その後、これは明確な区分けはできませんが、鈴鹿はフォーミュラカークラスの導入、富士は、レーシングスポーツカーやストックカーもありましたね。それぞれのコースの特色が活かせるカテゴリーが出始めていきました」
――1966年に日本グランプリが鈴鹿から富士移った頃、私はレースに興味を持ち始めて、『オートスポーツ』や『カーグラフィック』などの専門誌を買うようになりました。その記事展開も、『年に一度の日本グランプリが中心』という大前提の扱いでした。さらに、インパクトが大きかったのは、1968年と1969年に行なわれた『日本カンナム』でしたが、本場カンナム(以下、CAN-AM)のオープン2座席か、もしくは、ル・マン24時間を中心とするスポーツカー耐久選手権用のクローズドボディか。いずれにても、F1ではなくスポーツカーでした。
「当時は、CAN-AMやル・マンなど、欧米の自動車メーカーが力を入れていましたね。つまり、資金が大量に流れ込みますから性能競争に拍車がかかります。必然的に色々なマシンが出てきますから自動車レースは隆盛を極めます」

1968年の日本GP、富士のS字を駆け上がる“怪鳥”日産R381。この半年後に行なわれた“日本CAN-AM”には残念ながら出走しなかったが、“シボレーエンジンに頼る苦肉の策は、大排気量化に拍車をかける役目を担った。下の写真は、3月に富士スピードウェイで行なわれた『富士ワンダーランドフェス』にて。
――私のように、金網の外から見るファンとしては、富士1000kmとかNETスピードカップなど、すべてのレースが日本GPを目指す実戦テストの場だと勝手に思い込んで固唾を呑んで見つめていました(笑)。そんな状況の中に突如現れた異様なCAN-AMレースのインパクトは大きかったです。
「ああ、そのCAN-AMレースというのは1968年5月の日本GPのあと、11月に行なわれた“ワールドチャレンジカップ富士200マイルレース”のことですね。このイベントも基本的には富士SWの開場年(1966年)10月の日本インディーと同じく臨時的というかスポットイベントでしたが、日本GPも、とくにニッサンがシボレーエンジン積んだR381で優勝して、大排気量マシン時代到来に合わせたようなものでした。
このレースは、日本のレース草創期から米国型レースの普及に熱心な105マイルクラブ(後の日本オートクラブ=NAC)の塩沢進午さんが大井オートレース場で米国で超人気の大型乗用車(セダン)をベースのレースを模したイベントを手がけてね、それも鈴鹿の第一回日本GPの半年後でしたが」
◆ストックカーレースの存在
――ちょちょっと待って下さい(笑)。私が仰天したCAN-AMとセダンのレース、どーもピンとこないのですが。
「(笑)こうゆう話は簡単にいかないんですよ、まあ、お聞きなさい(笑)。それで、1950~60年代、まさに自動車大国の名に恥じない(笑)米国の乗用車はバカでっかくてね、このフルサイズのレースカーをストックカーと呼んでいたようですが、ニッサンセドリックやトヨタクラウン、いすゞべレルなどをベースにした日本唯一のアメリカンレースがあったのです」
――あっ、そうなんですか、日本CAN-AMの前座で、エキジビションをやったのを観たことがあります。残念ながら、レースにはならずに、スタート前のフォーメーションラップのように、編隊を組んで走るエキジビションでしたが、それが好奇心をあおって一生懸命観た気がします。その後、いまは消滅してしまいましたが、陸奥湾サーキットとか、琵琶湖のジムカーナ場とかでやった一風変わったレースでしたよね。
「お、知ってることは知ってるんでね(笑)」
――日本CAN-AMの前座の模擬レース以外、実際には見たことがないですが、鈴木誠一と、本場アメリカからやってきたタイニー・ランドの闘いが雑誌でも話題でした。あ、そういえば、鈴木誠一さんがデイトナ500の前座の確かデイトナ200に参加した記事に興奮したのを思い出しました!!
「そうそう、海外といえば、CAN-AMとル・マンだけでなく、アメリカのストックカーとのつながりもありましたね。そもそも富士は計画段階でオーバル・コースでしたが、それは、今年、佐藤琢磨の優勝やF1のワールドチャンピオンであるフェルナンド・アロンソの挑戦で盛り上がったインディ500のインディアナポリス・モーターレースウェイではなく、NASCARのストックカーの総本山である『デイトナ500』の舞台であるデイトナ・スピードウェイと同じ、三角形の“おむすび形オーバル”でしたから」
――しかし、それと先ほど大井レース場? でしたか、そんなサーキット、初めて出てきましたが。
「本場のストックカーレースというのは、インディ500マイルレースと同じくオーバルコース(楕円形)をグルグル回り、ぶつかり合いも当たり前の格闘技要素が売りです。鈴鹿のようなロードコースは稀で、大方1km程度から4kmほどのコースですが、幸いというか日本には鈴鹿の以前に、一周500m位のオーバルコースを使うオートバイのギャンブルレース場がありますから、大井(東京都)や川口(埼玉県)などのオートレース場を使った小型ストックカーレースともいうべきものがあったのです。
まあ、本場にはほど遠い規模ですが、富士SWの元々の建設構想は米国を代表のストックカーレースのナスカー(National Association for Stock Car Auto Racing)の日本版を造ることでしたから、その底流はあったのです。また、後に富士SWでストックカーがシリーズ戦になるほど一定の人気を得たことは事実ですし、1966年の日本インディや編集長がショック受けた1968年の日本CAN-AMの開催は、NAC(日本オートクラブ)の塩沢進午さんが深く関与しているのですが、これは日本にも早くから米国型レーシングの流れが存在していたということで、そういった幾つものレーシング構想の流れが入り乱れる中、日本GPは、その場その時代の流れに翻弄されてきたように思えるのです」
――ほほー、そのような色々なレースの中から日本GPにふさわしいカテゴリーは何かとなれば、ひとつを選択するのは難しいですね。リキさんの仰る“翻弄されるGP”が良く解ります。ただ、富士SWでのグランプリは、グループ7の2シーターレーシングカーが定番になって、それがエスカレートしてきたわけで。
「まあ、そうゆうことですね。これは本ストーリー『第59回 ビッグマシンに突入した日本グランプリ』で詳細が載っていますが、2000cc中心のプロトタイプスポーツカーでは参加台数が増えず、折りしも台頭してきた米国のCAN-AMレースのマシンに目をつけたということです」
――そうでしたね。マシン製造規定が大幅にゆるく、それまでの欧州型というのか“マシン性能の公平性”が中心の車両規定が根底からひっくり返されるような(笑)。
「確かにそうですね。そのグループ7規定で1968年日本GPをやってみた。それでも新型マシン製造の時間的課題もあってニッサンR380やポルシェ910などの安定したマシンが有利だろうと思われていたところへトヨタの3000ccニューマシンの噂が本物になるや、シボレーエンジンの5500ccニッサン、これぞ本邦初のカンナムマシン(爆笑)や、なにおーっ、俺がもっと凄いマシン買うぞーって、6000cc超エンジンのプライベーターが現れたり、マスコミはいいメシのたね(笑)。結局、何が何だかゴッチャゴチャで」
――そのGPが終わった後に本場のカンナムマシンが上陸しましたから、こっちはもう(笑)。
「そう5月の日本GPの半年後の11月ね。正式には前に述べた『ワールド・チャレンジカップ・富士200マイル・レース』ですが、通称日本カンナムですね。GPで勢いづいたビッグマシンのある意味ブームに、“いやいや、本物はこんなもんじゃねーよ”とばかりに呼び寄せたCAN-AMドライバーとマシンは11チーム、だったかな。米国のカンナムシリーズが終了し、レースオフシーズンに入った11月末でしたね。
――忘れもしない11月23日です!!
「あはは、サスガですね(爆笑)。マーク・ドナヒューやアル・アンサーなどの看板ドライバー、マシンもローラT70(7000cc)、マクラーレン(6200cc)などの、これぞアメリカンのビッグマシンでしたね。
――そうですそうです!!
「残念なのは、CAN-AM象徴のマクラーレン・ワークスやシャパラルとジム・ホールなど、多くの参加予定がシリーズ最終レースの事故で来れなくなったことでした」
――それに日本側は3000ccのトヨタ7が出たのに、ニッサンは不参加でしたね。
「ニッサンの不参加事情は解るような解らないような(笑)ですが、トヨタが福澤幸雄、細谷四方洋、鮒子田寛ら5台のトヨタ7を出場させたのは立派でしたよ。コースはバンクを使わず日本インディの時と同じ4.3km左回り。75周(322.5km)でした。当初、僕はこれもインディのようなCAN-AMの真似ごとで終わるんじゃないかと邪推してたのですが、真剣なレース内容でしたね。編集長がのめりこんだのが良く解りますよ」
――ええ、1968年GPのあとにやってきた、本物のCAN-AMを見て、想像以上の速さと迫力には度肝を抜かれた感じでした。
「感受性が一番強い年頃に悪いモノを見ちゃったんではないですか(爆笑)」
――だから未だに、あの時の続きのまま、良かったのか失敗したのか(笑)。
「まあ得意なことやっていれば、何とかなるのではないですか(笑)。それで日本カンナムは75周を走りきったのはV8気筒7000ccエンジンを積んだマクラーレンM6Bのピーター・レヴソンでしたが、他はすべて周遅れでした。まあ3000ccのトヨタ7には辛いレースだったでしょうが、予選、決勝を通してCAN-AM勢の最速ラップは平均195km/h速さでした。左回りのショートコースとフルコースでは違いますが、この半年前の日本GPでニッサンのシボレー5500ccが記録した最速ラップが191km/hで、このCAN-AMの記録は、その後、長らく破られませんでしたから、本場マシンとドライバーのレベルには、日本のレーシング界は大きな衝撃を受けたのではないでしょうか」
――その流れは早くも半年後の1969年日本GPに現れるのですね。
「その通りですが、ニッサンにはこのレースにぜひ出てもらいたかったですね。編集長の言うように、このカンナムが翌年のGPに与えた影響は、この時点では解らなかったくらい大きかったですね。半年前のGPでニッサンがシボレーエンジンに頼る苦肉の策にブーイングが目立ちましたが、ニッサンは逸早く台頭し出したカンナムマシンに注目し、それなりの研究開発が進んでいたのではないかと考えます」
――その話で一番強く思い出すのは、左右分割式のリヤウィングを装着して“怪鳥”なんて呼ばれ日産R381で、CAN-AMというのは、こういうマシンばかりが走るんだろうなと思いました。
「そう、その当時、マシンのスピードはどんどん速くなってきて、タイヤ、シャシー、ボディーなどが高出力エンジンを支えきれず走行不安定によるものと見られる事故が目立ったきたものです。それまでのボディー構造は、いかに空気抵抗を減らすかが主眼で、流線型をしたデザインが多かったですね」
――高速になるほど厚くなる空気の壁をどのような形にすれば抵抗が少なくなるかのデザインが多かったですが、車体の下に入り込む空気がマシンを浮き上がらす現象が出始め、その対策にダウンフォースという発想がでてくるわけですね。
「高出力のエンジンが開発されても、その力が充分に活かせない、車体性能とエンジン性能のイタチごっこ。とにかく、カンナムというかグループ7の導入で高スピードマシンが一気に増えました」
――そのころ“ダウンフォース”という言葉が出だして、何のことか解りませんでしたが。
「そうなのです。マシンの下側に流れこむ空気の層で車体が浮いてしまい、車輪の駆動力が弱まり、スピードが落ちるだけでなく操縦不安定になる。要するに空気の流れをボディー上部に流す研究は進んだのですが車体の下側に流れこむ空気の流れがどんな作用をするか解らなかったのです。スピードがどんどん上がりだしてから、この現象への対策が始まりました」
――即ちダウン(down)は下、フォース(force)は力、マシンを路面に密着させる上からの力ですね。
「そういうことです。ボディー後部に羽状のウイングをつけたり、デザイナーたちがそれぞれ思い思いの創意と工夫をした空力付加物が現れ出したのです。特に1968年ごろから高々とウィングが林立するF1マシンが他のカテゴリーに影響を与えたようです。1968年GPのニッサンが車体リアにつけた大きなウイングは二分割で、左右別々に動く構造でした。これはタイヤを路面に押し付ける力を左右のコーナーで独自に作用させる大きなウイングで“怪鳥”などと呼ばれました」
――現代のように、コンピュータの演算がレーシングカー設計の常識になることなど考えられない、また、風洞実験もままならない時代でしたから、手探りの技術開発だったのですね。その結果がボディー形状に現われ、とんがったのがあれば、丸っこいのもある、その違いが外からわかって面白かったのです。
「なるほど。外から見て分かるから興味も深まる、というのはなかなか面白いですね。ただ、それまでは、どうやってスピードを上げるか、やっきになっていた。それが速くなってきたら、今度は、そのスピードを制御するダウンフォースという間逆なことをやらねばならないのだから皮肉だね(笑)」
――現代は、F1に限らず、WECにしても、カラーリングが同じだったらどれがどれかわからないですが、1960年代後半、ダウンフォースの発想が出だした1960年代中頃から10年ほどは、メーカーやチーム毎にそれぞれ違う形をしていました。特に、ボディの大きなスポーツカーに興味を惹かれたのは、“違いが分かる”ということでした。鈴鹿で初めて行なわれた日本グランプリで、ペチャンコのロータスに力さんでさえ驚いたわけですから、金網の外から観ていた私は、まさに毎月買い求めていた自動車雑誌を見る度にカルチャーショックの連発だったのです。
「ちょうどホンダF1の第一期もその頃ですね」
――専門誌が日本グランプリに傾倒していたこともあって情報が少なかったからだと思いますが、正直なところ、F1にはあまり興味がなかったのです。というか知らなかったのですが。
「わっはっは、そうだったんですね。情報の届き方でそういうことになるのか」
――特に、1969年は、日本グランプリと日本CAN-AMの印象が強烈で、いまでも1台1台、一人一人の顔が脳裏に焼きついています(笑)。
「市販のクルマでも同じで、どのメーカーのものか解ったのに、今は銘柄も解りずらい、個性がなくなったねー」
――あ、確かに!! 私は「創意工夫」という言葉に興味があって、だからそれを感じられるものが好きでした。CAN-AMで言うと、圧倒的に強かったマクラーレン・ワークスのM8よりも、本場で怪鳥と呼ばれたシャパラルの方に興味がありました。でっかいウイングもそうでしたが、他にも、全高が膝までしかないペチャンコのAVSとか、スノーモビルのエンジンを4基積んで1輪ずつ回していたマッキー・イットスペシャルとか。
「随分と詳しいですねー(笑)、僕はそんなに多くは知らないけれど、今の時代も、特徴あるデザインのマシンがもっと増えて欲しいね。分かりやすい内容でなければダメですね」
――一方で、ル・マンを中心とするスポーツカーの耐久選手権も、フェラーリ、フォード、ポルシェ、アルピーヌと、それぞれまったく違う形をしていたのも興味深かったです。
「スティーブ・マックィーンの映画『栄光のル・マン』の公開は1971年だったと思いますが、まさにスポーツカーが隆盛を究めていたころですからね」
――ああ、テアトル東京まで通って2回観ました(笑)。そうしたことで、日本GPが富士に移った1966年からニッサンのR380系のR381やR382にも注目しましたが、いろいろな試行錯誤が残ったままのようなトヨタ7シリーズや、いすゞにダイハツなど、今でも思い思いのクルマを出してくれたGPに興味が尽きなかったのを思い出します。
「確かに、色々なデザインのマシンがレースを盛り上げました。今はカラーリングで見分けるしかないのだけど、何でもかんでも塗りたくった化粧みたいなのが多すぎるねー(笑)。第一にスマートさに欠けてるね。ただ、性能が上がってくると、車体構造や空力上の形状からデザインが似てくるのです。車両規則で追い込まれて、自由度が狭くなってしまう、という側面もあるだろうし、これは仕方ないのかなー」
――いずれにしろマシンがどんどん進化する時期を同じくして、私がモーターレーシングにのめり込んでいったものですから、その一つ一つを思い出すたびにマシンの形が鮮明に浮かんでくるのです。
「1968年GPから日本CAN-AMへと、この年は富士スピードウェイを舞台にしたモンスターマシンによって“絶対的スピード!”の狂演が自動車レースの真髄である大きな流れが確立したようでした。一般社会も、この年だったかなー。TVから「♪大きいことはいいことだー♪」ってコマソンが流れてねー」
――ああっ知ってます知ってます。覚えているなー、作曲家の山本直純さんが、大判のチョコレートなのに値段が安いの宣伝で、流行語になりました。
「そうです、そうです(笑)。とにかくね、大きいことはいい、とか、最高速度210キロの東京・大阪新幹線が走り出して4年、スピードの感覚も社会生活に入りこんできた。とくにスピードを表わしたり速さの比較には新幹線が対象で、地上を走る乗り物で一番速いのは新幹線が一般的観念。だから、富士の自動車レースが250km/h以上で走り回るのを知れば“ヒェーッ、こだま号・ひかり号より速いんだってー”、まさにスピードの象徴になる。解りやすいし説明も簡単(爆笑)。また、今では悲惨な話だけど、米国がベトナム戦争へ猛攻をかけ、日常的に戦争の映像が流れたりの世相だから、大きいとか、速い、強い、勇猛といった要素が飽くこと知らず上昇する日本経済の世相にマッチしていたのだろうなー、自動車レースもそういった中にあったからねー、CAN-AM化への流れもその一つでしょう」
――なるほど、奥が深いものなのですねー。単に自動車レースだけの話では終わりませんねー。
「いえいえ、難しい話ではなく(爆笑)、レース、特にグランプリとなればなおさら、自動車という大きな産業の中に組み込まれた存在ですから、一介のドライバーやマスコミの言うことなんか、ムニャムニャですが(笑)、いずれにしても日本GPのCAN-AM化への流れは更に太くなって翌1969年GPの開催になっていくのです」
――では、次回はそのGPの実態について話をしましょう。
1968年5月3日第4回日本グランプリ(富士スピードウェイ) ◆GT(80周) 1. 北野 元 ニッサンR381 2. 生沢 哲 ポルシェ910 3. 黒沢元治 ニッサンR380 4. 横山 達 ニッサンR380 5. 大石秀夫 ニッサンR389 6. 砂子義一 ニッサンR381 8. 大坪善男 トヨタ7(クラスⅢ優勝) 10. 吉田隆郎 ダイハツP5(クラスⅠ優勝) ◆スピードカップ(30周) 1. 加藤爽平 コルトF2B 2. 益子 治 コルトF2B 3. 浅岡重輝 アロー・ベレット 4. 米山二郎 ブラバム・コスワース ◆GT(15周) 1. 都平健二 フェアレディ2000 12. 武智俊憲 ホンダS800(クラスⅠ優勝) ◆T(15周) 1. 大岩湛矣 トヨタ1600GT 3. 田村三夫 スカラインGT(クラスⅣ優勝) 21. 西川 順 ミニ・クーパーS(クラスⅡ優勝) 24. 矢島正則 ホンダS600 ※『日本モーターレース史』より
第六十三回・了 (取材・文:STINGER編集部)
制作:STINGER編集部
(mys@f1-stinger.com)